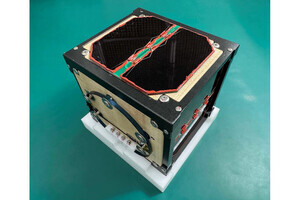筑波大学は6月12日、国際宇宙ステーション(ISS)に滞在する宇宙飛行士の血液検体に含まれる、さまざまな組織の細胞から放出された微量のDNAやRNA分子を「リキッドバイオプシー」の手法を用いて解析することで、体内深部で起こる変化を捉えたことを発表した。
同成果は、筑波大 医学医療系 ゲノム生物学研究室のNailil Husna LPDP Scholar、同・村谷匡史教授らの研究チームによるもの。詳細は、「Nature Communications」に掲載された。
-

今回の研究の概要。(1)11タイムポイントでの血液検体採取。(2)類似した変化が示されたムチン(MU)遺伝子群、ミトコンドリア(MT)遺伝子群のフライト前後のセルフリーRNAの変化の例。(3)体内組織の細胞からの放出や死細胞に由来する細胞外小胞の血中への放出と、その中の細胞外ミトコンドリアを含む小胞の概念図。(画像は、NASA Image Galleryの資料画像を用いて、BioRender.comを使用して作成されたもの)(出所:筑波大プレスリリースPDF)
ISSが周回するおよそ400kmの高度においては、地上の100万分の1程度の重力があり、微小重力(マイクロG)環境と呼ばれる。このような環境に長期間滞在すると、筋萎縮や骨量減少などが起き、人体の抗重力機能の減退が急速に起こることが知られている。
現在、月の開発が活発化しており、アルテミス計画では2020年代末ごろには月面に恒久的な有人活動拠点を建設するとされる。また、その先には火星有人探査も計画されており、こうした月や火星などの低重力環境や、火星を目指す際の片道で(現在の移動技術で)少なくとも半年ほどに及ぶ宇宙船内の微小重力環境での生活において、人体の抗重力機能の減退をどのように克復するかが重要な課題とされている。
そのため、ISSの日本実験棟「きぼう」に設置されている人工重力装置やマウス飼育装置を利用したさまざまな実験が行われ、骨や筋組織が宇宙で受ける変化の分子機構が解明されつつある。さらに、モデル動物を用いた研究により、体内時計や代謝の変化などが起こることも明らかになってきている。その結果として、ヒトでもさまざまな器官や組織の網羅的な解析を実施し、同様の応答が起こるのかどうかを検証する必要性が認識されるようになってきたという。しかし、宇宙飛行士の体内深部の組織を直接調べることは容易ではないことが課題となっていた。
そこで研究チームは、リキッドバイオプシーに注目。同手法は、血液などの液性検体を採取し、その中の「細胞外小胞」(生体膜で包まれた細胞外の構造)に含まれる生体分子を解析し、体内深部の組織や細胞で起こる変化を捉えられる解析技術だ。採血だけで体内の変化を把握できることから、臨床検査への応用を目指した研究も進む。今回の研究では、宇宙飛行士を対象に、打ち上げ前、宇宙滞在中、帰還後にた血液検体を採取し、それを用いてリキッドバイオプシー解析を行い、ヒトにおける宇宙環境応答の統合的な評価を実施することにしたという。
6名の宇宙飛行士が対象とされ、飛行前後とISS滞在中に計11回、血液が採取された。その血漿部分に含まれる細胞外DNAやRNA(セルフリーDNA、RNA)が解析され、宇宙で変化する遺伝子の同定が行われた。同定された遺伝子の中には、特定の臓器や組織で働くことが判明しているものがあることも突き止められた。そうした情報をもとにすることで、宇宙環境に応答する臓器や組織の種類を推定することができるという。
今回の研究では、特に顕著な変化が見られた細胞外ミトコンドリアをより詳細に解析するため、361種類の候補タンパク質が調べられた。その結果、細胞表面タンパク質「CD36」が細胞外ミトコンドリアを分離する指標(マーカー)として有効であることが見出されたとする。次に、CD36に対する抗体を用いて、宇宙で血漿中に放出されるミトコンドリアを含む細胞外小胞が単離され、解析が行われた。すると、その由来組織として、脳、眼、心臓、血管系、肺や皮膚などを同定することに成功したという。さらに、宇宙で血漿中に放出されるミトコンドリアには、地上とは遺伝子の制御が異なる特徴があることも突き止められたとした。
また、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2016年に実施した宇宙におけるマウス飼育研究の際の血液検体を用いて、同様の解析が実施された。すると、マウスでもヒトと同様に、ミトコンドリアの変化が起こっていることが明らかにされた。宇宙環境には、無重力、宇宙放射線、その他の船内環境など、さまざまな要因が含まれるが、マウスの研究結果との比較から、ヒトで見られるミトコンドリアの変化には、とりわけ重力変化の要因が関係していることが示唆されたとした。
細胞外へのミトコンドリアの放出は、神経組織の炎症や代謝関連疾患などに関わることが報告されているという。宇宙で起こる変化と地上での疾患の関連を調べることで、地上と宇宙の医学研究の相互の進展が期待されるとした。また、表面タンパク質を指標とした血漿中の細胞外小胞を分離する技術は、リキッドバイオプシー解析の高精度化につながりうるものとする。さらに、機械学習や人工知能を応用したデータ解析技術と組み合わせることで、全身のさまざまな細胞の遺伝子変化を血液検体から予測することが可能になると考えられるとしている。