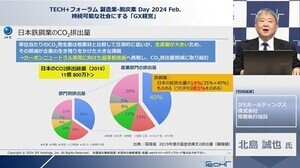企業の長期的な成長のためにも、経営におけるESGへの重要度が高まっている。中でも、日本では2050年のカーボンニュートラル化に向けて、政府がさまざまな支援を行い、企業のグリーントランスフォーメーション(GX)を後押ししている。
2月15日に開催された「TECH+フォーラム 製造業-脱炭素 Day 2024 Feb. 持続可能な社会にする『GX経営』」に、三菱UFJリサーチ&コンサルティング フェロー(サステナビリティ)で、東京大学 教養学部 客員教授の吉高まり氏が登壇。「カーボンニュートラル時代の企業経営とサステナブルファイナンス」と題し、ESGが企業経営にとって当たり前になった今、世界におけるESGはどのように進んでいるのか、日本ではどのような点に注目すべきかを語った。
注視しておきたい海外のESG投資事情
同氏はまず、「国家のESG投資の動きを注視する必要がある」と話した。ESG投資は、欧米を中心に規模が大きくなっているが、その国ごとの政策によってESGマネーの動きが変わっているという。
米国ではインフレ抑制法によって新たな雇用がグリーンエネルギーで生まれ、産業の一部になり始めている。そのため連邦政府も公共調達において、企業に気候変動リスクとレジリエンスの開示を求めることや、証券取引委員会(SEC)が気候変動に関する情報の開示を求める規則をつくり始めているそうだ。
また、今年は米国で大統領選挙があり、「大統領が交代すれば、政策が変更されるのではないかと懸念している企業も多い」と吉高氏は言う。
「現在すでに雇用が生まれている気候変動に関して、国の政策は一部変更があると思いますが、それに伴い、州によって対応が変わるのは間違いないと言われています。したがって、各州がどういう政策を採っていくかを見ていく必要があるでしょう」(吉高氏)
一方、欧州については、2014年の非財務情報開示指令(NFRD)により対象企業は非財務情報を開示することが義務付けられたが、2022年にはNFRDの改定版であるコーポレート・サステナビリティ報告指令(CSRD)が成立し、非財務情報開示の対象企業や開示内容が強化された。後者は2024年から随時適用されるそうだ。これはEU域外の企業にも適用されてくるため、欧州でビジネスする企業は、押さえておくべき動きだと同氏はアドバイスした。
EUでは企業だけではなく、金融機関に対しても「サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)」という、金融商品のグリーンウォッシング(環境に配慮したと見せかける、欺瞞的な環境活動)を規制する動きがあり、日本の金融機関もこういった経営をしていかなければならなくなっているのが今の状況だという。
吉高氏は、国際会計基準の中でもサステナビリティがスタンダード化され始め、気候関連の開示が要求されるようになると見込んでいる。気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)に移管され、日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)も開示基準案を出すことになる。そのため同氏は、「今後、日本の企業はこちらの開示基準をベースに開示を強化していってほしい」と語った。
サステナブルファイナンスとは
サステナブルファイナンスとは、企業が金融機関や投資家から融資・投資を受けるにあたり、企業の利益だけに注目するのではなく、ESGの視点において融資・投資を進めていく考え方を指す。ESG経営を進めている企業にとっては、サステナブルファイナンスを受けられる点で、脱炭素経営などに取り組むメリットがあるといっても良いだろう。
吉高氏はサステナブルファイナンスを、新たな産業・社会構造への転換を促し、持続可能な社会を実現するための金融手法だとした上で、その背景を次のように語った。
「金融の領域では、リーマンショック以降、投資家、銀行、保険に対して、ソフトロー(法的な強制力がないにもかかわらず、現実の経済社会において国や企業が何らかの拘束感をもって従っている規範)ができています。金融機関全体のサステナビリティを考えていくことが進んでいるのです。金融機関はリスクを見るだけではなく、企業の成長性を見なくてはいけないので、CSRというリスクの観点の情報開示のみならず、将来に対する長期的な企業価値の向上が図れる情報開示をしてほしいということもあります。そのため、SDGsのような共通言語によって、金融機関が企業を評価し始めているのです」(吉高氏)
企業に対して融資を行う金融機関は、自分たちの財務の情報の中で、気候変動のリスクとビジネスチャンスがどれくらいあるのか、顧客を含めて評価していかなくてはならない。そこで設立されたのが「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」だ。
こうした動きに対しては、金融機関はまず、投資先のGHG排出量を把握する必要がある。その手法を開発していくための組織として「Partnership for Carbon Accounting Financials(PCAF)」があり、2024年1月現在、日本の金融機関も26社が加盟している。
吉高氏は「実際に企業が脱炭素経営を取り組む際にどんなメリットがあるのかということを金融機関も知っていないと、企業にGHG排出量の削減を促し、また、GHG排出量データを取ることができない」と指摘した。
メリットという観点で同氏はさらに、大企業と取引のある企業は、サプライチェーンの中から外されない、新たな大企業との取引につながるチャンスがあるといった点を挙げた。また、エネルギーコストを抑えていくことにもつながるという。
加えて、人材採用でのメリットもある。
「サステナビリティやSDGsは、今や義務教育のカリキュラムに入っていて、(企業は)これらに向き合っていることが当たり前という認識が強まっています。この年代の学生が今後就職する際には、サステナビリティやSDGsへの取り組みも企業選びの指標にすることでしょう」(吉高氏)
気候変動に関わる国内政策
最後に吉高氏は、気候変動に関わる国内政策について「一番の注目点はGXリーグ」だとした。
経済産業省が2022年に発表した構想を経てスタートしたGXリーグは、自主的な排出量取引(GX-ETS)、市場創造のためのルール形成、ビジネス機会の創発、GXスタジオを通じた企業間交流の促進を主軸に取り組みを進めている。
GXを実現するためには、今後10年間官民で150兆円の投資が必要だといわれており、そのために政府は、GX移行債を発行する。今後、20兆円を発行していくが、2月にはまず1.6兆円が発行された。
金融機関にとっては、こういうものにまずお金が付いていくということを知ることで、自分たちがどこにサステナブルファイナンスとして融資・投資をしていけば良いのかの指針になるという。
もう一つ大事なのが、GX推進機構設立の動きだ。これは、GXのエネルギー分野やプロセス分野、プロダクト分野にリスクマネーを投じていこうというものである。
スタートアップでは、コマーシャルベースに乗るまでの資金がなかなか調達できないが、銀行がリスクを適切に評価することができれば、新しいイノベーションにも積極的に投資がなされる。そのため、GX推進機構が安定操業リスク、需要リスクなどを評価し、金融支援を行っていくのだ。
そのほか、企業は自身が販売するGX製品の市場創出における検討もしていく必要がある。これは、消費者がGXに向けた技術や製品に対して、少し高いお金を払うことに関して、市場のコンセンサスをつくっていくための施策を指す。そして、製品評価の在り方を整え、消費者にインセンティブを付けていく道筋を整備するためのものだ 。
その1つの指標がカーボンフットプリント(CFP) から得られるという。CFPにより自社の製品がどれくらいのCO2を排出しているのかを認識することで、それに対してどれくらいの投資が妥当なのかの判断が可能になる。
「新たなグリーン市場をつくっていく上では非常に重要な仕組みです」(吉高氏)
また、「削減貢献量」という指標もあるという。
削減貢献量は、従来使用されていた製品、サービスにおいて、顧客やサプライチェーン側で削減した分を定量化し、自分たちの企業価値を測る指標として使うというものだ。
「自分たちの製品やサービスによって顧客のCO2排出量を削減できた場合、それが企業価値の評価になっていきます。日本のような省エネ機器が優れている産業界にとっては、重要な指標になるでしょう」(吉高氏)
最後に吉高氏は、今年は第7次エネルギー基本計画策定、ISSBのIFRSサステナビリティ開示基準の適用開始、米国の大統領選挙、G7、G20、生物多様性の条約会議など、いろいろな国際的なイベントがあることに触れ、「こういったものを押さえながら、企業経営に活かしてほしい」と語って、講演を終えた。