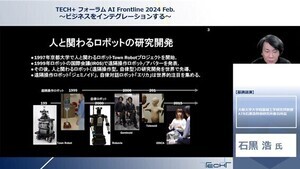日本デジタル空間経済連盟は2月22日、年次カンファレンス「Digital Space Conference 2024」を開催した。昨年に続き2回目の開催となる今回は、「リアルとバーチャルが融合した新たな世界へ」をコンセプトに掲げ、Web3や生成AI、メタバースをテーマとしたセッションを多数実施。併せて、デジタル空間を体験できる展示ブースも設置された。
4枠設けられた連盟セッションのうち1枠では、日本デジタル空間経済連盟 事務局次長 加藤諒氏の進行の下、NVIDIA エンタープライズマーケティング シニアマネージャ 田中秀明氏、日立製作所 研究開発Gr. 先端AIイノベーションセンタ 主管研究長 影広達彦氏が登壇。「インダストリアルメタバースの現在と未来」と題したトークセッションが行われた。
インダストリアルメタバースとは、産業分野において、シミュレーションやオペレーション管理などにメタバースを活用することだ。これにより、省人化や省力化などの実現が期待されている。
本稿では、セッションで語られたNVIDIA、日立製作所のインダストリアルメタバースへの取り組みを紹介するとともに、産業界におけるメタバース実装の課題や今後の展望についてレポートする。
NVIDIAはGPUを生かしてメタバース開発を支援
NVIDIAでは、メタバース環境の開発プラットフォーム「NVIDIA Omniverse」を提供している。セッションではまず、田中氏がこのOmniverseの活用事例を示しながら、産業におけるメタバース活用シーンについて説明した。
例えば自動車業界では、車体の解析や保守、メンテナンスだけではなく、工場の製造ラインにおいてもメタバースがすでに実装されているという。自動運転の領域においても、実道を走るのではなくメタバース上での走行シミュレーションが可能だ。他にも、持ち主が車体をカスタマイズする際、車体のデザインを3Dデータで生成することで、事前に完成形をイメージできる。
田中氏は「自動車業界のメタバース活用はかなり進んでいて、デザインからメンテナンスまで幅広く対応ができる」と手応えを語った。
また、NVIDIAでは、インダストリアルメタバースの実現に向けて、3つのキーワードを据えている。データに相互運用性があり、接続される「オープンスタンダード」、合成されたデータをメタバース環境で具現化する「生成AI」、そして、それを容易に導入できるような「アクセラレーテッドコンピューティング」の3つだ。
オープンスタンダードの領域においては、NVIDIAがピクサーやAdobe、オートデスクなどと連携した共通規格「Universal Scene Description (USD)」の活用により、データの標準化を目指しているという。もちろん、OmniverseもUSDに準拠したデータの生成が可能だ。
他方、生成AIの活用状況については、田中氏はラーメン店を模したメタバース環境を例示して説明した。同環境では、店員のキャラクター(アバター)が店内を動き回っており、ユーザーは実際にアバターと会話ができるようになっている。ユーザーがアバターに話しかけると、その音声データがテキストに変換され、プロンプトとしてLLMへ伝達。そこから生成された返答が今度はテキストから音声に変換され、キャラクターのフェイシャルアニメーションと連携して発音される仕組みだ。
今後は、「メタバース環境で指示をすると、ほかの場所にある物を持ってくる」といった動きもビジュアライズ可能になるという。
こうした高性能なメタバース環境を、NVIDIAが提供しているハード、ソフト群で実現していけることが同社の強みだと田中氏は言う。
「アクセラレーテッドコンピューティングを叶えるために、NVIDIAではGPUを中心としたソリューションを展開しています。AIのビジュアライズを叶えるのがOmniverseで、AI自体の開発や推論を行える『NVIDIA AI』なども提供が可能です」(田中氏)
日立製作所は運用保守におけるメタバース活用に期待
日立製作所はプロトタイプながらも、電車の車両内やプラント向けのメタバース環境の実装が進んでいるとのこと。
影広氏が「車両メタバース」と呼ぶのは、電車車両のCADデータからモデリングするメタバース環境だ。車両の運用保守に役立てることを狙い、運用情報や車両の組み立てなどを支援する。
また、プラント向けには発電所のモックアップ環境を生成し、発電所の移設工事における活用の実証実験中だ。工事において撮影された写真などのデータをアップロードすると、そこに位置情報を紐付けて管理に役立てられたり、作業員の制服に取り付けられたセンサーから作業員の位置などをモニタリングできたりするという。
同氏は今後、オペレーターが声で情報の照会をすると、その情報に位置情報などさまざまなデータを紐付けて返すような環境を作っていきたいと意気込みを語る。
「メタバース空間に運用保守の現場を構築して、新たな働き方を提供していきたいと考えています。我々はこうした環境を『5D現場拡張メタバース』と呼んでおり、空間の3Dと時間に加えて『Semantic(意味)』を付与する環境を作って、皆さまに価値ある情報提供を行っていきます」(影広氏)
産業界におけるメタバース実装のポイントは
影広氏曰く、インダストリアルメタバースの普及における壁は「リアルの世界で何かをすること」にあるという。仮にメタバース上で精細に環境を作っていても、そこでは起こり得ない事象には実際の世界での確認が必要だということだ。
「リアルの世界をバーチャル上に再現して、何らかの合意形成をしたいと思った時に、お客さまには『現場に誰かが行かなきゃいけないよね』と言われてしまいます。これが最大の課題でしょう。事故などのイレギュラーな事象への対策をより深く考える必要がありますね」(影広氏)
田中氏は、日本が他の国に比べてインダストリアルメタバースの普及が遅れている点にも言及。「アメリカやヨーロッパ、中国では活用、推進のスピードが速まっている。日本もスピード感が必要」と語った。一方、日本での実現場における信頼性や持続性は世界的に見ても評価が高い部分であり、こうした技術やノウハウをメタバース上に集積していくことが大事だとの議論も交わされた。
終盤、登壇者3人からインダストリアルメタバース普及に向けた提言として今後の展望が語られた。
影弘氏は「5Dメタバースを実装して、その次に行きたい」と語る。インダストリアルメタバースの普及に必要な膨大なデータ量と知識を蓄積し、人間とシステムが対等な信頼関係を作れる世界観を目指すという。
続いて、田中氏は「国内事例を多く作りたい」と話す。今回紹介されたインダストリアエウメタバースのデモや事例はいずれも海外発であり、今後日本で普及していくには国内先進事例の登場が求められることは自明だろう。これを実現するためにも、パートナーとの協業を強化し、現在70社以上が参画するパートナーカウンシルの拡大を狙っていくとのことだ。
最後に加藤氏は「BtoBとBtoCの垣根を超えられるようにしたい」と語り、セッションを総括した。
「もちろん産業界での定着が先になると思いますが、それを将来的にtoC向けに転用してもいいかもしれません。車両メタバースを鉄道ファンに公開することや、熟練工の技術を新人や若手に継承していくためにゲーミングやコーチングの発想を取り入れても良いでしょう。連携の垣根を低くしていい未来を作りたいですね」(加藤氏)