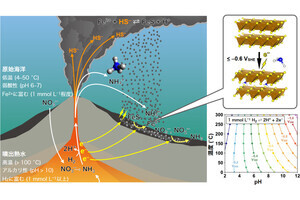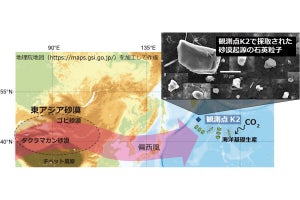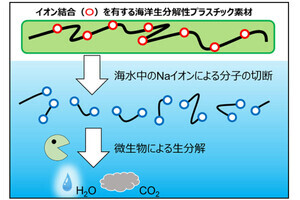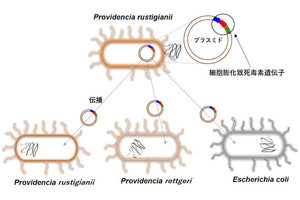琉球大学は12月25日、これまで不明瞭だった食用牡蠣(カキ)に蓄積するノロウイルスの由来について、環境DNA解析による網羅的な動物相の分析により、カキからノロウイルスが検出された時期と、動物種の出現パターンの相互相関を解析した結果、カモ類、ハクチョウ類の飛来と同調して起きていることを発見し、鳥類がノロウイルスの運び屋(ベクター)である可能性があることを発表した。
同成果は、琉球大 医学部附属実験実習機器センターの佐藤行人准教授、宮城県立がんセンター がん制御研究部の安田純研究部長、仙台大学 体育学部の櫻井雅浩教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、淡水系の水生生態学に関する全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Journal of Freshwater Ecology」に掲載された。
カキの生食による食中毒の多くは、その原因となったカキ個体の体内に蓄積していたノロウイルスに起因する。カキは、生態学的には海水中の懸濁物を濾し取って摂食する「ろ過食者」であり、その体内に蓄積されるノロウイルスは、海水から取り込まれていることが明らかにされている。
しかし、ノロウイルスがどのように海水に含まれるのかについては、明確にはわかっていない。これまでは、食中毒患者から排出されたウイルス粒子が、トイレと下水を通じて沿岸海域に流れ込み、カキに蓄積するとする「下水由来モデル」が唱えられてきた。しかし日本を含む先進国では、2000年代前後から下水汚泥の焼却処理が広く普及するようになり、少なくとも先進国の多くの地域では、通常は起こりにくいことが想定されているという。そこで研究チームは今回、カキに蓄積するノロウイルスが、沿岸海域を生活の場とする動物によってもたらされるという「動物由来モデル」を提案したという。
-

ヒトノロウイルスの由来に関する2つのモデル。(A)下水由来モデル。カキに蓄積するノロウイルスの由来を説明する従来説。食中毒患者から排出されたノロウイルスが、下水を通じて海水に還流し、再びカキに蓄積・濃縮されるというモデル。(B)ノロウイルスの動物由来モデル。カキが蓄積するノロウイルスは、沿岸海域を生活の場とする動物によって排出されて海水中にもたらされ、カキに蓄積・濃縮されるというのが、今回提起されたモデルの内容だ(出所:琉球大プレスリリースPDF)
今回の解析では、カキからのノロウイルスの検出日・場所として、カキの代表的産地の1つである宮城県・松島湾沿岸の漁協が行うRT-PCRに基づく自主検査の結果を使用。そして動物由来モデルを検討するため、カキの出荷シーズンに松島湾の海水を採取し、環境DNA分析が行われた。この分析は、海水に含まれる動物由来DNAを網羅的に調べ、ノロウイルスの検出と同調して出現する動物種を統計的に分析することが目的だとする。
-

シーズンにおけるカキからのノロウイルスの検出パターンと、同日に海水からDNA検出された動物相(鳥類および哺乳類)。図の縦軸は、カキのノロウイルス自主検査が実施された日付に対応しており、横軸はノロウイルス検査の陽性数(緑)、および検出された動物種(赤)が示されている。最上列は県全体でのノロウイルス陽性の検査数であり、上部の地図に陽性が検出された場所がプロットされている。上から2番目の列は松島湾内におけるノロウイルス陽性の検査数。各動物種の行に示されている数値は、環境DNA解析で検出された各動物種に由来するDNA配列数が示されている(出所:琉球大プレスリリースPDF)
その結果、ノロウイルスの検出タイミングとの間に有意な相互相関を示す動物として、6種の鳥類(オナガガモ・ヨシガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・ハシボソガラス・ハクチョウ)と、1種の哺乳類(イエネコ)が同定された。そして、カモ類やハクチョウ類の飛来からおよそ4~5週間後、およびカラスとイエネコの出現からおよそ1週間後に、カキからノロウイルスが検出される傾向があることが示唆された。
さらにこの7種間の相互相関関係について、複数の異なる視点を導入してさらなる検討が行われたが、結果には変化はなかったとのこと。加えて、得られる結果を別の統計的尺度でも確認するため、各動物の環境DNA解析の結果である配列数を、絶対数(半定量的指標)ではなく比率(100万分率による相対的指標)に変換した上で、相互相関が調べられた。すると、動物種が5種(ヨシガモ・ホシハジロ・ハシボソガラス・ハクチョウ・イエネコ)に減少したものの、結論としてはほぼ同じ見解が得られたとしている。
以上から研究チームは、季節性の渡り鳥がノロウイルスの自然宿主であり、それらが排出した糞尿を介してノロウイルスが沿岸海水に混入し、カキの一部に蓄積されるという動物由来モデルが支持されるとする。なおカラスとイエネコについては、その生態疫学的な解釈は現時点では不明だというものの、フィンランドの研究ではハシボソガラスの糞便にノロウイルスが含まれていたと報告されていることから、カラスとイエネコもノロウイルスの自然宿主の候補として、今後の重要な調査対象になり得ることが示唆されているとした。
また、動物由来モデルは下水由来モデルと相反するものではないといい、動物由来モデルは、下水由来モデルが想定する感染環よりもさらに上流に相当する、ヒトが感染する前のノロウイルスの由来について説明を与え得るものとする。このことから動物由来モデルは、下水由来モデルを補完して、ノロウイルスの感染環についての理解を深める可能性があると考えられるとしている。
なお今後の課題は、今回判明した7種の動物の腸管や糞便から、直接ノロウイルスを検出することだという。そして、ノロウイルスの自然宿主である動物種を特定できれば、その動物の細胞を使用することでノロウイルスの増殖を行えるようになることが期待されるとし、その増殖が可能になれば、ワクチンや小分子薬剤の開発など、治療応用への道を切り拓ける可能性があるとしている。