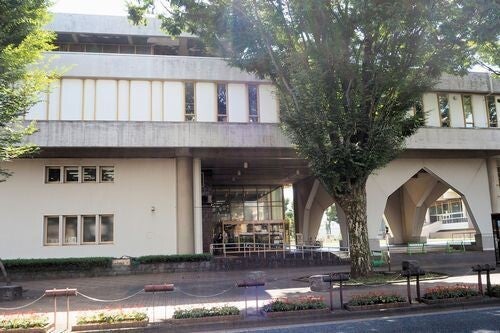東京都三鷹市は、電子マネーやクレジットカード、二次元コード決済によるキャッシュレス決済とセミセルフレジ(現金自動精算機)を令和3年から市役所本庁舎および、三鷹市内全4カ所の市政窓口に順次導入した。
利用できる電子マネーは、SuicaやPASMOなど交通系ICのほか、楽天Edy、WAON、nanacoなどがある。また、二次元コード決済として、PayPay、メルペイ、auPAY、d払いなど、そのほかクレジットカードも利用できる。なお、自治体におけるキャッシュレス決済とセミセルフレジの同時導入は、同市が東京都初の取り組みとなっている。
年間約11万8,000件の証明書発行時の接触を解消
同市はまず令和3年1月に、セミセルフレジを市役所本庁舎に導入。令和4年5月から、三鷹東部市政窓口、三鷹台市政窓口、三鷹駅前市政窓口、三鷹西部市政窓口の4カ所の市政窓口に導入した。
これにより、市民課総合窓口及び市政窓口における年間約118,000件に上る証明書発行の際に生じていた、市民と職員との間の手数料授受の接触を解消し、証明書受渡しまでの時間を短縮した。
キャッシュレス決済とセルフレジを導入した背景には、コロナ禍での接触機会の削減がある。
三鷹市 市民部市民課 年金・番号制度担当課長 佐藤優氏は、キャッシュレス決済とセミセルフレジを導入した理由について、次のように語る。
「コロナ禍で感染拡大の対応策として、全庁で検討する中で、総合窓口として市民課で何ができるのかとなった時に検討したのがセミセルフレジの導入です。それまで、普通の現金だけのレジを使っていたので、対面でお金のやり取りを行う際に接触が発生していました。その接触機会をなくすために、お客様と現金のやり取りを直接行わない方法と、現金によらずに一瞬で支払いが終わらせることができる方法を検討しました。この2点を満たせるものとして、セミセルフレジとキャッシュレスレジを導入しようと思いました」
市民の要望に応えてキャッシュレス決済を導入
キャッシュレス決済は、導入以前から市民からの要望があり、新たなレジ導入の際に同時に実現した。
三鷹市の窓口での証明書の発行枚数は、月に約9,500枚程度。マイナンバーカードの普及により、コンビニエンスストアでの交付も増えているが、令和4年度の実績でいえば、コンビニ交付は全体の2割程度だという。
また同市では、市が発行したカードを使って、市で設置している自動交付機で証明書を発行するサービスも提供しているが、こちらはメーカーが機器を生産しなくなったことから保守ができなくなり年内一杯(12月28日)でサービスが終了する。
同市では、手数料も窓口での交付よりもコンビニエンスストアでの交付の料金を安く設定している。例えば、住民票の写しの場合、窓口だと1枚300円だが、コンビニエンスストアでの交付なら200円、戸籍謄抄本は窓口だと450円だが、コンビニエンスストアなら350円と100円安くなっている。
なお、令和5年6月~令和7年3月までの期間は、さらに100円引き下げを行い、コンビニエンスストアでは住民票の写しは100円、戸籍謄抄本は250円で交付可能となっている。
ただ、マイナンバーカードが徐々に普及してきた現在でも、窓口での交付が圧倒的に多いという。理由としては、コンビエンスストアの交付に対応していない証明書がある点や、本人以外の第三者請求ができない等がある。
課題は「職員の工数削減には結びついていないこと」
キャッシュレス決済とセミセルフレジの導入は市民から好評だという。
もともとキャッシュレスへの要望が市民からあっため、それが実現されたという側面と、コロナ禍での導入だったため、お金のやり取りないのが良いという声が窓口で聞かれているそうだ。
キャッシュレスは、ほとんどのコンビニエンストアやスーパーマーケット等のレジに導入されているなど、利用機会は増えており、高齢者もSuicaやPASMOを公共交通機関で利用しているため、操作に関するトラブルはあまりないとのことだ。
一方で、職員の工数削減には結びついていないという。
「もともと使っていたレジと比べ、目に見えてわれわれの運用が改善されたのかというと、その効果は今のところ出ていません。窓口で、証明書の読み方の説明を行っていると、そこでお客様が滞留してしまいます。今までは次に並んでいる会計のみのお客様からお金を預かって対応することができましたが、セミセルフレジでは、対応中のお客様が済むまで次の方のお会計ができません。3月4月の繁忙期は、どうしてもレジが混雑してしまいます」と、佐藤氏は課題を語った。
また佐藤氏は、キャッシュレスの利用率を上げること自体は目標していていないと述べる。
「あくまでも選択の幅として、いろいろなものが選べることが一番いいことだと思います」(佐藤氏)
三鷹市は、先進的な取り組みに積極的であったが、一方で、全国標準化の動きの中でガラパゴス化するという懸念もある。そのため、佐藤氏は国が進める標準化の動向を注視しつつ今後、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めていきたいと語った。
「住民記録システム標準仕様書への対応がありますし、戸籍のフリガナ表記もあり、このあたりが全国的に標準化されてから、標準化されたものを使ってよりよいDXを考えていきたいと思っています」(佐藤氏)
なお、自治体情報システム標準化は2026年3月末までに完了することになっている。