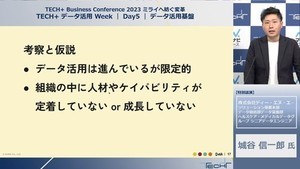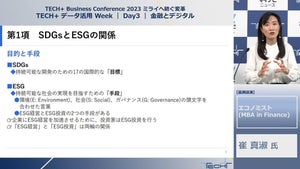“失われた30年”を取り戻すべく、もがき続けている日本経済。データを用いた分析が経営判断の一般的な手段となる中にあって、「分析に偏りすぎている」と警告するのは一橋大学 名誉教授の野中郁次郎氏だ。
5月15日~5月26日に開催された「TECH+ Business Conference 2023 ミライへ紡ぐ変革」の「Day1 ものづくりとサービス」基調講演に同氏が登壇。自身が提唱する競争力向上のヒント「ヒューマナイジング・ストラテジー」について解説した。
「TECH+ Business Conference 2023 ミライへ紡ぐ変革」その他の講演レポートはこちら
過度な分析主義が日本の競争力低下を招く
”失われた30年”という言葉に表されるように、日本の国際競争力低下は長期化している。要因はさまざまだが、野中氏は現在の日本的経営が「あまりにも分析中心で、数値経営が行き過ぎている」ことに要因の1つがあるのではないかと考察する。
この現象をPDCAサイクルに例え、P(Plan)とC(Check)が重視され過ぎている状態だと示したのが、社会学者の佐藤郁哉氏だ。佐藤氏はこれが指示待ち、手続き・手順優先、思考停止の悪循環を招き、D(Do)とA(Action)の2要素に悪影響を与えていると論じている。
「このように分析や計画、規制が行き過ぎると、身体化された生き抜く知恵である“野性”や創造性を劣化させるのです」(野中氏)
続けて野中氏は、第一次世界大戦時に現象学者のエトムント・フッサール氏が「日常の数学化」の危機を警鐘したことに触れ、「科学の基礎は直接体験」だと強調する。
直接経験で感じたお互いの主観をぶつけ合い、「われわれの主観」に到達し、それを客観的に共有できるよう、最終的に数値化・科学化する、この順番が重要だと続けた。だからこそ、「考える」前に「感じる」身体性の復権が求められているのだ。
実際、「身体感覚は意識より0.5秒早い」とも言われており、IQ至上主義を否定する”やり抜く力(GRIT)”など非認知能力こそが、成功の源泉であるという研究結果も出ている。同氏はさらに、身体性は人間ならではの原動力であり、「身体性に基づく共感は、AIやコンピュータには体現できない代物である」とも語った 。
SECIモデルの実践がイノベーションを生む
野中氏は、著書において「知識創造理論」と呼ばれる、世界的に新しい経営理論を提唱したことで知られる。ここでの「知識創造」は「イノベーション」と言い換えることが可能だ。この理論では、知識は「暗黙知」と「形式知」の2つに分けられている。暗黙知は直感や、ひらめきといった言語化の難しい経験知を指し、形式知は言葉や数値などで表現された知識や論理だと言える。
同氏は知識創造理論の基本的な考え方を氷山に例える。水面上に出ている氷の塊を形式知、水面下のそれを暗黙知だとし、「暗黙知と形式知は連続体でつながっている」と説明した。つまり、暗黙知と形式知は別々に存在するわけではなく、表面化していない暗黙知がどれほど豊かであるかによって、形式知の質と量が決まるのだ。
「暗黙知が形式知をつくるのであって、その逆ではありません。端的に言えば、全ての知は基本的には暗黙知に根ざしているのです」(野中氏)
組織的な知識創造プロセス(イノベーションのプロセス)の原理を説明したものが野中氏の提唱する「SECIモデル」である。暗黙知を直接経験や他者との共感によって獲得する「共同化」、暗黙知を概念などの形式知にする「表出化」、他の形式知と結合させ、戦略や理論など集合知を生み出す「連結化」、理論を実践することで組織知を身体化させ、個々の暗黙知を育む「内面化」という4つのステップを循環するモデルだ。
「このプロセスを、共通善に向かって無限にスパイラルアップしていくのが知識創造理論の根本原理であり、重要なのは起点が共感から始まること」だと同氏が語るように、SECIモデルはイノベーションを起こすダイナミックな変換(transformation)モデルなのだ。
ヒューマナイジング・ストラテジーとは
続けて野中氏は「ヒューマナイジング・ストラテジー」に話を移した。著書『野性の経営 極限のリーダーシップが未来を変える』(発行:KADOKAWA)では、創造性の源泉である人間の持つ”野性”を解放、錬磨する必要性を記している。同氏はこれを”人間くさい”戦略を意味するヒューマナイジング・ストラテジーと呼ぶ。人間は人的資本(モノ)ではなく、資本をつくる動的存在なのだ。
「ヒューマナイジング・ストラテジーは、人間の生き方の『物語り(ナラティブ)』であり、文脈に応じてダイナミックに、お互いに対話を重ねながら、共通善の実現に向かって、他者と共創し、無限に新しい価値を生み出し、自己変革していくというのが基本的な考え方になります」(野中氏)
ヒューマナイジング・ストラテジーは、「共通善」「相互主観性」「自律分散系」の3要素を基盤とする。
まず、共通善とは、組織が「なぜ、存在するのか」という存在目的を絶えず問うものである。「世のため人のため」「共通善」で貫かれた存在目的は、ステークホルダーの関係性を広げ、人々の行動を呼び起こす動機付けになる。今、流行のパーパスとも同義である。
次に重要になるのが、相互主観性、すなわち共感だ。主観だけでは独りよがりであり、客観だけでは形式だけとなる。しかし、客観にしなければ組織や社会の知とならない。主観と客観を媒介するのが、哲学者マルティン・ブーバー氏の言う「我―汝関係」、現象学の創始者である哲学者フッサールの言う「相互主観」、つまり、「われわれの主観」である。
母親と乳幼児の関係のように、全身全霊で他者になりきって一心体で共感する必要性を語った野中氏。言語を覚え知性の発達した成人同士がそのような関係になるためには、徹底的な議論や対話が必要となる。互いに「こうとしか言えない」という境地に共に達するために、忖度も妥協も排して、徹底的に互いの主観をぶつけ合う“知的コンバット”のプロセスを採らなければならない。
「重要なのは個人知ではなく集合知。新しい価値を創造し続けている企業は、知的コンバットの場を組織的に内在化し、ブラッシュアップしている。これがイノベーションの本質」だと野中氏は力を込めた。
自律分散型組織はアジャイル・スクラムでつくる
ヒューマナイジング・ストラテジーの3つ目の基盤である自律分散系とは、組織の動態を指す。トップダウンやヒエラルキーなど官僚型の組織ではなく、マトリョーシカのようなフラクタル(いくら分割しても個が全体を体現している)な組織が望ましいと野中氏は説明する。ここでは、理想(トップ)と現実(フロント)をつなげる、プロジェクトリーダーなどのミドルの役割が重要になるそうだ。
-

自律分散系組織のイメージ図
野中氏は、1980年代、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われるほどの勢いがあった日本のハードウエア隆盛期におけるイノベーションプロセスを研究した。そして、その成功の本質を解き明かした「新しい製品開発手法」という論文(共著)を発表した。
ここで唱えられたのは、開発プロジェクトのメンバー全員が組織や工程の壁を越えて一体となって顧客の課題を解決する「スクラム型開発」である。この論文を読んだジェフ・サザーランド氏がSECIモデルをベースとしてソフトウエア開発に展開したのが、アジャイル開発の1つ「スクラム」と呼ばれる手法である。
スクラムでは、プロジェクトメンバー全員が毎日会って、一人一人が、昨日を振り返り、共有する。「15分と短く、立ったままで行う会議だが、全員の共有が一巡すると、過去と未来が現在につながり、何をしたら良いかという先読みが全員でできてしまう。だから、会議終了後、すぐに自分のやるべきことに向かって動ける」と野中氏は語る。そして、開発者と品質管理担当といった異なる性質を持つ人同士がペアを組み、プログラミングを行う。
適時、適宜、全員で情報を共有し、見える化しながら、臨機応変に対応しながら、実践、反省、再実践を繰り返すという流れだ。このような組織は自律分散系組織となり、メンバー一人一人の力を結集する経営が可能になる。サザーランド氏は、スクラムは単なるソフトウエア開発の手法ではなく、「生き方(a way of life)」なのだと述べているそうだ。
“二項動態”でイノベーションを起こせるリーダーであれ
講演の終盤、野中氏は「二項動態(dynamic duality)」に話題を展開した。何事も二項対立(dichotomy)で捉えるのではなく、「共感を起点に、二項を総合する新しい意味や価値を共に創造するのだ」と同氏は語る。
デジタルとの関係で言えば、組織的イノベーションの原理を説明しているSECIモデルにおいて、起点となる共同化のプロセスは、身体性、直接経験、共感が重要であるため、デジタルによる代替が困難な部分である。それ以外の表出化、連結化、内面化は、デジタルによる支援や代替ができる。
「アナログとデジタルを絶えず動的に相互作用していくことで、SECIモデルは効率性と創造性などを同時に追求することが可能になります。デジタルも大いに活用すべきなのです」(野中氏)
二項動態を経営で実践するためにどうしたら良いか。「二項動態経営」では、変化する現実の流れの中で、共通善に向かって、「あれかこれか」ではなく、「あれもこれも」で 一見相反したり矛盾したりする物事を高いレベルで総合し、その都度の最善を判断し、機動的に実行する。試行錯誤を奨励し、失敗したら、反省し、また挑戦するという無限のプロセスを通じて、新しいイノベーションを生み出し、実現する。「論理分析型の静的な戦略論は役に立たない。むしろ、戦略構想を実践するための『物語り(ナラティブ)』が、二項動態経営には有効」だと野中氏は言う。
物語りとは、事実を並べただけのストーリーとは異なり、Whyを説明し、結論ありきではなく、オープンエンドに紡がれる。物語りは、戦略の大まかな筋書きを示す「筋(プロット)」と、いかに実現するかという行動指針を示す「台本(スクリプト)」で構成される。企業や国の「生き方」を知の物語りとして創作することが重要だと野中氏は述べる。
「二項動態経営とは、物語りで描かれる『生き方』としての人間くさい戦略論(ヒューマナイジング・ストラテジー)なのです」(野中氏)
野中氏によると、二項動態経営のリーダーには「フロネティック・リーダーシップ」が求められるという。フロネシスとは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが提唱した賢慮、実践的知恵に由来する中庸の理念であるが、それは単なる中間ではなく、状況に応じて最適な行動を取る「実践知リーダーシップ」なのである。
同氏はフロネシスを「現実に起こっていることに対して、変化し続ける文脈の中で過去と未来の“より善い”を洞察すること」だと解説。思索に基づいた冷静な頭脳と温かい心を備え、絶えず実践につなげられる人物、つまり抽象的な理論と具体的行動を二項動態で総合する「知的体育会」系リーダーが、「イノベーションをつくり出せる人物像になる」と語り、講演を締めくくった。