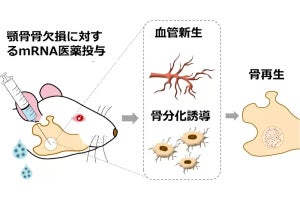岐阜大学は6月26日、イノシシの行動圏や日中と夜間における生息地利用を調査し、イノシシが比較的狭い範囲を利用していて、人間活動に合わせて利用場所を変化させていることを解明したと発表した。
同成果は、岐阜大 応用生物科学部 附属野生動物管理学研究センターの池田敬特任准教授、同・東出大志特任助教(現・石川県立大学 講師)、同・鈴木嵩彬研究員(現・特任助教)、同・大学 応用生物科学部の淺野玄准教授らの研究チームによるもの。詳細は、日本哺乳類学会が刊行する哺乳類の基礎生物学と応用生物学を扱う学術誌「Mammal Study」に掲載された。
イノシシは、農作物被害や人身被害を引き起こすだけでなく、豚熱などの伝染病に感染することから、これらの被害緩和のためにその個体数を管理することが強く求められている。野生動物の個体数管理の計画を立てるためには、正確な行動圏や生息地利用が有益な情報となるが、イノシシにおけるそれらのデータは、日本では限られた事例しか得られていないという。
日本国内では、2018年9月に岐阜県で豚熱が再発生し、イノシシが拡散の一因とされた。そのような状況では、イノシシの行動圏はウイルスの拡散を予測するため、生息地利用は効果的な捕獲や経口ワクチン散布のために重要な情報となる。そこで研究チームは今回、岐阜県美濃加茂市においてGPS機能を持つ首輪をイノシシに装着し、イノシシの行動圏や日中と夜間における生息地利用の解明を目指したとする。
海外の研究では、イノシシが捕獲地点から平均45.8km移動していたことから、研究チームは当初、今回の研究においても長距離移動が行われると考えていたとする。しかしその予想に反し、今回の調査地では、各個体の行動圏の重心と各測位点までの平均距離は0.26km~2.55kmと狭い範囲であることが確認され、行動圏面積は0.32km2~28.51km2だった。
日本国内のこれまでの研究では、兵庫県で0.39km2~9.47km2、島根県で0.81km2~1.32km2と報告されており、調査地域における環境やイノシシの密度、GPS首輪を装着した個体の性別や年齢、GPS首輪を装着している季節や期間に左右されることが明らかにされている。
また、イノシシは人為的撹乱を忌避し、人間活動の少ない夜間に活発に行動するため、ヒトの活動に合わせて利用場所を変化させていることが予想されたとする。今回の研究では、予想通り、日中は人間の生活圏に近い人工構造物や耕作地、水田面積の多い環境や、人間が近付きやすい緩い斜面を避けていることが確認された一方で、人間の活動が少なくなる夜間では、耕作地周辺を選択的に利用していることが突き止められた。
以上のことから、今回研究対象となったイノシシは比較的狭い範囲を利用し、ヒトの活動に合わせて利用場所を変化させていることが明らかにされた。実際に、イノシシ個体群におけるアフリカ豚熱ウイルスの拡散を調査した研究では、1km圏内では群れ内での接触、1km~3km圏内では群れ間での接触が高いことが報告されているという。そのため、ほかの地域へのウイルスの拡散を防ぐためには、感染個体が発見された地域周辺での集中的な対策(経口ワクチン散布や捕獲)が期待されるとする。特に欧州では、休息地点周辺における対策が効果的と考えられているため、日本においても、日中の利用場所付近での捕獲や経口ワクチン散布を実施することが効果的であることが考えられるとしている。
また、イノシシは被害が多発している耕作地周辺の竹林で休息している可能性があり、これらの環境を整備することによって、イノシシによる被害を軽減できる可能性が高いと考えられるともする。
一方で研究チームは今回の研究に関して、追跡期間が短い個体がいる点、性別や年齢を考慮できていない点、集落周辺における調査である点などの課題を挙げる。そのため今後は、イノシシの性別や年齢を考慮するだけでなく、イノシシによる豚熱の拡散予測のための山間部での研究や、養豚場での豚熱の発生防止を考慮した養豚場周辺での研究が実施されることが望ましいとしている。