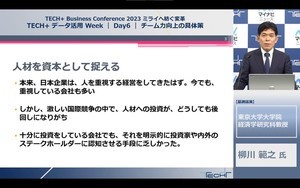日本企業のデータ活用は進みつつあるものの、各部署での個別最適化に終始していて、全社戦略に基づいていないケースも多い。
ゲームやライブストリーミングなどのエンターテインメント領域から、ヘルスケアなどの社会課題領域まで、事業を多岐に展開するディー・エヌ・エー(以下、DeNA)では、エンタープライズ規模でのデータ利活用を積極的に進めている。同社はどのようにして、スモールスタートからエンタープライズ規模のプラットフォームへと進化させてきたのだろうか。
5月15日~26日に開催されたオンラインセミナー「TECH+ Business Conference 2023 ミライへ紡ぐ変革」の「Day5 データ活用基盤」に、ディー・エヌ・エー ソリューション事業本部 データ統括部データ基盤部 ヘルスケア・メディカルデータグループ シニアデータエンジニア 城谷信一郎氏が登壇。同社の取り組みを例に、データ人材や組織、データ利活用プラットフォーム構築に関するポイントを紹介した。
日本企業のデータ活用は全社的な取り組みになっていない
日本企業の課題は、データ利活用のニーズが年々増えているにもかかわらず、取り組みが限定的されてしまっていることだ。そのために、全社的なデータ活用が進んでいない。城谷氏はその原因として、組織の中で人材が定着していない、あるいは成長していない、ケイパビリティが向上していない ことを挙げる。その上で、こうした状態を放置してしまうと、ビジネスや顧客の変化に即応できなくなると指摘した。
「(ニーズを解決できる)専門家がいても、リソース不足で待ち行列が発生してしまいます。また、過度に外部リソースへ依存すると、個別最適なものをつくってしまうリスクもはらんでいるでしょう。結果として、事業間でのデータ利活用プラットフォームを共同利用・相互利用できていない、ユースケースが限定されてしまうといったかたちでデータ活用の深さも幅も広がらず、ビジネスに悪影響を与えてしまいます」(城谷氏)
これらの課題の解決策は、データの専門家および非専門家からなる「データ活用組織の組成」と全社横断的な「データ活用基盤の検討」の2つに分けられるという。
データ人材・組織を育てていくポイントは「言語化」
まずはデータ活用組織の組成について考えていきたい。DeNAでは、2010年頃からデータ分析体制・文化の構築をスタート。2018年頃からは、AIやデータサイエンス人材の採用を強化してきた。しかし2022年頃からは、メンバーの入れ替わりや離脱などで組織の危機が生じたという。この対策として同社は、データ人材の採用戦略の立案と言語化に取り組んだ。
これらの経験から城谷氏は、さまざまな会社がデータ活用を進める上での施策について構造化・プロセス化し提言する。
「まずはAs-Isを整理し、To-Beから逆算した全体の戦略を立てることを推奨します。全社員がリスキリングをした上で簡単なデータを活用できる状態を目指すのか、AI/MLなどを駆使して他社に対して優位性を持ったプロダクトを出すのかで戦略は大きく異なるでしょう。最初にやるべきことは、目指したい姿の“言語化”です」(城谷氏)
このような中長期の目標に対して、人材リソースとケイパビリティをどう確保するかも戦略として重要となる。特に、専門家人材の採用が難しくなっている昨今では、若手の時期から育成したり、外部のビジネスパートナーやベンダーを活用したりしながら共に成長するという戦略も考えていく必要がある。
また、ジョブディスクリプションの定義もポイントだ。採用において「DX人材」という漠然とした募集要項が散見されるが、「DX」と言ってもその対象範囲は広い。
城谷氏は「データアナリスト、データエンジニア、データサイエンティスト、MLエンジニア……と分けて、それぞれが関わる業務や必要なスキルを明確化すべき」だと、職種ごとに業務の詳細を言語化することの重要性を強調する。これにより、ターゲティングが容易になり母集団の形成がしやすくなるだけでなく、求職者側も自身が描くキャリアの理想像との刷り合わせができる。その結果、求職者の応募確度が上がっていくそうだ。
一方で、そのデータ人材が入社した後のキャリアマネジメントについても考えておかなければならない。DeNAではロールごとにジュニア、ミドル、シニアというキャリアラダーを設定した。それぞれのロールにおいて、キャリアアップのために必要なスキルが細かく言語化されている 。また、長期的なキャリアについては、マネージャーの他にプレイングマネージャーやテックリードといった方向性に興味を持つ人材も多いため、本人の意向を確認しておくべきだという。
そして、最後に組織のデザインも定期的に見直す必要がある。組織には賞味期限があり、時間が経つと組織にボトルネックやひずみが生まれるため、定期的なリデザインが必要不可欠だ。
DeNAでは、かつて過去データエンジニア組織として全社横断のデータエンジニアチームが各部署のデータ活用の担当対応をしていた。しかし、事業やプロジェクトが増加するに連れて、1人が複数のプロジェクトに関与せざるを得なくなったという。結果的に、属人化が起き、メンバーのモチベーションが低下、データ活用基盤のクオリティにも影響を与えることになった。
そこで、「チームトポロジー」の組織論を取り入れたデザインにアップデートし、個別事業の対応と横断的な機能の提供に対応できる組織をデザインしたそうだ。
データ利活用プラットフォームの全体アーキテクチャをリデザイン
データ利活用プラットフォームを構築するにあたっては、過度な個別最適化による“車輪の再発明”、または情報の流通・共有の阻害などが課題となる。一方、過度な全体最適化をしてしまうと、ユースケースが固定されてしまうという弊害も生まれてしまう。
DeNAでは、城谷氏が担当するヘルスケア/メディカルの領域でデータ利活用プラットフォームを立ち上げた。データの分析利用、プロダクト開発、AI/MLなどさまざまなユースケースへ対応すること、データシェアリングの仕組みを提供しデータの流通・共有を行うこと、インフラ・クラウドを統一し、アジリティの高いプラットフォームを構築すること、ガバナンスを統一することが目指すべき姿だという。
現在、同事業では、プロセスを3つに分けて、それぞれにガイドラインやベストプラクティス、ツール、SDK(Software Development Kit)を提供している 。また、どの段階でも守るべき共通の指標や最善の方法論も定義されているそうだ。
さらに、ヘルスケア/メディカル領域はセンシティブなデータを扱う領域であるため、パーソナルデータとは何かを改めて定義。要配慮情報からオープンデータまで、データの種別ごとにティアリング(階層化)をしている。
-

ヘルスケア/メディカルにおけるデータ収集・統合から利用までのプロセスと、各段階で提供するもの
従来は、データ収集の環境と利用する環境が同じだったために、データの所有者と利用者が異なる場合は情報のやり取りがしづらいという課題があったと城谷氏は明かす。今回のように段階に分けて全体アーキテクチャをリデザインし、一元的にデータを管理できる流通・共有プラットフォームを構築したことにより、データの所有者が承認したデータのみを利用者に提供できる状態を実現。ガバナンスとセキュリティを両立することに成功した。
「立ち上げ中のため期待値込みではありますが、このような取り組みにより、利用者もどのような情報を取り扱って良いかが明確になります。セキュリティガイドラインをある種の“ガードレール”にして、ベストプラクティス・ツールを提供することで、生産性向上が期待できるようになりました」(城谷氏)
人材・組織とプラットフォームを相互作用させながら育てていく
講演の終盤、城谷氏は「人材・組織、プラットフォームのどちらかだけ整えたとしても、データの利活用はエンタープライズにはなっていかない。2つを循環・相互作用させながら育てていく取り組みが必要」だと強調した。
人材・組織はあるが、プラットフォームが使いにくければ広まっていかない。その逆もまたしかり であり、両輪で取り組んでいくことが重要なのだ。
データ利活用の取り組みは一朝一夕では成功しない。日々の積み上げと改善が必要になる。実際にDeNAでも、長年をかけて整備を進めてきたそうだ。しかし城谷氏が「今回紹介したような先行事例を参考にショートカットが可能」だと言うように、他社の成功事例を参考にしながら自社に適したアプローチを見つけていくことはできる。
城谷氏は最後に、「DeNAでも実はようやくスタートラインに立てた程度。日本全体のデータ活用はこれからもっと盛り上がるでしょう」と今後に期待を込めた。