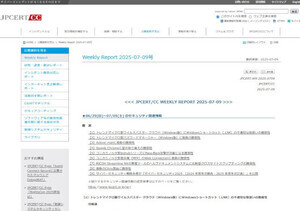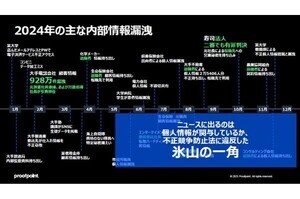新しい出会いの場として一般的となったマッチングアプリ。見知らぬ人々同士で交流できる一方、オンラインだからこそのリスクを危惧する声は少なくない。では、プラットフォーマー側はどのように安全性に向き合っているのだろうか。
世界190カ国、40以上の言語で利用されているというマッチングアプリ「Tinder」を運営するTinder社では安全対策をつかさどる「トラスト&セーフティチーム」を設置し、ユーザーが安全で信頼できる場所の構築を進めている。
5月30日、同チームで総統括責任者を務めるローリー・コゾル氏が来日してメディア向けのラウンドテーブルを開催。同社APACコミュニケーション・ヴァイスプレジデントのパブリ・デヴ氏とともにTinderで推進している安全対策について解説した。
ホストとして、ゲストが安全に楽しめる環境を作る
昨年の同社資料によれば、Tinderのダウンロード数は5.3億に上り、グローバルなプラットフォームとして世界190カ国で利用可能となっている。日本では、特に東京における利用者が多いという。
コゾル氏は「日本はTinder社の創立以来重要なマーケット。ビジネスとして好調なだけではなく、日本の皆さまは安全性やプライバシーへの意識が非常に高い」と述べた。
実際に、日本のユーザーからの声を基に実装した機能もある。日本国内のユーザーの傾向として、Tinderで同僚や同級生など知人と出会ってしまうことに抵抗があることが判明した。そのため、連絡先のブロック機能を実装して「まだ知らない人と新しい出会いができる」環境を作っているという。
こうした機能の追加をはじめ、出会いを求めて集まったユーザーへTinderが安全な場所を提供する自身らをコゾル氏は「パーティーの主催者」に例え、次のように説明した。
「出会いという目的を持って来てくれたゲストに対して、我々がホストとなって迎え入れているんです。そこでゲストにどのように振る舞うべきだ、どうやって話せばよいということは助言しません。ですが、ゲストがパーティーの中で危険を感じたり、不快に思ったりすることは、主催者として排除しています」(コゾル氏)
機械学習を使ったアラート機能で迷惑行為の減少に貢献
Tinderでは、ユーザーが安全にプラットフォームを使用するために、機械学習によるメッセージ分析とレコメンド表示を行っている。
前提として、Tinderではお互いに興味を持った状態でダイレクトメッセージのやりとりがスタートする。他人とのマッチングはお互いに「ライク」というスタンプを押すことで、ダイレクトメッセージが送れるようになる仕組みだ。しかし、ライクにも”重さ”がある。例えば、「少しお話してみたい」と思ってライクをした相手から予想以上に強烈なアプローチが来たら、不快感を抱いてしまうこともあるだろう。
そこで、Tinderでは不適切だと思われる可能性があるメッセージには、送信ユーザーに対して「本当に送信しますか?」というアラートを出している。一方、受信したユーザーにも「不愉快な思いをする内容がありましたか?」と質問が送信される。ここに「はい」と答えれば、相手の不適切な言動を運営側に報告することもできるのだ。
Tinderとしては、こうしたユーザー同士のモチベーションの違いやトーク上での不適切な表現を機械学習で集計してレコメンデーションをしている。このシステムを導入した結果、迷惑メッセージの送信を10%減少させることができたという。SNSでもユーザーから賞賛の声を得られており、「利用者のニーズに応えた機能となっている」とコゾル氏は胸を張る。
こうしたユーザーを危険から守る取り組みとして、同社ではアプリ内で「セーフティーセンター」を設けている。これは、各地域でのセーフティーガイドやTinderの利用にあたって知っておきたい知識を確認できるクイズなど、安全性を担保するための情報が集約されたガイドラインだ。コゾル氏は「行動する前に、相手が不快なことをしないように学んでもらうこと、良い行動をとってもらうために我々から必要な情報を提供するのがセーフティーセンターの役割」と語った。
オンライン詐欺に強い警戒「そこに愛はない」
上述の他にもさまざまな安全対策を行っているものの、全ての脅威が取り払われているわけではない。同社では「Tinderを媒介して発生するオンライン詐欺」を警戒しているという。Tinder上での詐欺行為だけでなく、マッチした相手を他のプラットフォームへ誘い、そこで詐欺行為を働くケースもあるようだ。
ただ、Tinderで詐欺行為を行っているユーザーには特殊な傾向があり、同社では行動パターンから危険なユーザーのピックアップができているという。ライクの頻度やアプリの使用場所など、行動履歴をサーバーで解析して、危険なユーザーの監視を行っている。併せてユーザーへも詐欺被害に遭わないように啓蒙活動を行っており、Tinderの外で会話を試みた場合や、「為替」や「暗号通貨」といったキーワードを受信した際にはアラートを表示している。
「我々が協力している大学の先生が、『お金が欲しい、とか個人情報が欲しい、という会話があれば、そこにはもう恋心なんてない』と仰っていました。つまり、そこに愛はありません」(コゾル氏)
今後はAIやアバターを駆使してさらに安全な環境へ
パンデミックが終わり、出会いの場がオンラインからオフラインへ回帰している。Tinderのユーザーにもその動きはあるようで、同社ではさらなる安全機能のアップデートが求められる。
Tinder社としては、ある一定の距離を保ちながら全体を監視・巡回できる環境を構築して必要な危険は排除する、という姿勢を持っている。「まるでナイトクラブのセキュリティ(警備員)のように、全体を見ながら必要な時にだけ介入する。逆に言えば、いざというときに助けを求められるような環境を作りたい」とコゾル氏は話した。
同社はこの世界観を実現するためにAIの活用も視野に入れており、ユーザーへの危険信号のより高精度な表示や、何か問題が起きた場合のフォローアップに活用していくとのことだ。加えて、すでに各地域へ常駐している“仲裁人”によって、AIから検知された危険な事象に対して一つ一つ対処する体制を整えている。
コゾル氏によれば、日本においては、「自分の顔写真を見せたくない」というインサイトがあるという。Tinderでは、アバターなどの活用で「ある程度のところまでは自分を開示し、プライバシーには配慮する」境界線を引くシステムの開発を検討中とのことだ。
コゾル氏は今後のアップデートについて、「まだ開発中だが、秘密のメカニズムがある。次回来日した際にはお披露目できると思う」と見通しを語った。