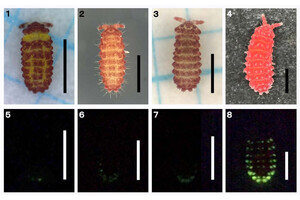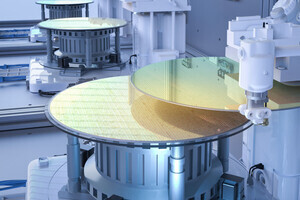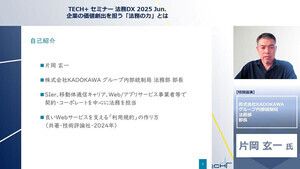SAS Institute Japanは今年5月、代表取締役社長に手島主税氏が就任したことを発表した。同氏は直近で、日本マイクロソフトの執行役員常務として、クラウド事業など主力事業を統括していたことから、この人事は業界では驚きをもって受け止められた。
今回、日本ヒューレット・パッカード、米Hewlett-Packard、セールスフォース・ジャパン、日本マイクロソフトと外資の大手ITベンダーで要職を務めてきた手島氏が、なぜ、SASの代表取締役社長就任を選んだのか。また、SASでどんなことをやり遂げようとしているのか。今回、手島氏に話を聞くことができたのでお伝えしたい。
SASでの新たな挑戦を選択した背景
手島氏は、日本マイクロソフトの事業をけん引するキーパーソンの一人であり、記者会見にもよく登壇していた。そのため、SASの代表取締役社長に就任するというニュースがIT業界に与えたインパクトは大きかった。
手島氏がマイクロソフトの幹部から、SASの代表取締役社長という新たな道を選んだ理由は何か。同氏は、これまでの活動から感じたことを次のように語っていた。
「マイクロソフトでは、ワークスタイルイノベーションを担当したが、そこでコラボレーションやハイブリッドワークについて知見を得て、新しい世代の人をどう導くかという課題を見つけた。また、企業は多様化が進む企業にどうシフトするかを悩んでいる。こうした中、リーダーの立場で、グローバル化に踏み込む必要があると感じた」
SASを選んだ3つの理由
そして、手島氏は次の活動の場として、SASを選んだ理由は3つあると述べた。
1つ目の理由は、これから上場を控えているSASの可能性だ。SASは2021年に米国でのIPOに向けた準備を開始したことを発表している。「46年という歴史あるSASがパブリックカンパニーとして、どう成長するのか。その中で、リーダーとしてチャレンジしたいと考えた」と、手島氏は語る。
2つ目の理由はカルチャーだ。ご存じの方も多いと思うが、SASはFortuneによる米国企業を対象にしたランキング「最も働きがいのある企業100社」の常連であり、古くから働きやすさに定評がある。手島氏は、「多様な文化の中で成長するとともに、日本でもダイバーシティ&インクルージョンを進めていきたい」と話していた。
3つ目の理由は「テクノロジー」だ。「SASでは、クラウドを力にしながら新しいことを実践できる。インフラは成長を遂げているが、データやアプリケーションのブレイクスルーはこれからであり、正解がないVUCAとも言われる、変化が著しい今、グローバルレベルでリスクが起きている。また、多様化が生活の中で起きているが、その中心にテクノロジーがあり、バイアスと戦っていかなくてはいけない」と手島氏。
昨今、AIの利用において、倫理面における問題が取りざたされている。手島氏は、「倫理との戦いにおいて、最後に決めるのは人。確実性をどう担保するか。技術の収斂がないと難しい。SASは統計学に基づく確固たる技術力を持っている」と、手島氏は話す。
アナリティクスでブレイクスルーを起こしたい
そして、手島氏に、SASのリーダーとして、どんなことにチャレンジしてみたいかについて聞いてみた。
手島氏からは、「アナリティクスでブレイクスルーを起こしたい。人中心のイノベーションを実現したい」という答えが返ってきた。さらに、「技術の使い方次第で、企業は継続的に成長できるかどうかが決まる。技術的に成長するには、企業はそのための仕組みを内部で作り出す必要がある」と同氏は続けた。
SASは昨年、意思決定を支援するソリューションを発表したが、このソリューションを活用して、人のトランスフォーメーションも目指したいという。
さらに、手島氏は次世代の人材育成にも力を注ぎたいと繰り返し述べていた。企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に不可欠なアナリティクスとAIに関するテクノロジーを強みとするSASが、手島氏のパワーによって、どう飛躍を遂げるのか、楽しみにしたい。