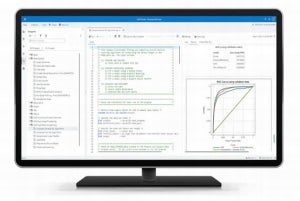コロナ禍は収束しつつあるが、物価高騰に国際紛争と、まだまだ予測困難な事態は続いている。そうした中、企業が変化を乗り越えて生き残るためにレジリエンシー(回復力)が必要とされるが、レジリエンシーを備えている日本の企業は少ないようだ。
米国SAS Instituteが今年4月、企業のレジリエンシーに関するグローバル調査の結果を発表した。これによると、日本の経営層の87%は、レジリエンシーを「非常に重要」または「少なからず重要」と考えているが、自社がレジリエンシーを備えていると考えるエグゼクティブは全体の約4分の1(27%)にとどまっているという。
同社はこの調査から、ビジネス・レジリエンシーを維持・強化するために必要なルールとして、5つを明らかにしている。
- スピードと機動力:市場の状況の変化に迅速に適応する
- イノベーション:データ主導のインサイトを通じて、進歩を加速させる
- 公平性と責任:革新と並行して、転換的テクノロジーの設計、開発、利用において倫理的基準を確実に適用する
- データカルチャーおよびリテラシー:組織全体にデータリテラシーを浸透させるデータドリブンのフォーカスを構築する
- 好奇心:調査の力を活用し、イノベーションと影響力を促進するインサイトを導く
そして、同社は5つのルールを実装する上で、データとアナリティクスが重要な役割を果たすとの見解を示している。さらに、SAS Institute Japan 常務執行役員 営業統括本部 本部長 宇野林之氏は、日本企業がレジリエンシーを獲得できない一因に、デジタル人材の不足があると指摘する。
そこで、企業がデジタル人材を育成して、レジリエンシーを手に入れて大きな成長を遂げるためにはどうすべきか、宇野氏に聞いた。
レジリエンシーがないと、何が起きる?
レジリエンシーという言葉はまだなじみが薄く、その重要性が今一つ理解できない人もいるだろう。宇野氏は、レジリエンシーについて「経済状況の変化に対応するため、変化によって受けたインパクトから回復するために必要な力」と説明した。
上述した5つのルールに基づき、速いタイミングで変化から気づきを得て、気づきを得た段階でどう行動するかを決めることが大事だという。
では、企業がレジリエンシーを備えていないと、どのような事態が起こるのか。例えば、バリューチェーンを迅速かつ正確に分析できず、製造業なら工場の稼働が制限され、タイムリーに製品を作ってマーケットに出すことができなくなる。これでは、新規ビジネスを創出するどころか、既存のビジネスの維持まで危うくなってくる。
宇野氏は、「意思決定の判断材料になるデ―タやシステムがサイロ化されている点も問題です。複雑に絡み合っているシステムからデータを抽出して、単一のビューで必要なデータを見られるようにする必要があります。また、リスクが発見されたら、早期にアラートを上げる仕組みも必要です」と話す。
こうした意思決定に必要なデータを扱える人材が増えれば、企業はレジリエンシーを高めることができるというわけだ。
会社全体で、仮説を立てそれを証明するプロセスを楽しもう
では、どうしたらデジタル人材を育てることができるのか。宇野氏は、「経営層をはじめ、従業員一人一人がデータに興味を持つことが大切です。仮説を立て、それを証明するプロセスを楽しんでもらう。その結果、データドリブンのマインドが生まれ、データドリブン経営につながってきます」と話す。
加えて、企業でデータを活用するには「データ分析基盤」「アナリティクスプラットフォーム」が必要となるという。これらを整備できたら、いかにして分析するためのデータを迅速に作るかが重要になる。宇野氏は、その理由を次のように話す。
「アナリティクスは繰り返しの作業であり、データ分析のプロセスにおいてデータ加工が8割を占めています。よって、分析データを作るデータクレンジングをスピーディーに回すことが求められています」
しかし、企業はデータ作りに時間も労力も要することから、悩んでいるそうだ。この課題の解決策について、宇野氏は次のように説明する。
「分析のPDCAサイクルを効率よく回せるツールを選ぶことが重要です。データは1回作って終わりではありません。そのため、データを収集するためのロード時間 集計するためのロード時間などを高速化することも必要です」