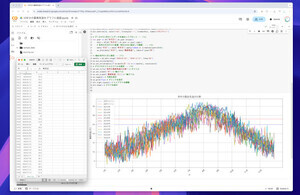「DX」という言葉を聞いてどんなことを想像するだろうか。
反射的に「デラックス」と読んでしまう人もいそうではあるが、ニュースやビジネスの現場でこの2文字を見掛けた時には、ぜひ「デジタルトランスフォーメーション」と読んでほしい。
インターネットで「DX」という単語を検索してみると、上位にヒットするのは「デジタルトランスフォーメーション」ばかりということからも、DXに対する注目の高まりを感じることができるだろう。実際、最初に「デラックス」と書いてみたが、素直に正しい読み方をしてくれた読者がほとんどだと思う。
しかし、「DX」が具体的にどんなことを指しているのかを説明できるかと言われると、難しいかもしれない。
経済産業省が、DXについて「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」 と定義しているように、具体的な施策は企業によって異なるのが現状だ。
そんなさまざまな意味合いを持つDXだが、その成功の鍵は「内製化」が握っていると言われている。
「なぜDX推進を社内が主体となって行うべきなのか」、「今後のDXの取り組みはどのような未来を迎えるのか」、そんな疑問を解決するために、先端のソフトウェアやアルゴリズム、テクノロジーを活用して成長する企業の支援を行うファインディの代表取締役である山田裕一朗氏に話を聞いた。
日本のDXを進めた「3つの時代」を振り返る
「DX」の未来を考えるために、まずは歴史から振り返ってみよう。
山田氏曰く、日本のDXの変遷は3つの時代に分けられるのだという。
1つ目の時代は「外注時代」だ。
「この時代は、デジタルが競争優位の要素ではないので基本的に外注に頼っていました。あくまで自動車会社なら『自動車』、スーパーマーケットなら『スーパーの売り場』が一番大切で、WEBアプリケーションによる集客にそこまで重きを置いていなかった時代です」(山田氏)
そんな2010年頃まで続いた外注時代の次にやって来たのは、企業が「デジタルが競争優位である」と認識し始めた「DX号令の時代」だ。
「どうやら外注をしているだけでは、デジタルが自分たちの競争力にならないと気が付き出したのがこの時代です。スーパーマーケットなら、アプリケーションで通知を出すとそれを見た顧客が来てくれる人が増えた一方で、新聞の広告を見て来てくださる人は減った。また、そのアプリはECと勝負をする時代になってきた。そんな気付きから『発注先』を変える企業が増えたのがこの時期です」(山田氏)
この「発注先を変える」とは、従来のSlerに依頼していたものを外資系やスタートアップに依頼するという潮流を指すという。外注時代に比べてDXに対する意識が高まり、デジタル化を競争力としてカウントし始めたこの時代だが、デジタル組織の優位性を認識していなかったのが今とは異なる点だという。
「2020年代に入ってからの3つ目の時代、つまり現代は、『役員本気DX時代』です。企業の競争優位性がデジタルではなく、デジタル組織にあるということに気付き、CTO(Chief Technical Officer:最高技術責任者)やCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)が組織を作りこむことに本気で取り組み始めたのがこの時代です」(山田氏)
DX推進を社内で行うべき企業の3つの特徴
DXの歴史が分かったところで本題に入ろう。まずは、今回の大きなテーマの一つである「なぜDX推進を社内が主体となって行うべきなのか」について掘り下げていく。
「DX推進を社内で行うべきメリット」や「DXの内製が注目される理由」といったように、「社内が主体となってDXを推進するべき」と報じるメディアは多いが、本当に企業はDXを社内主体で進めるべきなのだろうか?
「すべての企業に対して『するべきだ』とは言えません。企業として一定の規模がないと、資金面でも人材面でも大変苦労することが目に見えているからです。その一方で、規模があまり大きくない企業であっても、ある条件に当てはまる場合は『やらなくてはいけない』と言えます」(山田氏)
山田氏が、社内主体でDXを進めなくてはいけない企業の特徴として1つ目に挙げたのは「外資やネット大手の企業と競合している企業」だ。特にメディア業界や小売業界などは、少しでも顧客を得るためにインタフェースを大切にする必要があり、いわば「するか負けるか」の2択を迫られるほどの状況になってきているという。
2つ目の特徴は「スタートアップが資金の大規模調達を始めた業界」だ。以前は、スタートアップがマーケティング資金を調達してから動き出しても追いつくことができたそうだが、現代においてそれはかなり至難の業だという。なぜなら数年前までは、スタートアップの資金調達が数億規模だったところ、今では数十億単位での調達を行える企業も少なくなく、資金力で大手企業がなかなか勝てない場合が増えているというのだ。その場合は、スタートアップの動向を先読みしてすぐに動き出す必要性があるという。
そして3つ目は「グローバルを見据えた企業」だ。特に業界のトップなどは、グローバルを見据えて内製化に向けて動き出し、実際にやり切る企業も増えてきているという。やはりグローバルで戦っていくためには、デジタル組織としての競争力を身につけていく必要がありそうだ。
10年後までにDXの波に乗れていなければ「大手企業でも衰退」する?
ここまでDX推進をあおるようなことを書いてきたが、これまでの話を踏まえて、企業が「では我が社もDX推進に注力しよう!」とやる気を出したとしても、すぐにうまくいくとは限らないのが現状だ。
「DXを社内主導で進めようとした時、最初に当たる壁は『人材』だと思います。実際にガートナーの調査でも、ほとんどの企業がこの課題に直面しているという結果が出ています」(山田氏)
山田氏曰く、社内でDXを推進するためには2パターンの人材の採用が先決だという。それが「最初に強いリーダーシップを取って『内製化を進める人』」と「始まった後に採用面や育成面で『軌道に乗せる人』」だ。
「例えば、最初にリーダーシップを取れる人で考えると、確実に社内でDXを成功させている外部の人材を新たに採用する必要があります。なぜなら『やったことがある人しかできない世界』というものが確実に存在しているからです。特にトップに立つ人には、大手企業やメガベンチャーで大きなシステムを扱ったことがあるような経験が求められる傾向にあり、近年、CDOやCTOを外部から採用する企業が大幅に増えました」(山田氏)
なんだ、少し難しそうだからうちの会社はまだいいか……
そう思った人もいるだろう。しかし、山田氏は、10年という長期の目線で見た時にそのような企業は大きな損害を生む可能性がある、と警鐘を鳴らす。
「10年という長期目線で見ると、データアルゴリズムとそれを表示するインタフェースを押さえている会社が勝つというのはまず間違いないです。反対に言えば、そこに対しての競争力を持てなかった場合、大手企業でも競争力を失ってしまう企業が出てきても全くおかしくありません」(山田氏)
最後に、ここまで話を聞いてきた山田氏に自社の目標を聞いた。
「弊社は採用からスタートして生産性まで事業を広げてきました。今までは、人数こそ全てではないですが、スキルや経験よりも『何人採用できるか』と見ている企業も少なくない状態でした。しかし、これからは『どんな人がどのくらいいるか』が非常に大事になってくると思います。そのためには『給与水準をどれだけ上げられるか』『社員のモチベーションのための仕組みをどれだけ取りそろえられるか』といったことがとても大事になってきます。そのため、生産性が高い企業が採用力の高い企業になっていってほしいと思いますし、弊社もぜひそのお手伝いができればと思っています」(山田氏)