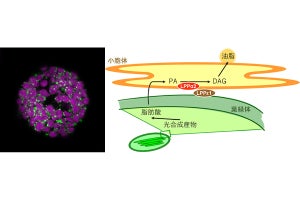東京農工大学(農工大)は4月12日、「付着散布」を行う"ひっつき虫"型の植物の種子を対象に、6種の中型ほ乳類の剥製模型を使用して、動物の体表に付着する種子の量に種間で違いが生じる要因を解明したと発表。またその付着量には、動物の体毛の長さや、種子が結実する高さと動物の各体部位の高さとの重複範囲の幅(以下「重複幅」)が影響することがわかったと併せて発表した。
同成果は、農工大大学院 農学府の佐藤華音大学院生、同・大学院 グローバルイノベーション研究院の小池伸介教授、ミュージアムパーク茨城県自然博物館の後藤優介副主任学芸員らの共同研究チームによるもの。詳細は、生態学に関する全般を扱う学術誌「Acta Oecologica」に掲載された。
種子散布は、自ら移動できない植物にとって、子孫を残すのと同時に分布を拡大できる唯一の機会だ。その散布にはさまざまな様式があり、そのうちの1つが、動物の体表に付着することで種子の分散を行う"付着散布"だ。
この方法では、幅広い種類の動物に種子が付着できると考えられているが、これまでの研究では、家畜やシカ類などの一部の動物種を対象に、種子が付着しているのかどうかを確かめるといった事例が大半だったという。そのため、実際に種子を運ぶと考えられる野生動物による付着散布の実態は、国内外においてほとんど知られていなかったとする。
そこで研究チームは今回、関東地方の平地に生息する一般的な中型ほ乳類を対象として、動物の体表に付着する種子の種類とその量の比較を行うと同時に、種子の付着量に影響する動物側の要因を調べたという。
種子の付着調査は、2021年から2022年にかけ、ミュージアムパーク茨城県自然博物館の野外施設にある林の縁において、体表に付着する種子の種類とその量を動物種間で比較するため、同博物館が所蔵するアカギツネ、アナグマ、アライグマ、タヌキ、ニホンイタチ、ハクビシンの中型ほ乳類6種の剥製模型を使用して行われた。
なお、模型には車輪が装着され、調査者が器具の後方に取り付けた棒を押して地面上を移動させることで、動物の歩行が再現された。そして模型を調査地内5地点で各10m走行させ、体表に付着した種子を体部位ごとに回収したという。
-

(左)調査に用いられた剥製模型。左からイタチ、タヌキ、ハクビシン、アライグマ、キツネ。(右)調査の様子。調査者が剥製模型を押すことで、実際に動物が歩いている様子が再現された(出所:農工大プレスリリースPDF)
また、冬に植物体が枯死した後の種子の付着状態も検証するため、植物が生育している10月と、植物が枯死した12月に付着調査を行ったとする。それと同時に、植物の種子の結実状態(高さや成熟の有無)も毎月記録し、種子の付着量は動物種間で異なり、付着量の違いには体毛の長さや重複幅が影響するという仮説を立てたうえで、検証が行われたとする。