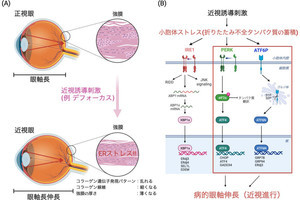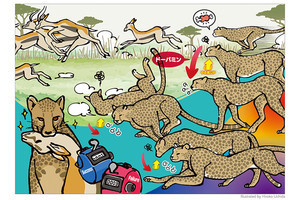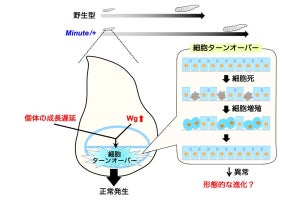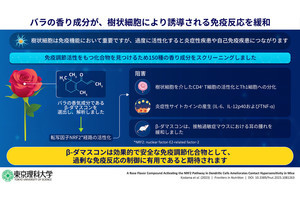理化学研究所(理研)は3月14日、神経細胞内で翻訳途中の「リボソーム」におけるタンパク質の品質管理の破綻が、発達障害などの神経疾患を引き起こす機構を、分子レベルで解明したことを発表した。
同成果は、理研 脳神経科学研究センター タンパク質構造疾患研究チームの遠藤良研究員、同・田中元雅チームリーダーらの研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。
細胞内において、mRNAの遺伝情報を翻訳して多種多様な新しいタンパク質を産生しているのがリボソームだ。翻訳の途中で異常が起きると、リボソームはmRNA上で停止し、タンパク質合成も途中で停止してしまう。このような未完成のタンパク質は細胞にとって有害となることから、「リボソーム品質管理機構」(RQC)が分解と除去の役割を担う。つまり、その機能的破綻はさまざまな疾患につながりうるということであり、その中には神経疾患の原因となる可能性も含まれている。ただし、神経細胞においてRQCがどのように機能しているのか、さらにはその機能不全がどのようにして神経疾患を引き起こすのかについては、これまでほとんどわかっていなかったとする。
そこで研究チームは今回、神経細胞内でのRQCの機能および神経疾患との関連を解明するため、RQCの主要因子の1つである「Ltn1」を欠損させ、RQC機能を喪失させたLtn1ノックアウト(KO)マウスを作製。同マウス由来のLtn1-KO神経細胞を用いて、まずはRQCの機能を失った神経細胞内でのタンパク質の変動を定量的プロテオミクス解析によって網羅的に調べることにしたという。その結果、Ltn1-KO神経細胞では、タンパク質「TTC3」と、タンパク質の翻訳後修飾の1つである「UFM1化」に関与するタンパク質群が著しく増加していることが判明したとする。
続いて、TTC3の神経細胞内での局在を解析したところ、主に小胞体に結合したリボソームのうち、40Sサブユニットに多く局在していることが明らかになった。このことは、TTC3が神経細胞内でmRNAの翻訳、特に翻訳開始に関与している可能性を示しているという。
さらに、TTC3とUFM1化との関連を調べるために、Ltn1-KO神経細胞内でUFM1化タンパク質をノックダウンすることによって発現を抑制したという。その結果、TTC3の量が著しく低下したことから、UFM1化はTTC3の量を安定化していることが示唆されたとする。
次に、TTC3の神経細胞内での機能、特にRQCへの関与を調べるために、人為的にリボソームを翻訳途中で停止させる配列を含む遺伝子を神経細胞に発現させ、合成が途中で止まったタンパク質(アレスト産物)の検出が試みられた。すると、Ltn1-KO神経細胞では予想通りアレスト産物を分解・除去できず、アレスト産物の蓄積が見られたという。さらに、Ltn1-KO神経細胞内でTTC3の発現を抑制すると、アレスト産物のさらなる蓄積が見られたことから、TTC3はRQCが機能しない時にアレスト産物のさらなる蓄積を防いでいることが確かめられた。