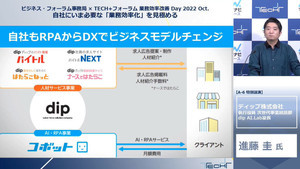銀行をはじめとする金融機関がこぞってデジタル化を進めている。日本5大銀行グループの一つに数えられるりそなグループも例外ではない。2018年にデータサイエンス専門のチームを社内に設置し、バンキングアプリをリリース。着実にデータ活用基盤を整え、デジタルバンキング戦略を推し進めている。
11月10日、11日に開催された「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」にりそなホールディングス データサイエンス部長の那須知也氏が登壇。これまでに同社が実践してきたデータ活用について語った。
【あわせて読みたい】「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」その他のレポートはこちら
4年で500万DLの大成功を収めたバンキングアプリ
りそなグループは首都圏と関西圏の二大都市圏を中心に店舗を展開する信託併営リテールバンキンググループだ。顧客数は1,600万人、法人顧客は50万社を数え、預金は61兆円に上る。
そんなりそなグループが描くデジタルバンキング戦略の対象は、大きく「会える顧客」と「会えない顧客」から構成されている。
会える顧客との接点は渉外担当者やATM、店頭でのタブレット端末などが担う。一方、会えない顧客との接点にはWebサイトやチャット、電話などが用いられる。この両方から取得したデータを分析し、商品開発と結び付けていくのが同グループのデジタルバンキング戦略である。
中でも中核チャネルとなるのがバンキングアプリだ。
りそなグループは、「スマホがあなたの銀行に」をキャッチコピーとしたバンキングアプリを2018年にリリース。那須氏によると、口座残高や入出金明細の確認はもちろん、振込などさまざまな取引をスマホで完結できる利便性が高く評価され、4年間で累計500万ダウンロードを突破(4月時点)し、多数の賞を受賞するに至ったという。
「アプリユーザーは20〜30代の比率が高いのですが、現在は中高年世代にもスマホが十分に浸透していることから、今後も利用率は落ちないと考えています。全世代にわたり、バンキングアプリがお客さまとの接点の中心になるでしょう」(那須氏)
中でも注目したいのは、月間の平均アクセス回数が11回を超えていることだ。バンキングアプリにアクセスするということは、ATMや銀行窓口に行くのと同じ意味を持つと那須氏は言う。
「月に11回もATMや銀行窓口に行くことはなかなかありません。手軽でアクセスしやすいスマホアプリだからこそだと言えます」(那須氏)
アプリを中心として、デジタル化は急速に進んでいる。2018年時点では口座開設手続きのほとんどが店頭で行われていたが、アプリをリリースして以来、アプリによる口座開設手続きが急増。2021年には積立定期預金と外貨預金の両方で8割超のユーザーがアプリでの口座開設を行うまでになっている。
このことは、グループの収益性にも貢献している。アプリを日常的に利用するユーザーが生み出す利益は、そうでないユーザーと比べて2.2倍、口座脱落率も1/5と非常に低く、優良な顧客だと言えるそうだ。
収益につなげるための「三拍子の掛け算」とは?
こうしたりそなグループのデジタルバンキング戦略を支えるのが、データマーケティングの取り組みだ。
那須氏によると、バンキングアプリを通じてそれまでとは比べ物にならないほど大量かつ整ったデータが収集できるようになったという。このデータを活かして、同グループは多様なマーケティング活動を行っている。
例えば、アプリ内で配信するアドバイス機能だ。
顧客に対して配信されるアドバイスは、データを基に一人一人出し分けられている。アプリをセットアップした翌日、セットアップの3日後、誕生月、年初などで配信される内容は顧客ごとに異なり、パーソナライズされたアドバイスによって、興味喚起から取引まで一直線に導いていく。申し込みに関する全ての手続きをアプリ内で完結できるため、離脱を防ぐ意味でも高い効果があるという。
「どんなに良いマーケティングモデルを構築しても、お客さまが途中で離脱してしまっては元も子もありません」(那須氏)
アドバイスの自動配信モデル数は年々増加しており、それ以外に手動での配信も組み合わせるなど、きめ細やかなコミュニケーションを確立してきた。配信数も右肩上がりで、2022年度は年間1億件を見込んでいる。
ただし、ユーザー数やアドバイス配信数などの「数」を追うだけでは収益化は実現できないと那須氏は指摘する。
「収益化するには、アクティブユーザー数とスムーズな取引導線、最適化されたコミュニケーションの三拍子を掛け算することが重要です。掛け算なので、どれか1つでもゼロになれば収益化もできません。一つ一つに対して、愚直に取り組むことが大切です」(那須氏)