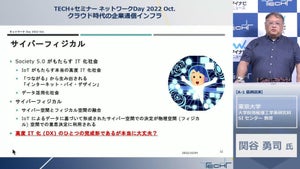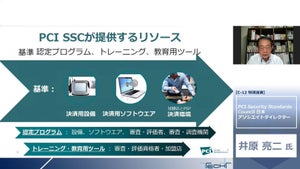データ時代の今、データはただ量を収集すればよいものではない。どう分析して洞察を得るか、いかに活用するかまでを常に考え、アップデートする必要がある。
11月10日、11日に開催された「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」の基調講演では、嘉悦大学 教授 高橋洋一氏が、「最近の政治経済情勢とデータについて」と題し、為替動向を例にとったデータ分析の基本的な考え方を伝授した。
【あわせて読みたい】「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」その他のレポートはこちら
データ分析の“川を上り、海を渡る”とは?
経済学者と紹介されることが多い高橋氏だが、講演の冒頭で「経済学者ではない。データサイエンティストだ」と明言し、データ分析における自身の考え方「川を上り、海を渡る」から説明を始めた。「川を上る」とは、過去の時系列(タイムシリーズ)データを揃えることを指し、案件にもよるが40~50年分遡ることが一般的だという。一方「海を渡る」とは、海外事例との比較だ。各国のデータを調べることであり、これは「クロスセクション」とする。
「データ分析を簡単に言うなら、タイムシリーズとクロスセクションの組み合わせです。川を上り、海を渡ると、データ分析はかなり完璧にできます」(高橋氏)
このやり方は政治や経済などでも応用できると言い、高橋氏は例として円と米ドルの為替について取り上げた。
今、為替動向は32年ぶりの円安を記録するなど、注目を集めている。では、円安はこのまま続くのか。
高橋氏は分析の前に、為替は「ランダムウォーク※」であり、短期的な予測はできないという前提を示す。しかし、サイコロ(特定の数字が出る確率が6分の1)を振る回数が増えれば当たる確率が増えるのと同じで、為替も長期的に見れば予測がしやすくなるという。
「たくさんサイコロを振ると、偶然要素がなくなっていき、結果的に理論値のようなものが出やすくなります」(高橋氏)
※次に現れる位置が確率的に無作為(ランダム)に決定される運動
為替の動向をどう予想するのか
では為替を長期的に見るにあたって、理論はどう考えるべきか。高橋氏は為替の性質を2種類の通貨の交換比率とし、それぞれの通貨のストックの割り算で考える方法が「あるべき姿」だとする。
通貨のストックとして現在のマネタリーベースがそれぞれ700兆円、5兆ドルであることから、700兆円÷5兆ドル。1ドル140円となる。
だが、「ここで満足してはダメ」だと強調した上で、1989年からの日米の為替レートとマネタリーベース比のグラフを示した。このグラフでは、両者がずれていることもあるが、動きは似ている。
「お金のストックで決まってくるという予想は、それほど嘘ではないのではないでしょうか」(高橋氏)
そこから、「ある程度の予測」だとしながら、「(為替は)2通貨のお金の量がどうなるかに依存する。それが予想できれば、為替レートがどのぐらいになるのかある程度分かる」という持論を展開。例えば、米国が金融引き締めをすればお金の量は減少する。5兆ドルあったものが4.5兆ドルになれば、700兆円÷4.5兆ドルになるので、1ドル155円となるのだ。もちろん、その逆も考えられる。
お金の量については、日本銀行の政策決定会合、米国の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録から、ある程度の予想ができる。
このように為替を例に数量分析の基本の考え方を説明しながら、「数字を分析することで、際限なく円安になることはあり得ないことが分かる」のだと高橋氏は説明した。