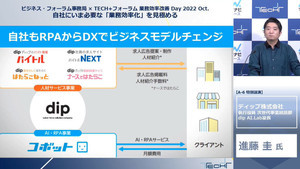DXを推進するにあたり、多くの企業が頭を悩ませるのが、既存のシステムや組織体制、これまでのやり方をどうやって変えていくかという部分だろう。効率的に進めるには何から着手するべきか、その答えは一つとは限らない。クレディセゾンでは、まずはこれまで外部ベンダーに依存していたIT部門の組織変革を行うところからスタートし、今や大きな成果を上げているという。
10月25日、26日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+フォーラム 業務効率改善 Day 2022 Oct. 自社にいま必要な『業務効率化』を見極める」に、クレディセゾン 取締役(兼)専務執行役員 CTO(兼)CIOの小野和俊氏が登壇。「クレディセゾンのDX戦略とクラウド活用」と題して、講演を行った。
【あわせて読みたい】「自社にいま必要な『業務効率化』を見極める」その他のレポートはこちら
まずは小さなデジタルチームで成功ケースを創出
かつて同社のIT部門は外部ベンダーに完全に依存しており、社内には技術に精通した人材が残らず、ノウハウも継承されないという課題を抱えていたのだという。さらに、経営層からのIT費用削減要請なども加わり、ITを武器として競争優位を確立できるような組織へと変革する必要に迫られた。
そこで同社は2019年~20年を「フェーズ1」として、IT部門とは別にデジタル組織を立ち上げ、デジタルカルチャーの醸成に取り組みながら、IT部門との融合を図っていった。ここでのポイントは、まずは小さく始めて成功事例をつくり、周囲の理解を得て、大きく拡大していくというアプローチだ。
「最初のデジタル専門チームは私を含めて3人という少人数体制で、従来のやり方に捉われず、最も良いと思われる方法を用いながら、とにかく成功を収めることに注力しました。すると“あのチームでは新しいやり方を取り入れて、上手くいっているんだね”と、周囲も心から賛成してくれるようになっていったのです」(小野氏)
全社システムに“栄養”が行き渡るよう、クラウド活用でシステム連携を促進
ここで小野氏は全社で取り組んだシステムの効率化の例を紹介する。クレディセゾンにおける全社システムのアーキテクチャは基幹システム、コア業務アプリ、デジタルサービスの3つのレイヤーに大きく分けることができる。2019年3月当時は、基幹システムへの依存度が非常に高く、システム連携が進んでおらず、基幹システムから周囲の末端まで「十分な栄養が行き渡りにくい状況にあった」と、小野氏は振り返る。
当時の課題を整理すると、以下の3つにまとめられる。
これらの課題を解決すべく同社では、まず課題1については基幹システムの機能を普遍的な機能に絞り込むようにし、課題2に対してはスムーズなシステム連携を促すための連携基盤を開発(API)、そして課題3に関してはクラウド活用やサービスAPIの開発、ITの内製化、新規パートナー開拓などの解決策を実施していった。
「目標として描いた理想のイメージは、基幹システムである幹にも、周囲のシステムやサービスである枝葉にも重要な栄養が行き渡り、木全体が生き生きと育つことができるような状態です」(小野氏)
そうして取り組んでいった結果、2019年当時、一部のアプリに限られていたクラウド活用領域は、基幹システムのクラウド化を成し遂げたことで、ほぼ全域に広がった。今は、新規システムやサービスに関してもクラウドファーストで検討するようにしているという。