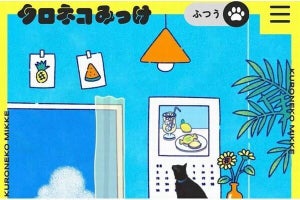私たちの日常生活に欠かせない飲み物として「コーヒー」がある。仕事で集中したい時や運転中の眠気覚ましなどで飲まれるのはもちろん、コーヒーに含まれるカフェインには脂肪燃焼作用があると言われていることからダイエットにも取り入れられているなど、コーヒーはさまざまな場面で愛飲されている。
そんなコーヒーを飲みたいと思った時、あなたはどのような手段でコーヒーを用意するだろうか。 本格的に豆から挽くという人もいれば、ペットボトルや缶コーヒーで済ますという人もいるだろうし、スターバックスコーヒーやドトールコーヒーといったコーヒーショップでテイクアウトしてくる人もいるだろう。 そして、それだけさまざまなコーヒーの用意の仕方がある中で、「カプセル式マシン」を使用しているという人も増えていることだろう。
自宅に置いているという人はもちろん、オフィスで共用スペースに置いてあることも増えたカプセル式マシン。そんなカプセルを作る上でもITが活用されていることはご存知だろうか。
今回は、「マルチブランド」「マルチドリンク」形式で、さまざまなカフェブランドと共同開発したコーヒーや紅茶、お茶が楽しめるカプセル式コーヒー&ティーマシンキューリグを展開しているカップスKEURIG事業推進部 部長の廣谷 俊介氏と、カプセルを製造しているユニカフェのR&Dセンター センター長である中村 洋介氏に、カプセル開発で活用している「味覚のデータ化」について話を聞いた。
コーヒーの決め手「味」と「香り」をデータ化?
時にコーヒーの味が「フルーティー」や「酸味がある」と表現されるのは、「味」と「香り」が作用しているといい、その味は品種や焙煎方法によって異なるのだという。
「コーヒーと聞いて想像されるのは、焙煎された後の黒い焙煎豆かもしれませんが、焙煎する前のコーヒーは赤い実をつけるフルーツの種子です。そのため種子の状態では青臭く、コーヒーのあの香ばしい香りは焙煎によって生まれるものです。そのため、焙煎方法や元の果実の品種によって香りや味が変わってくるのです」(廣谷氏)
キューリグでは、このコーヒーの決め手となる「味」と「香り」について専用の機器を用いて定量化することにより、味覚を再現性あるものに変換することに成功したのだという。
「味」を測るために、味覚センサーと呼ばれる機器が用いられている。この機器によって人間の舌で感じる味覚をデジタルデータで分析し、細やかな味わいのニュアンスまで可視化することで、カフェの味そのものを再現できるようになったという。この再現性を得るために、約1万検体の分析を行い、その分析結果に従って、コーヒー独特の「苦味」「酸味」「キレ」「ボディ」といった味覚をキューリグ独自の換算式で表現しているとのことだ。
もう1つの味の決め手「香り」については、ガスクロマトグラフ質量分析計という機器で、300を超える種類の香気成分の中から、コーヒーの9つの香気である「ハーブ」「フルーティー」「乳発酵(チーズ)」「硫黄」「カラメル」「ナッツ」「スパイシー・煙」「コゲ臭」「柑橘(酸)」に分類して表現している。
「本来、この味覚センサーやガスクロマトグラフ質量分析計はコーヒー専用の機械ではありません。そのため『このデータをコーヒーに置き換えるとどう表現されるか』ということを約2年にわたって研究し、『コーヒー専用の換算式』を生み出しました」(中村氏)
ここで細やかな分類分けをされた「味覚」と「香り」は、グラフなど可視化できる形でブランド側に渡されるという。従来のコーヒーは、個人の経験や感覚に頼って調整されていることが大きかった。そのため、このような結果が可視化できるという状態は、顧客にとっても自社のコーヒーの味を客観的に感じられるようになり、商品開発の際に的確なキャッチボールが可能になったという。
「このデータ化を用いても、最後にはやはりプロの感覚が決め手となる部分も多くあります。データとプロの感覚の両方をフルに活用することで、より良い商品を開発することができていると思います」(中村氏)
コーヒーを通じたコミュニケーションの輪を広げる
「どんなコーヒーがお好きですか?」
そう筆者が問いかけられたのは、取材の終盤に着席した時に入れていただいたコーヒーに口を付けている時だった。
実際のところ、筆者はどうにもコーヒー独特の苦みが苦手で、人生においてほとんどコーヒーを飲んだことがない。少し気まずいながらそう答えると廣谷氏と中村氏は顔を見合わせて、「せっかくでしたら、弊社のコーヒー診断を受けてみませんか?」と提案してくれた。
コーヒー診断とは、キューリグが同社のWebサイト上で無料公開しているもので、何択かの質問に回答していくと自分好みのコーヒーを紹介してくれるというサービスだ。回答を進めていくと、最後におすすめのカプセルと味覚のデータで自分の好みがどのあたりなのかを教えてくれるようになっている。
「弊社では、お客様がコーヒーを通じたコミュニケーションが取れることを目標にしています。今回受けていただいたコーヒー診断もその一つで、この診断が会話のきっかけになったり、お互いの好みを知るための第一歩になったりすれば良いなと考えています」(廣谷氏)
最後に廣谷氏に今後の展望を聞いた。
「われわれはお店でバリスタの方が入れてくださる味をそのままご家庭で飲めるように開発をしています。それには、毎回同じ抽出方法や抽出時間を取ることができるカプセル式マシンが最適なのです。『名店の味を預かっている』ということを忘れずに、ブランドとして正解だと思う味をご家庭に届けていきたいです」(廣谷氏)
2019年の日本におけるコーヒーの消費量は、農林水産省調べで約45万3千トンだったという。また、全日本コーヒー協会が行った「コーヒーの需要動向に関する基本調査」によると、2020年の1人の1週間当たりの杯数は、11.53杯にも上ったという。この数字を見ただけでも、コーヒーは日本になくてはならない飲み物の1つだということがよくわかる。
そんなコーヒーを少しでも美味しく届けるために日々研究を重ねる、そんなコーヒー業界の未来を支えていくのはテクノロジーの力かもしれない。