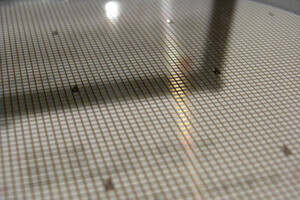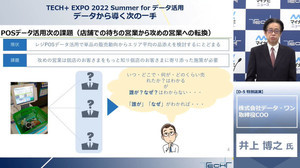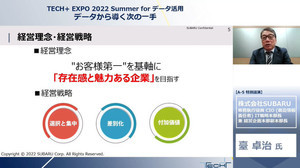1928年の創業以来、産業や社会の基盤を支える存在として「エネルギーと環境の調和」を課題の中心に据え、ビジネスを展開してきた日揮グループ。エンジニアリング業界の大手企業として、世界各国で数万件におよぶ大規模プロジェクトを成功させてきた。
7月22日に開催されたセミナー「TECH+ フォーラム 製造業 DX Day 2022 Jul. 持続的な競争優位性を構築する」に、日揮ホールディングスから専務執行役員 CHRO・CDOの花田琢也氏が登壇。「デジタルジャーニー実現のためのビジョンと組織造り」と題して、日揮グループの新たなIT戦略である「ITグランドプラン2030(以下、ITGP2030)」実行時の課題および解決方法、自らの経験をベースとした人材活用術、ニーズの本質をつかむ方法などについて解説した。
急務となったデジタルジャーニーの実現と「ITGP2030」策定
日揮グループでは2018年12月に、新たなIT戦略としてITGP2030を策定した。同グループのメイン事業はエネルギープラント建設であり、いずれも工期が数年におよぶ大規模なもの。建設のピーク時には、約4万人もの作業員が業務に従事することもある。
「サイトマネジャーは、ある意味で市長クラスの権限および責任を持ってプロジェクトの完遂を目指しています。そしてこれだけのスケールになると、デジタル技術を使わずに建設することは不可能です。3Dモデルも20~30年前に導入済みですし、その他にもさまざまな部分でデジタル技術を駆使してきました。しかしながら、どこかで同業他社に立ち遅れていた部分があったのです」(花田氏)
遅れの原因は、「長期的なビジョンとグランドプランの不在」「最新のIT技術をイノベーションに活かせていない」「データ活用の不十分さ」「グループ内におけるIT適用の不統一」といったことにあった。こうした課題を抱える中、ITGP2030策定につながる“黒船”となったのは、メジャーオイルトップマネジメントからの助言だったそうだ。その内容は、「2030年に工数は3分の1、スピードは2倍になり、乗り遅れればマーケットからキックアウトされる。これを回避するには、とにかくデジタルジャーニーを急ぐこと」というものだ。これを受けて日揮グループでは、分散していたデジタル機能を1つの部門に統合。約半年をかけ、2030年に向けたIT戦略としてAI設計/プロジェクトデジタルツイン/3Dプリンタ・設計自動化・新素材/標準化・Module化したプラント/スマートコミュニティという5つのイノベーションを含むITGP2030の策定を行ったのである。