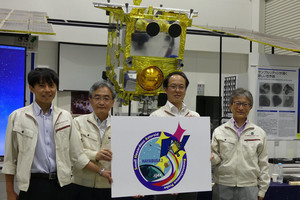宇宙航空研究開発機構(JAXA)、海洋研究開発機構(JAMSTEC)、高輝度光科学研究センター(JASRI)、国立極地研究所、分子科学研究所、神奈川大学、英・オープン大学、大阪大学、立命館大学、名古屋大学の10者は8月16日、2021年6月20日から開始した小惑星リュウグウ粒子のPhase-2キュレーションの分析成果として、「リュウグウ粒子は、かつて太陽系外縁で形成され、水と有機物を多数含んでいた。このような始原的な小惑星は、後に太陽系の内側まで移動し、地球に水や有機物を供給した」という仮説を発表した。
同成果は、JAMSTEC 超先鋭研究開発部門 高知コア研究所の伊藤元雄主任研究員を代表とする、日米英の100名超の研究者が参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。
リュウグウは約46億年前に形成されて以降、熱による影響が少なく、太陽系形成時の有機物や含水鉱物を今も残している可能性があると考えられている。このような有機物や鉱物から化学的情報を得ることで、太陽系の形成史や、地球の水の起源、さらには地球生命に至るまでの有機物進化過程などの解明も期待されている。
Phase-2キュレーションでは、まず大型放射光施設SPring-8において、リュウグウ粒子のX線CT撮影が実施された。各粒子の形状や内部構造を取得することで、どの部分がどの分析に適しているかが決定され、国内外の研究機関それぞれに、粒子が地球大気に触れないようにして輸送された。
伊藤主任研究員らのPhase-2キュレーション高知チームには、8個の粒子が配分された。それらは大きさが1~4mm程度と米粒ほどで、合計重量は50mgほど。分析結果に基づく同粒子の元素組成は、これまでに発表された成果と矛盾がなく、「リュウグウは太陽系全体の元素組成を代表する始原的な物質である」という確証が得られたという。
-

(左上)配布された最大のリュウグウ粒子「A0002」。(左下)SPring-8で取得された放射光X線CT像。(中央)リュウグウ粒子中の水が関与してできた鉱物群。赤は含水ケイ酸塩鉱物、緑は炭酸塩鉱物、青は酸化鉄、黄は硫化鉱物。(右)中央図の白四角領域の電子顕微鏡拡大図 (C)Ito et al.(2022)より改変 (出所:SPring-8 Webサイト)
また、粒子ごとに多少の違いはあるが、水が関与して形成したと考えられる鉱物が多く見られるとしている。このことから、リュウグウには過去に氷が存在し、その氷が溶けてできた水と、もともと含まれていた鉱物が反応した結果、現在観察されている鉱物が作られたものと考えられるとしている。
さらに超高解像度二次イオン質量分析装置を用いた詳細分析から、水素と窒素は、地球と比べると重い同位体成分に富んでいることが判明。この結果は、宇宙塵と良い一致を示すばかりではなく、彗星の値に近い傾向も見られるという。このことは、リュウグウ粒子は熱の影響をあまり受けず、形成当時の物質科学的情報を保っていることを示唆しているとのことで、同粒子は、太陽系外縁部で形成後、現在の位置まで移動したことが考えられるとする。
-

水素と窒素同位体比は、太陽系外縁部での形成を示唆。グラファイトからなるプレソーラー粒子(太陽系形成以前に、超新星などの星周環境で生成された太陽系外起源の微粒子のこと)も確認された (C)Ito et al.(2022)より改変 (出所:SPring-8 Webサイト)
加えて、走査型透過X線顕微鏡(STXM)と超高分解能透過型電子顕微鏡(TEM)による観察から、脂肪族炭化水素に富む有機物は、粗粒の含水ケイ酸塩鉱物と複雑に入り混じった組織を持つことが判明。同組織は、有機物が水の存在下で鉱物と反応したことを示す直接的証拠だという。