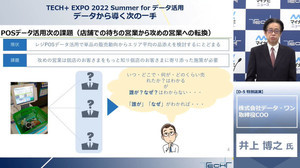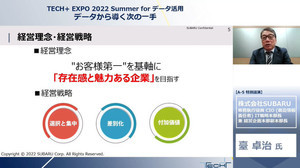2022年10月に施行される改正育児・介護休業法では、「出生時育児休業」の制度が新設される。これにより企業は、従業員の休業期間中の就労の可否の検討、労使協定の締結、規程改訂などにかかる実務対応が求められている。改正に伴い、企業側はどのような点に注意しておくべきだろうか。
7月20日に開催された「TECH+セミナー 労務管理 Day 2022 Jul. 法改正で更に変わる! 多様な働き方と労務管理」にて、多田国際社会保険労務士法人 代表社員 多田智子氏が解説した。
-

多田国際社会保険労務士法人 代表社員 多田智子氏
出生時育児休業とその分割取得の活用イメージ
2022年4月より段階的に実施されている育児・介護休業法の改正。厚生労働省は、法改正の目的として「出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得を可能とする規定の整備、事業主に対する個別の労働者への育児休業に係る周知および意向確認の義務付け等の措置を講じること」を挙げている。
-

育児休業法改正の概要
特に10月の改正では、出生時育児休業が新設されるほか、育児休業の分割取得および育児休業中の就業が可能となることが大きなポイントとなる。
多田氏は、出生時育児休業について「男性従業員から『育児休業を取りたい』と言われたら、出生時育児休業なのか、育児休業なのかを確認をする必要があります。実際には、まず出生時育児休業を取得するケースがほとんどになると思っています。その後に育児休業を取るという世界観になるでしょう」と説明する。
また、子の出生後8週間までの期間に、最大4週間の育児休業を2回まで分割して取得可能になることについて多田氏は、「初めにまとめて2回分の休業を申し出なければならないことに注意が必要です。また、通常の育児休業は1カ月前ですが、出生時育児休業の申出は原則2週間前まで。ただし、労使協定を結ぶ場合は1カ月前までにすることもできます」と注意点を述べた。さらに、「社内周知の際に、なぜ2回に分けて取れるのかという疑問が生じることが考えられるでしょう。厚生労働省としては、父親側の都合を想定し、出産時にまず1回、里帰り出産から戻るタイミングでもう1回取得するという使い方をイメージしています。里帰り出産しない場合は、1回で4週間の休業を取得しても問題ありません。このイメージを人事から従業員へ伝えておく必要があります」ともアドバイスした。
-

出生後8週間以内の育休取得例