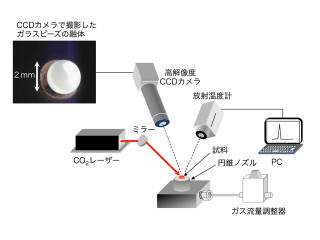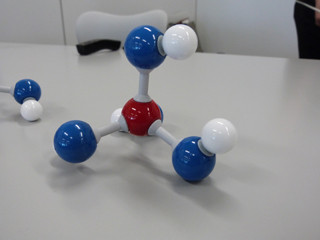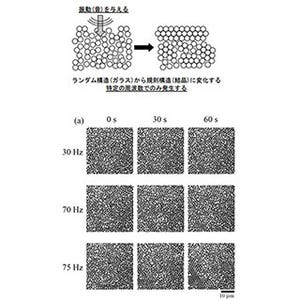愛媛大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)、山梨大学、理化学研究所(理研)は5月16日、大型放射光施設SPring-8の高強度の高エネルギーX線を活用することで二酸化ケイ素(SiO2)ガラスの高圧下における構造変化の解明に成功したと発表した。
同成果は、愛媛大 地球深部ダイナミクス研究センターの河野義生准教授ら20名強の研究者が参加した共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
四面体構造を持つ液体や非晶質(アモルファス)物質は、高温もしくは高圧環境下において異常な特性を持つことが知られており、その構造的起源の理解は、物理学、化学、地球科学、材料科学などの多くの科学分野において重要な課題とされている。
水は特異な特性を持つことが知られているが、地球上でありふれた物質の1つで、ガラスの材料などに用いられるSiO2も特異な性質を有することが知られている。例えばSiO2の液体や、非晶質構造の固体であるガラスは、高温下において密度の最大化したり、加圧時に粘性が低下したり、高圧下において圧縮が最大化したりするなどの異常特性が知られている。
そのため、そのメカニズムの理解は物理学のみならず、地球・惑星内部におけるケイ酸塩マグマの理解や、材料科学における酸化物ガラス材料の特性の理解などの幅広い科学分野において重要な未解明問題とされている。
水における異常特性の構造的起源として、「二状態仮説」が幅広く研究されており、そこでは水の状態を2種類の局所構造の混合状態と仮定し、水の液体構造に潜む四面体構造の割合の温度・圧力による変化が異常特性に重要な役割を果たしていることが理論研究により提唱されている。
SiO2においても水と同様に、二状態構造的記述が可能であることが理論研究により示されており、四面体性の高い構造である「S状態」の割合の変化が、SiO2液体の異常特性を制御するパラメーターであることが提案されているところだという。しかし、SiO2液体もしくはSiO2ガラスに潜む四面体構造や、その高圧下における変化についての実験的な証拠は、これまで見つかっていなかったという。