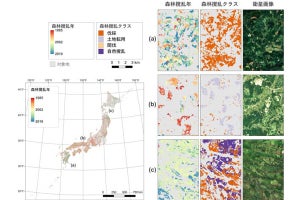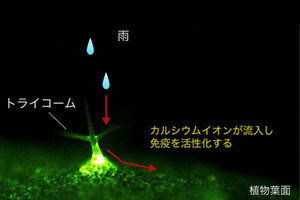北海道大学大学院理学研究科の小川宏人教授らの研究グループは、物体を触角で触れているコオロギの逃避行動を詳細に観察することで、昆虫が触角を通じて周囲の空間を認識していることを確認したと発表した。
詳細は科学ジャーナル「Journal of Experimental Biology」誌にオンライン掲載されている。
動物は感覚器官を通して外界を知覚し、特に空間情報を得るためには視覚が用いられることが多いが、夜行性や暗所を好む動物の場合、体性感覚※1が重要な手掛かりとなる。特にげっ歯類※2のヒゲや昆虫の触角は、それを積極的に動かすことによって周囲にある物体を検出するという。
例えば、昆虫は頭部の触角を積極的に動かし周囲の物体を知覚する。しかし、既往の研究では、昆虫が触角を用いて周囲を「認識」しているかは不明であった。なぜなら、周囲の空間全体を認識しなくとも、触角への刺激に対して一定の関係性をもって反応すれば、触角を使う行動が説明できるからだ。
そこで、同研究グループは、球形のトレッドミル上にコオロギを保持し、その前や横にさまざまな物体を置いて触角で触らせた状態で短い気流刺激を与え、それによって生じる逃避行動を調査した。
気流刺激は触角ではなく、腹部にある尾葉と呼ばれる別の感覚器官によって検出されるため、仮に逃避行動が変化すれば、コオロギが触角から得た空間情報を別の行動に反映させていることになる。
実験の結果、コオロギは物体の形や位置、向きによって逃避行動の進路を変えた。その進路は障害物との衝突を避けるようにカーブし、特に前に壁を置いた場合は、進路を変えるだけでなく、反応までに時間がかかり、逃避距離が短くなった。
これらの結果から、コオロギは触角を使って周囲の障害物の配置や向きなどの空間配置に合わせて、別の感覚刺激によって生じる行動を変化させることが分かった。研究チームは同成果を昆虫が触角を介して周囲の空間を「認識」している、言い換えれば「イメージ」していることを示唆する初めての報告だとしている。
研究グループでは同成果を踏まえて、コオロギの空間認識能力がどこまで優れているのか、あるいは視覚情報とどのように統合されるのかを調査する行動学的な研究と、コオロギの脳内で空間配置を表現する神経活動を光学計測などの方法によって明らかにする研究を進めるという。
-

コオロギの機械感覚器官と逃避行動の変化。A:コオロギの触角器官と尾葉器官。B:コオロギの前に壁を設置したときの逃避行動進路。上は左半分に、下は中央に壁を設置した場合。壁がない場合は直進するが(グレー)、上では壁と反対側に、下では左右のどちらかに軌跡(青)がカーブする(出典:北海道大学)
文中注釈
※1:触角、温度感覚、痛覚の皮膚感覚と、筋や腱、関節などに起こる深部感覚のこと
※2:げっ歯目の哺乳類の総称。リス、ネズミ、ヤマアラシなど