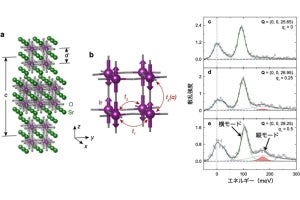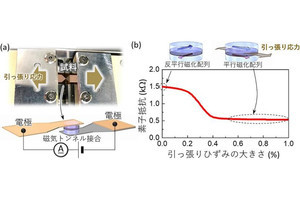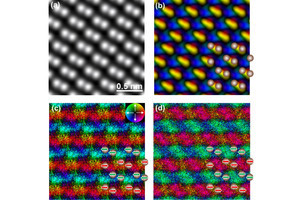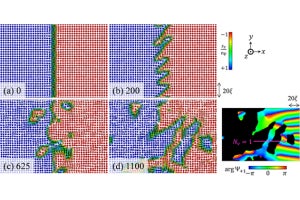慶應義塾大学(慶大)は2月21日、磁石に音波を注入すると、「磁気回転効果」によって起電力が発生することを理論的に示したことを発表した。
同成果は、慶大 グローバルリサーチインスティテュートの船戸匠特任助教(スピントロニクス研究開発センター)と中国科学院大学カブリ理論科学研究所の松尾衛准教授の国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する主力学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。
磁気回転効果は、ミクロな角運動量である電子スピンが力学的な回転運動(マクロな角運動量)と互いに変換可能である現象であり、物質を高速回転させるほど磁気回転効果は大きくなるが、毎秒1万回転程度の高速回転であっても、磁場換算で地磁気以下の極めて微弱な効果しか得られないことから、これまであまり注目されていなかったという。しかし、2020年、慶大の能崎幸雄教授らの研究チームが、固体表面を伝搬する音波(表面弾性波)を用いることで、結晶格子点を1秒間に10億回以上回転させ、磁気回転効果によってスピン流が生み出されることを実証。表面弾性波を非磁性金属の銅と強磁性体を複合した材料に注入することで、交流のスピン流を銅の中に生み出し、これを隣接する強磁性体に作用させることによって磁気の波を励起することにも成功したほか、スピン流と電流を相互に変換する物質として知られている白金を銅と強磁性体の複合材料へ接合させることで、磁気回転効果により生み出された交流スピン流を起電力へ変換させ、電気的に検出することに成功したことが報告された。
しかし、この手法では、白金のような貴金属を必要とする必要があるほか、3種類の物質を複合させるといった複雑なデバイス構造を必要するなど課題があった。そこで研究チームは今回、強磁性金属の単膜というシンプルなデバイス構造において、磁気回転効果に由来した起電力が発生することを理論的に提案することにしたという。
強磁性金属に表面弾性波を注入すると、強磁性体内の自由電子スピンには格子の回転変形に伴って磁気回転効果が働く。同時に、強磁性体の磁気には弾性変形に伴って向きが変化する「磁気弾性効果」が働くことで、磁気の波が励起される。この磁気の波が自由電子スピンへ作用することで、起電力が発生するというメカニズムだという。今回の研究では、自由電子スピンへ働く磁気回転効果と磁気へ働く磁気弾性効果の2つの効果が組み合わさることで、貴金属や複雑なデバイス構造を必要とせずに、磁気回転効果に由来する起電力が発生することが確認されたとする。
また、表面弾性波の一種である「レイリー波」により発生する起電力が解析され、弾性波の進行方向および磁性体の膜厚方向へ起電力が生じること、またレイリー波の進行方向と磁性体の磁気の向きについて非相反性が現れることも判明したほか、強磁性金属としてニッケルを用いた場合に実験で観測可能な大きさの起電力が生じることも明らかとなったという。
なお、研究チームによると、今回のメカニズムを用いれば、これまで困難だった磁気回転効果のスピンデバイスへの応用に道を拓くことにもつながるという。しかも、音波さえ生み出すことができれば、ほかに制限を受けることなく幅広いスピンデバイスに対して磁気回転効果を応用することが可能であるため、ジュール熱を伴う電流に比べ、エネルギー損失が少ないため、磁気デバイスの高性能化・省電力化が実現でき、かつ安価なレアメタルフリー技術として貢献できるとしている。