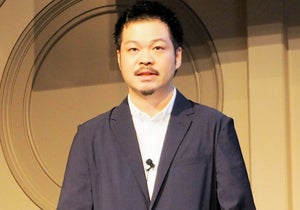2022年の年頭にあたり、Tableau 日本 カントリーマネージャーの佐藤豊氏は年頭所感として、以下を発表した。
パンデミックが続いた2021年は、多くの組織がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進め、政府においてはデジタル庁が発足するなど、データの重要性がさらに高まった年でした。当社が調査会社に依頼して実施したパンデミックにおけるコミュニケーションに対する管理職の意識調査によると、コロナ禍においてビジネスコミュニケーションに対する影響をポジティブととらえているリーダーは、データ量を増やした企業の場合、そうでない企業の3倍となっています。DXはデータトランスフォーメーションであり、データ量が増加することは企業にとって様々な機会をもたらします。その機会をどのように活用するかが、今年は重要になると考えます
データのさらなる民主化
2022年、データの民主化はさらに進んでいきます。爆発的に増加している大量のデータから、企業がいかにインサイトを得られるか、データへのアクセス確保が課題となります。そのため、データを標準化してより人々が利用しやすいものにすることが肝要です。機械学習やAIなどの革新的なテクノロジーで、データ分析のハードルが下がり、分野の専門家であるビジネスパーソンが自らの洞察を提供できるようになります。
またビジネスプロセスに分析を取り入れることで、データドリブンな意思決定がより迅速になり、組織はよりアジャイルに急激な環境変化や要求に対応できるようなります。すべてがデジタル化された環境で、どこからでも働くことができるようになる「Digital HQ」に職場が移行している現在、データと分析の民主化は特に重要になります。データは、組織が意思決定を行う際の共通項となるでしょう。
社内のデータ人材の育成
昨今、日本の大学や教育機関でデータサイエンス学部や講座が増えてきています。データサイエンス教育の重要性が認められ、若い世代からデータスキルを身につける取り組みが進んでおり、今後も盛んになると期待しています。
同時に、分析ユビキタスの時代に入っているため、一般的なビジネスパーソンも分析を仕事に必要なスキルとして受け入れるようになります。分析のためのデータを準備する能力から、データ主導の洞察を効果的に伝達する能力まで、さまざまなスキルにおける熟練度に応じた仕事が生まれます。
職場では、リーダー自らが従業員の模範となってデータリテラシーを向上する必要があります。当社の昨年の同調査では、議論を推進するためにビジネスリーダーによるデータの使用と組織との間には強い相関関係があることが明らかになりました。リーダーが率先してデータ分析を習慣にしている組織ではデータ分析も頻繁に行われています。
信頼を築き、ビジネスの成果を引き出すデータカルチャー
今年、注目すべきことは、データの利用が、どうビジネスの成果に影響を与えるかです。パンデミックによりスピードの必要性が浮き彫りになりました。意思決定におけるアジリティは、より多くの人々が意思決定を行い、行動に移すことができる文化があってこそ実現できるものです。
そこでデータカルチャーが重要になります。データカルチャーは意思決定のためにデータ利活用に価値を置き、実践し、奨励する人々の集まりです。重要なのは、それに対する私たちの行動です。そのような行動の一つに信頼があります。特に規制の厳しい業界ではガバナンスが非常に重要であり、信頼性の高い環境を構築することで、データを扱う人々に信頼を置くことができ、ひいては人々は活用しているデータを信頼することができます。
2022年、部署や組織との間のデータの壁が取り払われ、より広範囲で自由かつ創造的なデータ活用が可能となることが、日本経済の成長に大きく寄与すると考えております。そのためには、誰もがデータリテラシーを身につけ、データカルチャーが組織全体、グループ全体に普及することが重要です。今年もTableauはそのようなお客様や皆様の成功のために力を尽くして参ります。