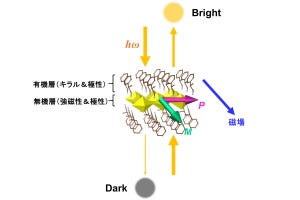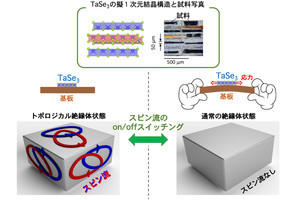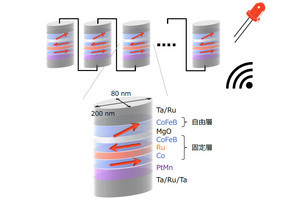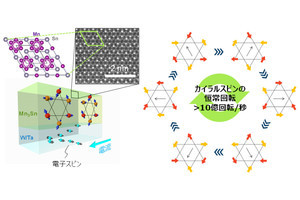名古屋大学(名大)は6月2日、「パラジウム酸鉛」に鉄とリチウムを少量、共置換することによって400℃以上の高温から磁石になる材料である強磁性半導体セラミックス「PbPd0.93Fe0.05Li0.02O2」を発見したと発表した。
同成果は、名大大学院 理学研究科の寺崎一郎教授らの研究チームによるもの。また同成果は、名大が展開しているプログラム「名大 MIRAI GSC」(科学技術振興機構の「次世代人材育成事業グローバルサイエンスキャンパス」の1つ)の一環で、寺崎教授の機能性物質物性研究室において研究を行った2人の高校生による成果が出発点となったという。詳細は、応用物理学を扱う国際学術誌「Journal of Applied Physics」に掲載された。
永久磁石の基盤となる強磁性体は、鉄やコバルトのような遷移金属、もしくはサマリウムやネオジムといった希土類の合金であることが一般的でシリコンやガリウム、ヒ素などの半導体は強磁性を示さないことが知られている。
そうした中、1990年代に入り東北大が、現在の同大総長である大野英男教授率いる研究チームにより、ガリウム・ヒ素のガリウムの一部を磁性元素であるマンガンに置換することで、半導体と強磁性の性質を併せ持つ物質「強磁性半導体」の開発に成功した。強磁性半導体は、その電子のスピンが電場などで制御できることから、スピントロニクスを実現する材料として、その後、世界中で精力的に研究されるようになった。
ガリウム/マンガン・ヒ素の欠点は、強磁性を示す温度(キュリー温度)が低く、低温でしか強磁性を利用できない点だ。室温で動作する素子を作るためには、キュリー温度を室温以上にする必要があるが、それを実現するのはなかなか容易ではないという。
そうはいっても、これまで多くの研究者が室温以上で強磁性を示す半導体を報告することに成功しているともいう。ただし、それらは薄膜試料で得られる磁化の絶対値がとても小さいものであり、ほんのわずかに混入した強磁性不純物による“ニセ”の強磁性の可能性を排除できず、室温強磁性半導体を巡る議論が続けられてきたという。
ところが、今回発見された「PbPd0.93Fe0.05Li0.02O2」は、グラム単位のセラミックス試料という巨視的であり、室温で永久磁石に吸い付くというこれまでにない明白な応答を示すことが確認されたとする。この物質は「PbPdO2」(鉛・パラジウムの酸化物)が基本物質で、まずパラジウムの5%を鉄に置換して「PbPd0.95Fe0.05O2」とするという。ただ、この時点では、まだほぼ非磁性だという。
そこからさらにパラジウムの2%をリチウムに置換することで誕生するのがPbPd0.93Fe0.05Li0.02O2で、このわずかな違いで、400℃以上の高温から強磁性を発現することになるという。400℃以上という温度は、これまで知られている理論では説明できないほどの高い強磁性転移温度であり、PbPd0.93Fe0.05Li0.02O2の強磁性メカニズムは現時点では未知だとのことであり、まったく新しいタイプの強磁性半導体セラミックスである可能性があるという。
今回の成果の大元となった2人の高校生が行った研究は「室温で強磁性を示す半導体セラミックスの開発」というテーマで、前年度の寺崎研究室の修士大学院生が研究していた物質である「(Pb,Ag)Pd0.95Fe0.05O2」の結果を土台に、「Pb(Pd,Fe,Li)O2」が強磁性になるのかを調査するというものであったという。
この実験の結果、リチウムを2%入れたときに大きな強磁性信号が出ることが発見され、その後も2人は研究を続け、リチウムを5%入れてみたところ、強磁性信号が失われることも発見したという。今回の研究成果は、この2人が発見した組成を中心に、ほかの測定を組み合わせて基礎物性を掘り下げた結果だという。
寺崎教授らは、今回の発見は数gの試料で強磁性を確認することができたという点で、これまでの報告とは一線を画すものだとしている。グラフでデータを示すだけでなく、永久磁石に試料が確実にくっつくことを見せることができ、室温以上で強磁性を示す半導体が存在することを明らかにした点で、ほかの強磁性半導体の研究にも影響を与えると思われるともしている。
また今回のPbPd0.93Fe0.05Li0.02O2の持つ強磁性は、既存の理論では説明ができそうにないため、新しいメカニズムによる「高温強磁性半導体」の可能性を示しているともしている。
なお、研究チームでは今後、メカニズムの解明と共に、同様の物質の開発が進めば、高温強磁性半導体が有力なスピントロニクス素子の基板材料となることが期待されるとしている。