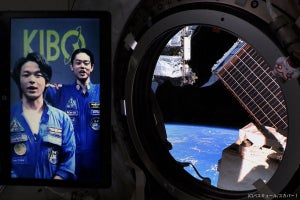2020年11月29日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「光データ中継衛星」を搭載した、H-IIAロケットが打ち上げに成功した。
光データ中継衛星には、JAXAが開発した「光衛星間通信システム」、愛称「LUCAS(ルーカス)」と呼ばれるシステムを搭載。地球観測衛星などとのデータ中継をレーザー光を使って行うとともに、そのデータを中継し、地上に送り届ける役割をもっている。運用が始まれば、地球観測衛星と地上とが通信可能な時間が従来の約4倍に向上、さらに通信速度は従来の約7倍に向上すると期待されている。
データを中継する衛星を打ち上げること、またその通信を「光化」することで、宇宙開発や私たちの生活にどのようなメリットがあるのだろうか。
衛星でデータを中継するメリット
光データ中継衛星には大きく2つの目的である。そのうちのひとつが、「他の衛星のデータを地上へ中継すること」である。
地球観測衛星などの衛星はすべて、ただ地球や天体、宇宙などを観測したり計測したりしただけでは意味がなく、そのデータをしっかりと地球に送り届けて初めて意味を成す。たとえば地球観測衛星なら、地球を撮影したデータを地上で分析することで、ある地域で起こっていることを把握し、それを都市計画や防災、科学的な調査、ビジネスなどに役立てたりできるのである。
しかし、衛星は地球のまわりを回っており、そして地球も自転をしているため、衛星から地上へデータを送れる機会は限られている。たとえば地球観測衛星のような地球を南北に回る衛星の場合、地上のある1か所の地上局のアンテナと通信できる時間は、1回あたり最大でも10分、1日の平均通信可能時間は最大1時間ほどになってしまう。
近年では、準リアルタイムである地点の画像を手に入れたいという、データの高頻度、即時性向上といったニーズが高まっているが、これではもし世界のどこかで災害が起きた際などに、その場所を迅速に衛星で撮影し、データを手に入れるということは難しい。
そこで、地球の赤道上空の高度3万5800kmにある静止軌道に、その通信を中継する衛星を置けば、地上から直接通信できないときでも通信ができるようになる。これにより、1回の通信可能時間は最大40分、1日の平均は最大9時間にまで大きく広がり、衛星からのデータをより迅速に得られるようになるばかりか、逆に衛星へのコマンド(指令)送信も迅速にできるようになる。
JAXAではかつて、2002年にデータ中継技術衛星「こだま」(DRTS)を打ち上げ、運用したことがあり、陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)に対して、災害などが起きた際に「こだま」を中継して緊急観測コマンドを送るとともに、観測データも即時に取得することで、中継しない場合に比べ短時間での運用を実現。東日本大震災をはじめ、国内外で起きたさまざまな災害状況の把握で多大な貢献を果たした。
「こだま」は2017年に運用を終えているが、今回打ち上げられた光データ通信衛星はその後継機として、2021年度以降に打ち上げられる予定の新しい地球観測衛星である「だいち3号」(ALOS-3)や「だいち4号」(ALOS-4)のデータ中継を担い、災害時などの運用に役立てられる予定となっている。
-

データ中継衛星がない場合とある場合との比較図。黄色がデータ中継衛星を使用せず、地上と直接通信する場合の通信可能時間を、紫が静止衛星に置いたデータ中継衛星を使って通信を中継した場合の通信可能時間を示している (C) JAXA
データ中継に使う通信を「光化」するメリット
そして、この衛星のもうひとつの目的が「他の衛星との『光化』」である。
前述のように、近年、地球観測衛星のデータの高頻度、即時性向上といったニーズが高まっているのと同時に、そうした衛星が撮影する画像の画質や情報量、画像サイズも大きくなっており、通信回線の容量を増やすことも求められつつある。
そこで光データ通信衛星では、衛星との通信のやり取りに、従来使っていたマイクロ波(電波)ではなくレーザー光を使う、「光衛星間通信システム」、愛称「LUCAS(ルーカス)」が搭載されている。
地上のインターネットでも光回線が普及しているのと同じく、衛星通信も光を使うことで、帯域などの制限が少ない、ギガビット級の高速・大容量の通信が可能になる。前述した先代のデータ中継衛星「こだま」の通信速度は240Mbpsだったが、LUCASでは1.8Gbpsとなり、じつに7倍以上の高速化となる。
レーザー光の波長は、地上の光ファイバー通信でも一般的に用いられている1550nm(近赤外)帯を使う。この波長は、人体に対して安全であるうえに、伝送損失も小さくでき、さらに地上の光ファイバー通信で確立された技術を活用でき、くわえて将来的に地上の技術革新を取り入れられる発展性もあるなど、数多くのメリットがある。
また、通信を光化することにより、小型・軽量な通信機器を実現することができ、衛星への搭載性が高まるというメリットもある。たとえば、前述の「だいち」と「こだま」では、「だいち」側のアンテナは直径1.3m、「こだま」側は直径3.6mのものが必要だったが、LUCASでは地球観測衛星側はわずか10cm、光データ通信衛星側も15cmと、桁違いの小ささにできる。
さらに、通信相手の地球観測衛星がもつ、高分解能な地球観測センサーへの擾乱による影響を小さくすることができ、また通信波の広がりが小さく、通信システム間の干渉が発生しにくいといったメリットもある。くわえて、通信を妨害したり、傍受したりすることが技術的に難しいことから、秘匿性の高い通信ができるなど、その恩恵は計り知れない。
ちなみにJAXAは、かつて2005年に打ち上げた光衛星間通信実験衛星「きらり」(OICETS)を使い、欧州宇宙機関(ESA)の先端型データ中継技術衛星「アルテミス(ARTEMIS)」との間で光通信の実証実験を実施しており、LUCASはその成果を足がかりにして開発された。
光データ中継衛星は、「こだま」の後継機として、ALOS-3などの実用衛星からの実際のデータ中継を担うとともに、「きらり」の成果をさらに先へ推し進め、光通信を使った衛星のデータ中継という新しい技術の実証を行うことを使命としているのである。