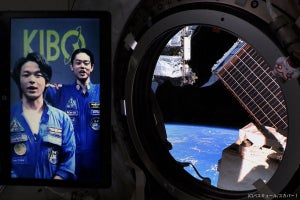「結婚式を挙げた場所を宇宙から見たい」、「自分の部屋で『今の宇宙』の星々に包まれたい」、こんな願いが数年後に実現するかもしれない。
より鮮明に、より頻度高く。人工衛星はひたすら「道具」としての「機能」を追い求めてきた。ところがまったく別のベクトルをもつ衛星プロジェクトが今、注目を集めている。ソニー、東京大学(東大)、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が取り組む「宇宙エンタメ・サット(衛星)」(仮称)だ。
コンセプトは「宇宙を解放する」。
今まで、宇宙から地球を見る体験は宇宙飛行士だけの特権だった。地球の人口は約78億人ほどだが、その中の約600人。また地球の撮影を行う観測衛星などのオペレーションは専門家だけに許されていた。ところが「宇宙エンタメ・サット」はその常識を打ち破る。衛星に搭載されたカメラを自由に操作できるチャンスが一般の私たちに開かれ、遠い宇宙の星々や地球の姿を自ら撮影できる。あたかも宇宙にいる宇宙飛行士のようなリアリティある視点や体験が得られるというのだ。
どこからそんな発想が生まれたのか、どうやって実現するのか。ソニー、JAXAのキーパーソンに聞いた。
きっかけは3年前の勉強会
このプロジェクトが生まれたきっかけは?
「ソニーは多趣味で好きなことを楽しんでいる人が多く、仕事後の部活のような感じでセミナーをほぼ毎日のように開催し、情報交換やアイデア出しをしています。3年前の2017年6月末、JAXAや内閣府の方に来て頂いて、『宇宙って今こういう拡がりがあるよ』とか『民間がどんどん参入してますよ』とソニーのメンバー100人ぐらいにお話頂いたんです。それから『宇宙で何かできないか』とブレストが始まりました」(ソニー事業開発プラットフォーム新規事業化推進部門宇宙エンタテインメント準備室 中西吉洋さん)
-

Sony Space Entertainment Projectの事業開発リーダー中西吉洋さん。現業はスポーツエンタテインメント部でテニスラケットにセンサーを付けたり、テニスコートにカメラを設置したり、新たな分野での事業の立ち上げに積極的に携わっている
ブレストの結果なぜ、エンタメ衛星に?
「ソニーがやるならゲームとかカメラがあるよねなど色々なアイデアを出しあう中で、『宇宙飛行士になりたかった』とか、『やっぱり宇宙に行きたい』という夢を語る人もいました。けど、いきなり宇宙には行けないから、カメラを乗せた衛星を打ち上げて、自分が宇宙にいるように地球や星を撮ろうという方向に決まっていきました」
その後、プロジェクト立ち上げのために中西さん達は企画書を手に、予算化や人集めに駆けずり回る。そして今、「Sony Space Entertainment Project」は2022年の打ち上げを目指し、JAXAや東大と協力しながら衛星開発が着々と進められているという。いったいどんな衛星なのか?
ソニーの事業開発リーダーである中西さん、衛星開発リーダーである全真生さんが語ってくれた衛星の詳細は以下の通りだ。
- 衛星の大きさは?:超小型衛星(10cm角×3~12の範囲)
- どこを飛ぶ?:地球周回低軌道
- カメラは何台?:1台
- どんなカメラ?:ソニーのカメラシステムの中から“高感度に”撮れるもの
- 何が撮れる?:4K動画と静止画
- どんな操作ができる?:遠隔操作でズーム、パン、チルト、ロールが可能
- どのくらい小さいものまで見える?:グラウンドまで含めて学校がわかるぐらい
- どうやって撮影する?:タイマー(予約)撮影とリアルタイム撮影
- いつ打ち上げる?:2022年(目標)
衛星開発に関してソニーは経験がない。そこで最強のパートナーとタッグを組んだ。東大とJAXAだ。ソニーはイメージングやセンシングなどの技術を活用して衛星のミッション部(カメラ部分)の開発や全体のシステム構築を、東大は超小型衛星システムや超小型推進系の開発実績から衛星の基本機能(バス部)開発を担当。JAXAは技術力と多数の衛星やISS利用・運用経験をいかし事業・研究開発計画を支援する。
高感度なカメラで、見えなかったものを見る
-

ソニーの衛星開発リーダー全真生さん。過去にTV向けLSIの設計、モバイル向けのイメージセンサーの開発を行うなど半導体設計に従事。現在はTV向けのシステムエンジニアとしてモデル開発を行う。取材当日、今後の放射線試験に備え放射線従事者になるための特殊健康診断を受けてきたそう
衛星に搭載されるソニー製カメラの特徴はなにか。「今回は感度を優先したカメラを選定した」(全さん)。
その理由は?
「宇宙飛行士や宇宙関係者の皆さんに話を聞くと、地球低軌道を飛行する衛星やISS(国際宇宙ステーション)の場合、1周約90分のうち半分は夜だと。(観測衛星は主に地球の昼間の写真を撮るので)半分の時間は撮れないことになる。それなら撮れなかったものを撮りたい、見えなかったものを見たい。たとえば地球の夜景やオーロラ。衛星の向きを変えれば、遠い宇宙の星々もきれいに撮れるだろうと」(中西さん)
そもそもこの衛星の狙いは、「宇宙飛行士の視点で地球や宇宙を見る」ことだった。ISS滞在中の宇宙飛行士たちは、日々Twitterで宇宙から撮影した地球(夜景も含め)の写真を投稿している。ところが「実はISSの窓はほとんど地球側についていて、宇宙側には窓がない。星空を撮影するのが難しいと油井亀美也飛行士も言ってました。地球も宇宙も撮影できるのが、この衛星の特徴だと思います」と、JAXA新事業促進部J-SPARCプロデューサーの藤平耕一さんは「エンタメ・サット」の特徴をそう語る。
そうなのだ。私は油井飛行士に取材し、2019年に「星宙の飛行士」という書籍を共著で出版させて頂いた。油井飛行士は子供のころ天文学者になりたかった自称・天文オタクであり、宇宙から見る星空を撮影するのをとても楽しみにしていた。ところがISSは地球観測がその目的の1つにあり、ほとんどの窓は地球を向いていたと残念そうに語られた。それでも油井飛行士はISS中の窓を調べ、時にはロシア居住棟の個室に入らせてもらうなど苦労して星空の撮影を行ったのだ。
さらに夜景の撮影は難易度が高いとも聞いた。ISSは秒速約7.8km、東京-大阪を約1分で飛ぶほどの超高速で飛行している。街明かりがぶれないように夜景を撮るには高度なテクニックが必要だ。ISSの動きに合わせて約1秒間流し撮りに挑戦するも、「画像を拡大しても光がぼやけないように撮れるまでに数か月を要した」と話して下さった。
宇宙飛行士が練習することでテクニックを磨き、ようやく撮れる地球の夜景や真っ暗な海の映像を、ソニーのテクノロジーを駆使して衛星で撮ることができないか。ソニー製の感度の高いカメラシステムを使えば、「速いシャッタースピードで撮影できるので、ぶれが少なくなるだろう」と中西さんは言う。さらに「衛星自体を動かしたり、画像処理を加えたりなどさまざまな手段を駆使して最終的にぶれが少ない作品にできるよう頑張りたい」。テクノロジーの力で、どこまで鮮明な写真が撮れるのか注目だ。
そしてISSではなかなか撮影できない天の川や深宇宙の天体についても、高感度カメラ×大気のない宇宙空間での撮影で星空に包まれるような映像を得られることが期待される。もちろん、地球を撮りたいというリクエストもあるだろう。自分の住む街、家、子どもたちなら自分が通う学校を見たいと思うかもしれない。「グラウンドまで含めて『これがうちの小学校』とわかるぐらいの分解能をめざします」(全さん)
どうやって撮る? 撮影方法は2種類
「エンタメ・サット」の売りの1つは「感度が高く、夜景や星も写せること」。そしてもう1つの売りが「誰でも自由に撮影できること」。これが「宇宙を解放する」と謳う所以だ。アーティストやクリエイター、企業、子どもたちも含め、将来的にさまざまな人たちのニーズに幅広く答えたいという。
撮り方は2通り。1つは衛星が今まさに見ている映像をリアルタイムで撮影する方法。「撮影コマンドを送信してから実際の撮影まで少しタイムラグがあるかもしれませんが、衛星画像を活用したシミュレーターを開発して直観的に操作できるユーザ体験が作れればと考えています」(全さん)。もう1つは、タイマー(予約)撮影。「この日」「この場所を」「こういうふうに」撮りたいと事前に設定して撮影をリクエストする方法だ。
誰でも操作できるとなれば、さまざまなオーダーが来るだろう。「とにかくオーロラが撮りたい」人、シャッタースピードや画角など細部までこだわるプロのカメラマン、「想い出の場所を晴れた日に綺麗に撮りたい」人、「曇っていてもいいから早く撮ってみたい」人など。
「自分自身が宇宙に行って本当にカメラをいじって操作できるようにして、なるべく自由に撮らせてあげたいです」全さんはいう。「たとえ上手く撮影できなくても、それも含めて面白いと思って頂ければ」と。
具体的にどんな操作で撮るのだろう。実は操作のインタフェースも検討中だ。「カメラを構えて撮るようにするのか、スマホのような操作なのか、パソコンのマウスなのか。映像の表示もスマホか、テレビかヘッドマウントディスプレイか、大きな空間に大画面でドーンと見せるのか。見せ方もいろいろありますね」(中西さん)。カメラによる撮影の設定だけでなく、操作インタフェース、映像の表示方法まで組み合わせもさまざまな可能性が広がる。
課題もある。搭載予定のカメラは4Kの動画も撮影できるが、ボトルネックとなるのは通信時間。地上へのダウンロードに時間がかかり、その間は新しい撮影ができなくなってしまうのだ。宇宙のリアルタイム動画をアーティストとオーディエンスが共に楽しむ「宇宙フェス」などのアイデアもあるが、実現には通信が鍵を握ると言えるかもしれない。
「(撮影枠や通信など)リソースが限られる中、どうアウトプットを最大化するか。一部の人が独占するよりいろいろな人に使ってもらうことを将来的には目指したい。ただし、いきなり『宇宙エンタテイメントをやります』と言っても一般の方々にはイメージがわかないと思うので、まずは表現力をもったアーティストさんや、宇宙にチャレンジしたいパートナー企業さんと組んで作品を作ってもらう。その後、より多くの人に機会を広げていくことになるでしょう」(中西さん)
CMやドキュメンタリ製作、科学館での映像展示などさまざまな利用が考えられる。現在、ソニーは新たな事業を共に作るクリエイターやビジネスパートナーを募集中だ。8月にプロジェクトを発表後、すでに数十件の問い合わせが寄せられたという。「メディア関係など多種多様な方から問い合わせを頂き、打ち合わせを始めています。どこの会社にも宇宙好きの方が中期事業計画に宇宙を入れておられて『何とかしたい』と連絡を下さったり(笑)」
もちろんソニーグループはミュージックチームやプレステなどのゲーム部門、スパイダーマンなどの映画を手掛ける映画部門などエンタメに精通したプロ集団である。宇宙という素材を使ってどんなエンタテイメントができるか議論中だという。
自らねじを回して小型衛星を製造した経験があるJAXA藤平氏は「今まで誰でも操作できる衛星なんて存在しなかったし、訓練された人が運用室で操作してデータを天気予報に回していた。JAXAの中でも衛星運用はセキュリティレベルが高い。その意味でこのプロジェクトはまさに『宇宙を解放する』。誰が操作しても壊れず使いやすくなければならない。今までの衛星は正確に動かすことが第一目的で、使いやすさは考えてなかった。幅をもった利用シーンを考える衛星自体初めて。さまざまな面で画期的です」と期待を隠さない。
目指すのは新たな価値を作ること
より多くの人がエンタメ・サットのカメラを駆使してあたかも宇宙にいるかのような宇宙の視点を得る-これはプロジェクトの第一歩に過ぎないという。「ソニーは衛星開発に初めて携わりますし、カメラを自由に操作して撮影するのは世界初。さまざまなことにチャレンジしうまくいったところ、いかなかったところをノウハウとして蓄積して次につなげたい」(中西さん)
次とは?「まずはどのくらい写せるのか。足りないのは解像度かズーム機能なのか、または撮った映像ではなく、それを届ける地上側の仕組みが大事なのか。考えながら2号機に繋げていけたら」
その先に何を狙うのか。「まずは宇宙から地球や遠い宇宙を見てもらう。地球を眺めることで湧き上がる気持ちってあると思うんです。宇宙飛行士が言われるように『地球って儚いよね』と気づいたらゴミを捨てるのをやめようと思うかもしれないし、『海ってこんなに綺麗なんだ』と気づいたらマイクロプラスチックの海洋汚染問題に関心が向くかもしれない。あるいいは「国境が見えないのに戦争をしている場合じゃないよね」とか。単に宇宙の果てまで行きたいというワクワクを感じてくれるだけでもいい。なにか新しい視点や気づきが生まれるようなことが僕らの手段でできたら」(中西さん)
「道具」としての宇宙利用から「楽しみ」としての宇宙利用へ。衛星バス部の開発を担当する東大チームのキーパーソンであり3年前から深く関わる小泉宏之 准教授は「宇宙利用は20年ごとに転換期を迎えてきた。1960年~80年代は米ソが宇宙開発のパイオニアとして活躍した時代。80年代からはさまざまな国が参加し、2000年からは民間利用が進められた。次の20年はエンタメだと思う。一般の人々が次の20年を作るのです」と語る。
2022年の打ち上げ目標まで時間はそれほど残されていない。現在、カメラとレンズ部分やそれらを納める筐体設計中。年末にはミッション部が形になり東大が開発するバス部と合わせて試験を繰り返していくことになる。「宇宙を解放する」新しい発想のエンタメ・サットの実現まで注目していきたい。
Sony Space Entertainment Project のコンセプトビデオ
Sony Space Entertainment Project コンセプトビデオ【ソニー公式】