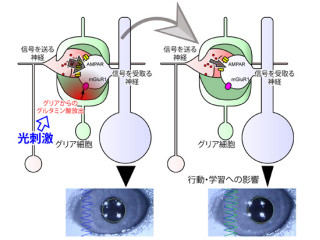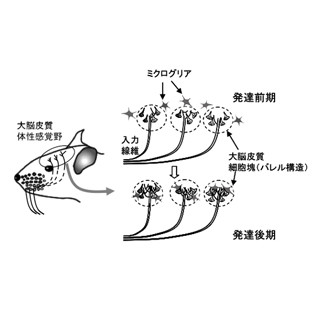東京大学は、マウスを用いた実験的脳傷害モデルを用いてタンパク質「プログラニュリン」の炎症反応における役割を調べたところ、同タンパク質は脳傷害部位に集積する「活性化ミクログリア」に発現し、ミクログリア自身の過剰な活性化を抑制して炎症反応を軽減することを明らかにしたと発表した。
成果は、東大大学院 農学生命科学研究科 獣医学専攻 博士課程の田中良法(日本学術振興会 特別研究員)、同・松脇貴志 助教、 同・山内啓太郎准 教授、同・西原眞杉 教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、2012年12月28日付けで「Neuroscience」オンライン版に掲載された。
プログラニュリンは細胞の増殖や腫瘍の形成、創傷の治癒などに関与することが知られているタンパク質だ。これまで研究グループは、プログラニュリンの脳における発現が性ホルモンである「エストロゲン」により促進され、新生子の脳の性分化や成熟動物における神経新生に関与することを見出してきた。
近年、プログラニュリン遺伝子の変異による「ハプロ不全」が、記憶障害は軽度であるが意欲低下や攻撃性向の増大などの人格変化を示す認知症の1種の「前頭側頭葉変性症」の一因であることが報告され、またアルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経変性疾患の発症リスクを高めることも示唆されている。
さらに最近、変異型プログラニュリン遺伝子のホモ接合により「神経セロイドリポフスチン症」が発症することも報告された。これらのことは、プログラニュリンが神経変性を防ぐ作用、すなわち神経保護作用を持つことを示唆しているが、その仕組みは明らかになっていない。
そこで研究グループは今回、マウスの大脳皮質にステンレス針を刺入するという実験的な脳傷害モデルを用いて、その後の回復過程を調べた。その結果、コントロールの野生型マウスでは傷害後にタンパク質「CD68」を発現する活性化ミクログリアが増え、このミクログリアがプログラニュリンを発現していることが判明したのである。
研究グループが作成したプログラニュリンの遺伝子を欠損するマウスを用いて同様の実験を行うと、野生型マウスよりもCD68を発現する活性化ミクログリアが傷害部位により多く集積すると共に、酸化ストレスの指標となる「カルボニル化タンパク質」の蓄積や血管新生の指標となる「ラミニン」の免疫反応性が増大していることが明らかとなった(画像)。
さらに、プログラニュリン欠損マウスではミクログリアの作用発現に関与するサイトカインである「TGFβ1」の産生が上昇すると共に、「アストロサイト」においてTGFβ1の細胞内情報伝達を仲介する「Smad3」のリン酸化も亢進していたのである。
なお画像は、実験的脳傷害モデルにおけるCD68陽性の活性化ミクログリア(上)とラミニン(下)の免疫染色像。野生型マウス(左)と比べて、プログラニュリン欠損マウス(右)ではミクログリアの過剰な活性化が起こると共に、血管新生などの炎症反応が亢進している。
以上の結果より、脳に傷害が起こった時に傷害部位に集まる活性化ミクログリアでプログラニュリンが産生され、このプログラニュリンがミクログリア自身の過剰な活性化やTGFβ1シグナルを抑制することにより、酸化ストレスや血管のリモデリング、「アストログリオーシス」などの炎症反応を制御していることが示唆された。
プログラニュリンはこのような炎症抑制作用を通して神経保護作用を発揮していることが明らかとなり、またプログラニュリンの持つこのような神経保護作用が神経変性疾患を抑制する1つの機序となっていることが考えられたのである。
今回の研究により、プログラニュリンは脳傷害部位に集積する活性化ミクログリアに発現し、ミクログリア自身の過剰な活性化を抑制して炎症反応を軽減することが明らかになった。プログラニュリンの持つこのような神経保護作用が、神経変性の抑制にも関連している可能性が考えられると、研究グループはコメントしている。