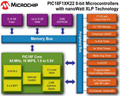初期のスイッチモード電源(SMPS)設計では、「電圧モード」動作と呼ばれる標準的な制御方式が使用されていました。これは、ランプジェネレータで電圧コンパレータの一方の入力を駆動し、エラーアンプ/ループフィルタからの誤差信号でもう一方の入力を駆動するというものです(図1)。この結果、電圧誤差信号のみに基づくPWMパルスが出力されます。この方法でも十分動作しますが、この回路には2つの基本的な制約があります。1つは回路の素子を保護する電流制限の機能がないこと、そしてもう1つは入力または出力の過渡応答が遅いことです。
電流モード制御
SMPS設計が成熟するにつれて、多くの設計者がより安全な「電流モード」制御と呼ばれるシステムに移行するようになりました。このシステムではランプジェネレータの代わりに、インダクタ電流によって駆動される電流帰還信号を使用します。このシステムでは、インダクタのピーク電流が誤差信号によって直接制御されるため、過電流による回路障害のおそれがありません(図2)。電流モード制御ではインダクタ電流を管理するので、制御ループから「ポール(インダクタによる遅延)」がなくなり、システムの過渡応答も改善します。
スロープ補償の重要性
一般に、アナログの電流モードPWMコントローラには、ピーク電流しか測定できないという問題があります。実際には平均電流を出力コンデンサで積分して目的の出力電圧を得ているので、測定しなければならないのは平均電流です。通常、平均電流は近似によりピーク電流の1/2として求められます。デューティサイクルが50%より小さければ、インダクタ電流は次のPWMサイクルの開始までに0になります。PWMサイクルの終わりまでにインダクタ電流が0になれば、平均電流はインダクタ電流のピーク値の1/2と等しくなります(図3)。
通常はこの設計で正常に動作しますが、デューティサイクルが50%を上回るといくつかの問題が発生する場合があります。まず第1に、平均電流がピーク電流の約1/2を上回るようになります(図4)。
PWMデューティサイクルが50%を超えると、平均電流はピーク電流の測定値から推定される値よりも大きくなります。この結果、出力電圧は目的の値を超えて上昇を続けます。これは、電圧制御ループの遅れによって電流セットポイントが再調整されるまで継続します。電流セットポイントが再調整されると、出力電圧は目的のレベル未満にまで下降し、以後、低調波発振と呼ばれるこの現象が繰り返されます。
電流モードでのこの発振を解消するために、アナログの電流モードコントローラには「スロープ補償」と呼ばれる手法があります。電圧エラーアンプによって生成される電流スレッショルドに右下がりのランプ波電圧(図5)を加えると、電流制限コンパレータの電流スレッショルドは、平均インダクタ電流に対してより忠実に追従するようになります。