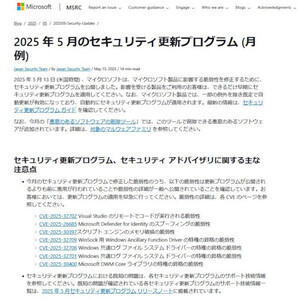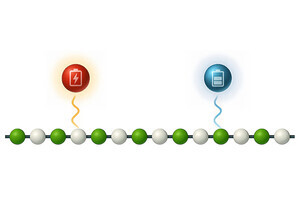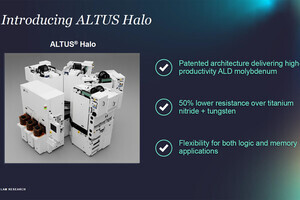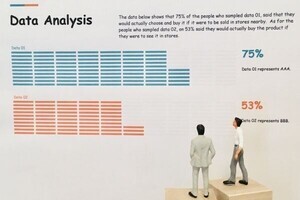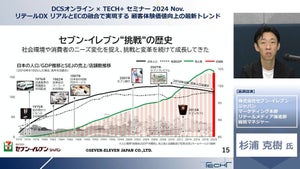可能性が増えるほどに冒険しなくなる
セッションも中盤に入り、國領氏が問いかける。「実は、人間って自由を生かして能動的なことをできるほど自立的ではなかったのではないか」と。ネットから流出する情報にたやすく影響を受けるなど、人間の心の弱さについて言及。たとえば音楽でも、特定の数曲に人気が集中することが目立つとし、「可能性が増えるほどにみんなが同じものを求めたり、冒険しない傾向がある気がしてならない」と述べた。
「IT化やデジタル化が進み、音楽、出版、映画すべてがダウンサイジング化している」。宮台氏の答えは、國領氏に同調するものだった。ローコストを追求した結果、すそ野が広がり、誰でもメディアに参加できるようになった。「その結果、音楽や映画についての話題が人々の日常会話から消えた」とも付け加える。
お茶の間で家族みんなが揃い、音楽番組やクイズ番組を見る時代はとうに過ぎた。テレビもすでに国民的メディアの座を降りている。宮台氏は「メディアの悪影響も、暴力やセックスをどう表現するかよりも、情報の受け手側がどういうコミュニケーションをするかに依存している」とする。神成氏も「たとえば、名工の功績を讃えるだけの番組を作るのではなく、その現場に眼を向けてどう発展させるかが重要。IT業界もそういう視点を忘れている」と注文をつけた。
自ら手を動かし、その先で人をどのように動かせるかを具現化するため、ヒントとなるのは日本が培ってきた「ものづくり」の文化だ。「工場内の一人ひとりは無力感を感じてしまいそうな状況でも、問題を全体へブレイクダウンし、みんなが影響力を発揮できるようにする。そうやってイノベーションを引き出すという工夫があった」と、國領氏は先人の知恵を評価する。
 |
チャットの様子 |
セッション中、会場のスクリーンには会場内外の人々が参加するチャットが映し出されていた。議論に対する疑問や意見を共有できる。また、パネラーが「いまあなたは無力感を感じているか」などの質問を提示し、投票を募った。
聴衆の意見がダイレクトに伝わるメリットの一方、会場内を巻きこんでの大論争といった盛り上がりには欠ける。そんな静かな雰囲気を察してか「わざと挑発的に」と前置きした上で、宮台氏が切り出した。「便利・快適・安全が大切だと思ってる人は、階級が低いと断言できる」
欧州のエリート教育には「真のエリートは失敗から学ばなければいけない」との固定観念があり、ネガティビティを吸収しなければ将来、名誉ある存在にはなれないというものだ。國領氏は「高齢社会の中で不安感が高ければ、安定を欲するという気持ちは分からないではない。安全や安心を捨て、大きなプレッシャーの中でエクストリームを提唱するのは難しい」と異論を唱えた。
エクストリームに対し寛容な社会を構築できるかについて、宮台氏は「基本的には価値観の問題」と総括する。ノイジーであるか否か、ダーティーであるか否か、複雑であるか否か。さまざまなバリエーションをどのように組み合わせるのが最適かを模索するしかないようだ。