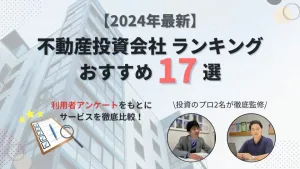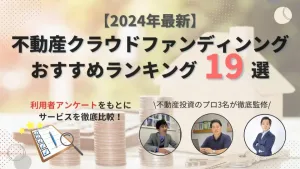土地活用として賃貸併用住宅の建築を検討していて、「建築費用はいくらかかるのか」「建築費用を抑えることはできるのか」という疑問を持っている方も多いと思います。
賃貸経営を成功させるためには、事前に建築費用を把握しておくことが大切です。
本記事では、構造ごとの建築費用の相場や、建築費以外で用意が必要な費用、建築費用を節約するためのポイントについて解説します。
賃貸併用住宅を建てるメリットやデメリット、建築の手順についても説明しているので、賃貸併用住宅の建築による土地活用の基礎知識としてお役立てください。
\年間10万人が利用するサービスで無料診断/
イエウールでプランを見る
賃貸併用住宅の構造ごとの建築にかかる費用

賃貸経営住宅の建築構造は、木、軽量鉄骨、重量鉄骨、鉄筋コンクリートの中のどれかか選ばれるケースが多いです。建築メーカーによっても坪単価は異なりますが、建築費は構造によって大きく変動します。構造別の坪単価は、以下をご覧ください。
| 構造 | 坪単価 |
|---|---|
| 木造 | 70~100万円/坪 |
| 軽量鉄骨造 | 80~120万円/坪 |
| 重量鉄骨造 | 90~130万円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造 | 100~140万円/坪 |
木は構造の中でも坪単価が安くて加工しやすいのが特徴ですが、耐久性が低いので将来的に修繕費の負担が大きくなる可能性があります。2階建てくらいの建物に適している構造です。
鉄骨には重量鉄骨と軽量鉄骨の2種類があり、軽量は2~3階建て、重量は3~5階建てくらいの建物に適しています。一般的に厚みが6㎜以上だと重量鉄骨、6㎜以下だと軽量鉄骨に分類されます。厚みのある重量鉄骨の方が強度が高いのが特徴です。
鉄筋コンクリートは5階建て以上の建物に向いていて、マンション建築によく使用されます。鉄筋とコンクリートがそれぞれの弱点を補い合うことで強度を高めています。コンクリートを流し込む工程が必要になるので、構造の中でもコストが高くなりやすいです。
投資の専門家監修記事!信頼できるおすすめの不動産投資会社ランキング
「【2024年最新】おすすめ不動産投資会社ランキング17選!各会社の口コミ・悪質な投資会社の見極め方も徹底解説」
「不動産投資に興味があるけど、どの会社を選べば良いか分からない」「悪質な不動産投資会社に騙されたくない」という人に向けて、不動産投資会社17社を利用した人の満足度を基に、おすすめの投資会社をランキングで紹介!
さらに、投資専門家に聞いた信頼できる投資会社の選び方や、投資額10億円の投資家インタビューも紹介しているので、ぜひご覧ください。
建築費以外に賃貸併用住宅でかかる費用

賃貸併用住宅を建てるためにかかる費用は建築費だけではありません。以下のような諸費用も必要となります。
- 初期費用
- 管理委託手数料
- 固定資産税
- 修繕費
建築費以外にかかる費用も忘れずにチェックしておきましょう。
初期費用
賃貸併用住宅を完成させるためには建築費以外の初期費用が必要となります。初期費用は建築費の5%くらいが目安だと考えてください。初期費用の内訳は、以下の通りです。
- 造成費
- コンクリート費
- 家具・家電の設備費
- 登記費用
- 印紙税
- 設計料
- ボーリング調査費用
- 地震・火災保険料
土地の造成工事がかかるのは田んぼや畑などの地盤が弱い土地に建築する場合や、土地に高低差がある場合です。造成工事にかかる費用は業者や土地の状態によって異なります。造成工事が必要ない土地の場合はボーリング調査費用もかからないので、初期費用を少なく抑える事が可能です。
土地の造成の基礎知識から費用について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をあわせて読んでみてください。
「土地の造成工事の基本とは?基礎知識や造成費用・節約のコツまで紹介!」
管理委託手数料
管理委託費用とは、賃貸物件の管理を管理会社に委託する場合に発生する費用のことです。自分ですべて管理する場合は発生しませんが、入居者の募集や設備点検、クレーム対応などの管理業務をすべて1人でこなすことになるので負担が重くなります。
賃貸オーナーが選択できる委託方法は管理委託方式とサブリース方式の2種類です。管理委託方式の場合は、オーナーが得る家賃収入のうち5~10%を手数料として支払います。サブリースよりも手数料は安いですが、空室の場合は家賃収入を得ることができません。
サブリース方式の場合は、家賃収入の15%~20%を手数料として支払います。管理委託方式より手数料は高めですが、空室がある場合でも安定した家賃収入を得ることが可能です。
固定資産税
固定資産税は毎年1月1日の時点で土地や建物などの固定資産を保有している人に課せられる税金です。不動産が市街化区域内にある場合は、都市計画税も課税されます。課税標準額に乗じる税率は1.4%が通常ですが、賃貸併用住宅の場合は戸数が2戸以上になるので軽減措置を受けることが可能です。
土地部分は戸数×200平方メートル以下までが小規模住宅用地になるので課税標準額が6分の1まで減額されます。200平方メートルを超える部分についても3分の1まで減額できます。
建物部分は、新築後3年間は固定資産税を半額に減額することが可能です。また3階建てや、準耐火構造、耐火構造の物件を建てた場合は5年間固定資産税が半額になります。
修繕費
修繕費は建築当初こそかかりませんが、入居者が退去するときや事故や災害が起こったとき、10年20年たって経年劣化が目立ってきたときに必要になってきます。空室対策のために設備を入れ替えたり、リフォームを行うときにも必要です。
入居者が退去した時の原状回復に必要な修繕費は20万円程度となっています。基本的には入居者の納めた敷金を使用しますが、経年劣化による変化はオーナーが負担しなければなりません。設備や機械の故障や雨漏りなど、突然修理が必要になった場合の修繕費として数十万円程度用意しておくと安心です。
入居者の満足度を高めるためのリフォームも、定期的に行うのであれば1回につき数十万円かかります。外壁や屋根の経年劣化による修繕費用が最も高いです。数十年に1度の大規模修繕に対応するために数百万円の資金を貯めておく必要があります。
投資初心者におすすめの記事!Amazonギフト券がもらえる不動産投資セミナー
「【2024年】Amazonギフト券(アマギフ)がもらえる人気の不動産投資セミナー10選|怪しい投資会社の見極め方も解説」
不動産投資セミナーは、不動産投資の基礎知識を得たり、優良な投資物件を紹介してもらえる利点がありますが、「セミナーに参加したら投資しないといけないの?」「営業がしつこくて怪しいのでは?」というイメージを抱いている人も多いのではないでしょうか。
上記の記事では、Amazonギフト券がもらえる不動産投資セミナーを10選紹介しています。セミナーや面談不要でアマギフがもらえる会社や、信頼性の高いセミナーを厳選しているので、ぜひご覧ください。
賃貸併用住宅の費用を減らすポイント

賃貸併用住宅は賃貸部分と住居部分の建築が必要になってくるため、一般的な賃貸物件と比べても建築費が高くなる傾向にあります。建築費を抑えるポイントは以下の通りです。
- 複数社へ見積もりを依頼する
- 住居部分を50%以上にして住宅ローンを組む
- 設備のランクを下げる
- 不動産取得税が安くなる広さにする
建築費は総工事費の中でも大きなウェイトを占めています。コストダウンの方法を詳しく見ていきましょう。
複数社へ見積もりを依頼する
全く同じ建物を建てる場合でも、建築を依頼するハウスメーカーや建築施工会社によって費用が異なります。最初から業者を絞って見積もりを依頼しても適正価格であるかを判断できないので、できるだけ複数の業者から建築プランや費用の提案を受けるようにしてください。
見積もりを比較することで建築費の相場がわかるようになります。複数の見積もりを取るのを嫌がったり、相場からかけ離れた金額を提示したりするのは悪徳業者の可能性が高いです。相場に近い金額を提案してくれた業者は信用できると判断しましょう。
\年間10万人が利用するサービスで無料診断/
土地活用は上場企業が運営する安心の『イエウール土地活用』がおすすめ!

イエウールでプランを見る
住居部分を50%以上にして住宅ローンを組む
賃貸物件を建てる場合は住宅ローンを利用することができません。賃貸物件はアパートローンや不動産投資ローンを組めば融資を受けることができますが、住宅ローンよりも金利が高いので総返済額が多くなるのがネックです。
しかし、賃貸併用住宅の場合は住宅ローンを利用することが可能です。多くの金融機関で住居部分の床面積が50%以上あることを要件としています。住宅ローンは金利が低くて長期で組むことができるので、毎月のローン返済額を最大限まで下げることが可能です。
さらに床面積が50平方メートル以上、住居部分が50%以上あれば、住宅ローン控除を適用させることができます。アパートローンでは控除を受けることができないため、節税も大きなメリットです。
賃貸併用住宅で住宅ローンを組む方法について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をあわせて読んでみてください。
「賃貸併用住宅は住宅ローンが組める!メリットから注意点まで徹底解説」
設備のランクを下げる
建物の建築に使用される材料費は、総工事費の10%にも及びます。もし、建材や設備にこだわりがないのであれば、ランクを下げることを検討してください。規格内の建材でも十分な性能を持っているので、多少グレードを落としても問題はありません。
自宅だけ豪華にしたい場合は、住居部分の建材や設備のランクを上げて、賃貸部分は規格内の部材にすることである程度建築コストを抑えることができます。できるだけシンプルな建材や設備を使用すれば、修繕費用も節約することが可能です。
不動産取得税が安くなる広さにする
個人が賃貸併用住宅を取得した場合は、不動産取得税が課せられます。不動産取得税は以下の計算式を用いて算出することが可能です。
不動産の取得時期や種類によって軽減措置が適用できます。賃貸併用住宅を新築する場合、賃貸部分を一戸あたり40平方メートル以上240平方メートル以下にすれば、課税標準額から1,200万円を控除できます。さらに、住宅を取得しているため税率を3%に軽減することが可能です。
1万円からお手軽に不動産投資!おすすめの不動産投資クラウドファンディング
「【投資専門家が監修】人気の不動産クラウドファンディングおすすめ19選比較|口コミ評判と実績・選び方も解説」
「不動産投資に興味があるけど、少額から手軽に始めたい」「不動産クラウドファンディングって本当に儲かるの?」という人に向けて、不動産クラウドファンディング19社を利用した人の満足度を基に、おすすめのサービスをランキングで紹介!
さらに、投資専門家に聞いた信頼できるサービスの選び方や、利回りが高いサービスも紹介しているので、ぜひご覧ください。
土地を賃貸併用住宅で活用するメリット

土地活用として賃貸併用住宅を建てるメリットは、以下の通りです。
- 家賃でローンが返せる
- 相続税対策になる
- 柔軟に活用できる
賃貸併用住宅を建築するメリットを詳しく確認していきましょう。
家賃でローンが返せる
賃貸部分が入居者で埋まれば、毎月決まった家賃収入を得ることができます。住宅ローンを組んだ場合は毎月返済が必要になるため、家賃収入をローンの返済に充てることが可能です。自己資金や給与収入を削って返済していく必要がありません。
貸せる部屋数が多くて満室に近い状態を維持できれば、安定して多くの収益を生み出すことができます。ローンを返し終わったら収益をすべて自分のものすることができるので、定年退職後のための資産形成として活用することが可能です。
相続税対策になる
建物は固定資産税評価額で相続税評価が行われます。賃貸併用住宅の場合は人に貸していることにより権利が制限されるので貸家として評価されます。貸家は自宅用の建物よりも相続税評価額を低くできるので相続税対策に有効です。
賃貸併用住宅を建築すると、相続人が支払う相続税を安くすることができます。建物の賃貸部分に評価減の特例を適用できるからです。さらに、小規模宅地等の特例を適用できる要件を満たしている場合は、最大330平方メートルの部分までの評価を50~80%軽減できます。
柔軟に活用できる
賃貸併用住宅を建てておけば、オーナーが亡くなった後も残された家族に不動産と賃貸経営を引き継ぐことができます。残された家族も、賃貸として活用し続けるか親族や子供世帯が住む家として、活用するかを選ぶことが可能です。親が介護施設に入居した場合は、住宅部分を賃貸として貸し出すこともできます。
賃貸併用住宅としてだけではなく、二世帯住宅や賃貸住宅としても活用できるので、家族構成やライフスタイルの変更に合わせて柔軟に活用法を変更できるのが魅力です。
土地を賃貸併用住宅で活用するデメリット

賃貸併用住宅にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。
- 空室リスク
- 売却が難しい
- プライバシーが保ちにくい
デメリットを把握して対策を考えておきましょう。
空室リスク
賃貸経営で最も考慮すべきなのが空室リスクです。貸す部屋がいくらあっても入居者がいなければ賃貸収入を得ることはできません。空室の期間が長くなればなるほど、赤字が続き経営が苦しくなっていきます。住宅ローンの返済を自己資金から捻出する状況になってしまいかねません。
貸せる部屋数が少ないほど空室リスクの影響は大きいです。空室リスクの軽減には、以下のような対策が有効となります。
- 集客力のある管理会社に任せる
- 競合物件の調査を行う
- 物件のメンテナンスを行う
空室対策の方法について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をあわせて読んでみてください。
「空室対策アイデアを7つ紹介!施策ごとのコスト・リスク・難易度を比較」
売却が難しい
賃貸併用住宅は自宅と賃貸物件を同時に探している人向きで需要が限られるため、一般的な賃貸物件と比べて売却しにくいというデメリットがあります。
売却したくてもすぐに買主が現れる可能性が低いので、売却完了までの期間が長くなりやすいのが難点です。
いつかは賃貸併用住宅を売却したいと考えている人は、買主へのアピールとして、設計の段階から仕様や設備にこだわって建築したり、常に満室の状態をキープすることをおすすめします。
プライバシーが保ちにくい
賃貸併用住宅では必然的に入居者と自宅の距離が近くなるため、プライバシーを守るのが難しいという問題があります。賃貸物件では音漏れやゴミの出し方などのトラブルが起こりやすいので、気を遣いながら生活しなければなりません。
プライバシーを守りたいなら、出入り口を完全に別にしたり、遮音性の高い建材を採用したりすることが有効です。近くに住んでいるとクレームも頻繁に受けやすくなるので、クレームやトラブル対応は管理会社に委託するなどの対策を実施しましょう。
賃貸併用住宅を建てる流れ

最後に賃貸併用住宅を建てる際の流れを確認していきましょう。建築の流れは以下の通りです。
- 建築会社を選ぶ
- 賃貸併用住宅のプランを決める
- 建築開始
- 入居者の募集
事前に賃貸併用住宅を建てるまでの流れを把握しておきましょう。
建築会社を選ぶ
まずは建築会社の選定を行います。賃貸併用住宅のモデルハウスや完成見学会に参加して、自分が建てたい家のイメージを膨らませてください。担当者との相性や案内係の接客態度も、建築会社選びの重要な要素となります。
建築費用の相場を把握するために、必ず複数の会社に見積もりを依頼して比較してください。建築費用だけで判断するのではなく、余計な項目がないかもチェックすることが大切です。
賃貸併用住宅のプランを決める
施工会社を決定したら、どのプランで建築を進めていくかを相談します。オーナーの自宅を上の階に設定したり、縦割りで分けたりすることができます。自身のライフスタイルに適した快適に暮らせるプランを選定してください。
単身者ならワンルーム、ファミリーなら1LDKなど、入居者のターゲットを絞ってニーズに合う間取りを決めることも大切です。
建築開始
具体的なプランが決まったら、施工会社と契約を結びます。住宅ローンを申し込む場合は金融機関に審査を依頼してください。審査に通ったらつなぎ融資か自己資金で着工金を支払いましょう。着工金の入金が確認されたら、建築がスタートします。建築期間は構造や階数によって異なりますが、大体3~6ヶ月程度です。
入居者の募集
建物が完成する3ヶ月前くらいから入居者の募集を開始します。管理会社に委託している場合は任せきりにして問題ありません。自分で入居者を集める場合は、インターネットを活用したり、チラシを作成したりして入居者を集めます。建物が完了したら、入居開始です。
まとめ

賃貸併用住宅は選ぶ構造によって建築費が変動します。坪単価だけを気にするのではなく、構造ごとのメリットやデメリット、建築に適している階数に注目して構造を選びましょう。
建物を完成させるためには建築費以外の費用もかかります。諸費用も総工事費に含まれることを覚えておきましょう。
また、自宅部分と賃貸部分の建築が必要になるので建築費用が高くなる傾向にあります。建築費用の出費を抑えるために、この記事で紹介したコストダウンの方法を実践してみてください。
※「マイナビニュース土地活用・不動産投資」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328_summary.PDF
・https://www.fsa.go.jp/news/r4/kokyakuhoni/20230120/kpi_toushin_230120.pdf
・https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
・https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001411696.pdf
・https://www.fsa.go.jp/
\年間10万人が利用するサービスで無料診断/
土地活用は上場企業が運営する『イエウール土地活用』がおすすめ!

イエウールでプランを見る
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。