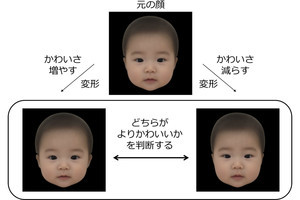大阪大学(阪大)と浜松医科大学は1月24日、幼児期のスクリーンタイム(ST)とその後の子どもの神経発達の関連を解析し、コミュニケーション機能の発達に弱いながらも影響があることを示した一方、子どもの頻繁な外遊びがスクリーンタイムの望ましくない影響を緩和することを明らかにしたと発表した。
同成果は、阪大大学院 連合小児発達学研究科の杉山美加大学院生、浜松医科大 子どものこころの発達研究センターの土屋賢治特任教授(阪大大学院 連合小児発達学研究科兼任)、同・西村倫子特任講師らを中心に、海外の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国医学会が刊行する小児医学を扱う学術誌「JAMA Pediatrics」に掲載された。
スクリーンタイムは、テレビやDVDなどの視聴に加え、スマートフォンやタブレットなどを見る1日あたりの平均デジタル視聴時間のことで、WHO(世界保健機関)は2歳児におけるSTは1時間を超えないよう指針を出しているが、コロナ禍によって在宅時間が伸びる中、米国では指針を遵守している家庭は3割程度と報告されているとする。
幼児のSTが長いことによる懸念の1つとして、神経発達学的予後(神経発達)がある。STが長いと、その後の言語機能、社会機能・対人機能(社会性)、運動機能の発達に望ましくない影響が生じたり、学業成績が低下したりする可能性があるのではないかというが指摘されている。ただし、STの影響を否定する研究結果もあるという。
加えて、ST問題の理解と対応においては、(1)幼児期の長いSTが、子どものどのような機能にどの程度影響するのかが確かでない、(2)幼児期のSTを減らす保健指導・介入がこれまでも行われてきたが成功していない、という2点の未解決の課題も残されていた。
幼児のSTを減らすべきかどうか、もし減らすべきなのであればその理由はどのようなものか、そして、どのように望ましくない影響を減らすとよいのか、それを考えるための科学的根拠が十分に集まっていない状況だという。
そこで研究チームは今回、浜松医科大が2007年からスタートさせ、現在も継続している大規模疫学研究「浜松母と子の出生コホート研究(HBC Study)」のデータを用いた調査を行うことにしたという。