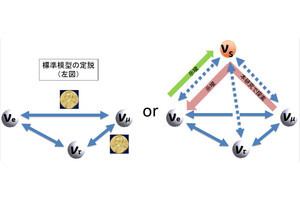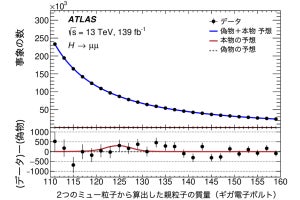岐阜大学、日本原子力研究開発機構(JAEA)、東北大、J-PARCセンター、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の5者は3月2日、「ストレンジクォーク」をふたつ持つ「グザイマイナス粒子」を含む超原子核「グザイ核」を新たに観測したと発表した。
同成果は、岐阜大 教育学部・工学研究科の仲澤和馬シニア教授、JAEA 先端基礎研究センターの早川修平博士研究員、東北大大学院 理学研究科の吉田純也助教、KEK 素粒子原子核研究所兼J-PARCセンター 素核ディビジョン ハドロンセクションの高橋俊行教授らをはじめとする、日・韓・米・中・独・ミャンマーの6国26大学・研究機関の総勢97名の研究者・大学院生からなる大型の国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する学術誌「Physical Review Letters」にオンライン掲載された。
我々が見て触れられるものは原子でできており、その原子は主に陽子と中性子と電子で構成される。電子はそれ以上分割できない最小単位と考えられているが、陽子と中性子はさらに分割することが可能だ。陽子は2個のアップクォークと1個のダウンクォークで構成され、中性子は2個のダウンクォークと1個のアップクォークで構成されている。つまり、我々が見て触れられるものの大半は、アップクォークとダウンクォークと電子でできているともいえるのだ。
クォークには本来、アップとダウン以外にも、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムがあるとされているが、アップとダウン以外の残りの4種類は陽子や中性子に含まれないため、我々が触れることはまずない。
ただし、陽子や中性子のようにクォーク3個からなる粒子は、陽子や中性子以外にもいくつか存在する。「ラムダ粒子」、「グザイマイナス粒子」、「グザイゼロ粒子」などだ。
ラムダ粒子やグザイ粒子に含まれるのがストレンジクォークで、グザイ粒子は2個の同クォークを有する。こうしたストレンジクォークを含む粒子は「ハイペロン」と総称され、「超原子核」とはそのハイペロンが入った原子核のことをいう。また、ラムダ粒子が入った原子核は「ラムダ核」、グザイ粒子が入った原子核は「グザイ核」と呼ばれる。なお、ハイペロンの寿命は短く、たとえばグザイ粒子の場合は、わずか100億分の1秒で崩壊してしまうことが確認されている。
こうした超原子核のうち、中でもグザイ核の研究は、中性子星を理解するうえでも重要とされる。グザイ粒子は、中性子星内部で発生する可能性のある粒子のひとつだからだ。
中性子星とは、太陽の8~9倍以上の質量を持つ大質量星が超新星爆発を起こしたあとに中心に残る天体のことだ(大質量星の質量などの条件によっては大質量星の中心核が重力崩壊を起こしてブラックホールとなる場合もある)。太陽と同程度の質量があるにもかかわらず、直径がわずか20km程度しかなく、極限まで圧縮された超高密度が特徴である。あまりにも密度が高い(重力が強い)ため、陽子が電子を吸収して中性子にならないと存在できないほどで、天体の大部分はその名称の通りに中性子で構成されていると考えられている。
中性子星の質量の上限値、半径、内部の密度や圧力といった性質を理解するには、その内部において、どのような条件下でどのような粒子が発生するのかを考える必要があるという。グザイ粒子の発生条件は陽子や中性子との間に働く力の強さに依存することから、その大きさを地上実験によって決めることが必要で、グザイ核の実験データの充実は長く望まれていたという。
グザイ粒子と原子核の間に働く力は「強い相互作用」と呼ばれる。これまでの実験から、それ引力であることが示唆されていたが、それが実際に引力であることを2015年に明らかにしたのが、仲澤シニア教授が率いる研究チームだった。このときはKEKの12GeV陽子シンクロトロンを用いた実験であり、このことは「木曽イベント」と呼ばれている。
しかしこの木曽イベントでは、グザイ核が崩壊した際の娘核が基底状態だったのか励起状態だったのかを確定できなかったという。そのため、質量を一意に決められず、グザイ粒子と原子核に働く強い相互作用の大きさを精度よく決定できなかったという。
グザイ核事象は非常に希な事象であるため、質量を一意に決め、さらにグザイ粒子に働く強い相互作用の詳細を知るには、より多くのグザイ核を観測する必要がある。そこで国際共同研究チームは今回、大強度ビームを利用できるJ-PARCにおいて、新たに開発された技術を用いて従来の10倍の事象観測を目指した実験を行ったのである。
今回の実験では、J-PARCの加速器ビームで作られる大強度・高純度の負電荷のK中間子ビームをダイヤモンド標的中の陽子と反応させることで、グザイマイナス粒子の大量生成が行われた(グザイマイナス粒子と同時に正電荷のK中間子も生成される)。それを総計1500枚の特殊な写真乾板に入射させてグザイ核事象の記録が行われたのである。その後に写真乾板が現像され、独自に開発された光学顕微鏡システムでグザイ核事象の探索が実施された。
探索を効率よく行うため、グザイマイナス粒子の生成反応を写真乾板の前後に設置された検出器群によって同定し、さらにグザイマイナス粒子が写真乾板へ入射する際の位置に関する測定データを用いたうえで、写真乾板内の探索が行われた。そして探索の結果、ある写真乾板に記録された飛跡がグザイマイナス粒子と窒素14原子核とが束縛した状態の痕跡と確認されたのである。
-

写真乾板中で今回観測されたグザイ核事象(伊吹イベント)の顕微鏡画像。グザイマイナス粒子がA点で窒素14原子核に吸収されグザイ核を形成し、ベリリウム10ラムダ核(#1)とヘリウム5ラムダ核(#2)に崩壊した。ベリリウム10ラムダ核は、B点でいくつかの原子核(#3から#6)といくつかの中性子(電荷を持っていないので飛跡は残らない)に崩壊し、ヘリウム6ラムダ核はC点でヘリウム4原子核(#7)、パイマイナス粒子(#8)と陽子(#9)に崩壊した (出所:共同プレスリリースPDF)
グザイマイナス粒子が写真乾板中の原子核に吸収され、ふたつのラムダ核(ベリリウム10ラムダ核とヘリウム5ラムダ核)に崩壊した事象であること、グザイマイナス粒子と窒素14原子核との間に働く力(束縛エネルギー)は1.27±0.21MeVであると一意に決定することに成功したのである。この値は世界最高クラスの精度だという。
グザイマイナス粒子は、負電荷を持つ電子と同じように正電荷を持つ原子核とクーロン力で束縛状態を作るが、働く力がクーロン力のみであれば束縛エネルギーは0.39MeVにしかならないという。しかし今回観測された事象は、クーロン力に加えて、原子核と強い相互作用による引力によってさらに強く束縛したグザイ核状態を形成したあとに崩壊したもので、今回の結果から強い相互作用による引力の大きさもわかるとしている。
なお今回の崩壊は、グザイマイナス粒子が原子核中の陽子と反応してふたつのラムダ粒子へ変換する反応で起きるが、この変換反応が強いとグザイマイナス粒子が原子核内に入ってグザイ核状態を形成する前に壊れてしまうため、変換反応の強さは弱いということも示唆されるという。
グザイマイナス粒子と原子核の間に働く力、またそのもととなるグザイ粒子と陽子・中性子との間に働く力や変換を引き起こす強い相互作用は、原子核の成り立ちや天体サイズの原子核ともいえる中性子星の内部の状態を理解するうえで重要であり、今回の研究で強い相互作用の新たな知見が得られたとしている。
またこれまでグザイ核事象は数例しか観測例がなく、新たに発見された場合、発見に貢献した研究機関や発見者に縁のある地名にちなんで命名することが研究チームの慣例となっているという。そこで今回の事象は、仲澤シニア教授が所属し、顕微鏡を用いた探索を主導する岐阜大学が位置する岐阜県・伊吹山にちなみ、「伊吹イベント」と命名された。
グザイマイナス粒子に働く力を精密に測定した今回の研究は、物質を構成する素粒子クォークから物質が形成される仕組みの理解に繋がる成果になるとともに、中性子星の内部構造の解明に一歩迫る成果となるという。
さらに国際共同研究チームは現在、「全面探査法」と命名された新たなグザイ核の探索法を開発中だ。これにより現状の検出器群で同定できないグザイマイナス粒子によって生成されるグザイ核の観測が可能となり、同手法によるグザイ核事象の観測数は今回のさらに10倍(過去実験の100倍)になると見積もられている。多くのグザイ核事象を観測することで、数多くの種類があり、そしてさまざまなエネルギー状態もあるグザイ核を系統的に測定し、同粒子の強い相互作用の詳細を明らかにするとしている。