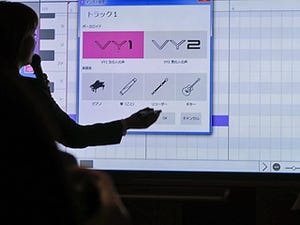さて、白石先生の授業風景に戻ろう。数学といえば、先生が黒板に図や式を書き、それを生徒たちがノートに書き写す“スクール形式”の授業をイメージする。ところが、白石先生は授業の後半、生徒たちをグループ分けして出題をした。各グループ内で生徒たちが協力しあって問題を解くという寸法だ。文科省は“思考力”“判断力”“表現力”を育てるような授業を推進しているが、“協働性”についても重要視している。
このグループワークは、数学の授業とは思えないほど、生徒たちが生き生きしていた。それぞれiPadの画面を見せ合ったり、ClassRoomで画面を送受信したりしているのか、課題を共有した“学び”を楽しんでいた。印象的だったのは、終業のチャイムが鳴ったとき。すでに課題を解いていたグループは談笑していたが、“解”にたどりついていないグループは、なんとか解こうとがんばっていた。だが、無情にもチャイムは鳴る。
「えぇー!」「ウソ!?」といった声が、各グループからあがった。これこそ、授業に集中していた、いや、授業を楽しんでいた証拠といえよう。近年、アクティブ・ラーニングの重要性が高まっているが、“能動的に学ぶ”というのが基本。まさに、その現場をみた気がした。
AI英会話アプリの試験導入も検討
さて、この品川女子学院に新しい動きがあった。それは、トークノートとジョイズが共催した「ICT教育の最前線事例に関する記者発表会」においてだ。これは、品川女子学院や聖徳学園、島根県・松江市、DeNAといった学校法人、自治体、企業などが、教育についての取り組みを紹介するというもの。
この席で品川女子学院は、AI英会話アプリ「TerraTalk」を試験導入するとリリースした。導入は夏休みに予定されているので実際の環境を拝見することはできなかったが、ICT教育に関して同校が積極的なのがわかる。ただ、TerraTalkの試験導入と、それまで取り組んできたiPadの導入は、若干性格が異なるかなと感じた。
前者は、英語を学ぶという目的が明確で、学力の純粋な向上を目指したものといえる。一方、後者は社会に出たときに、デジタルデバイスを柔軟に扱えるような素養を身につけさせるのが主目的なのかなと感じた。いずれにせよ、ICT教育に対する同校の積極さが、伝わってきたことは確かだ。