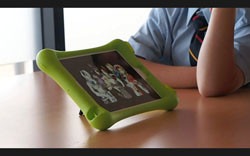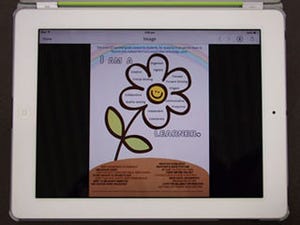Whyを常に問う
キャンパスを案内しながらも、こまめに生徒に声をかける萩原氏。テクノロジーを活用しながらエンゲージメントを高めることを目指していく中で、テクノロジーがいかに生徒の学ぶ楽しさを効果的にサポートするか、というテーマについて向き合っている。
学びへの生徒の積極性や関与の度合いを測る方法について教えてくれた。それは、「Whyを常に問う」ということだった。
授業中や、オープンスペースで何かしている生徒がいたときに、「何をしているの?」という質問には、誰でも答えられるはずだ。しかし、「なぜ、それをしているの?」という問いかけに対してどのように答えるだろうか。
この「なぜしているか」という問いに対して、例えば「授業の課題が出たから、○○について調べている」という答えが返ってくると、それは普通のことかもしれない。しかし授業でやらなければならないから、という動機付けは、果たしてエンゲージメントが高い状態と言えるだろうか。
一方で、「こんな課題が出ていて、○○についてまとめたいから、調べている」という答えが返ってくると、前述の「授業の課題で……」とは違うことがわかる。課題は同じように出されているが、自分でまとめたい内容を決めて、そのゴールに向かって取り組んでいる、ということが現れている。
簡単な例ではあるが、常に「Why」を生徒に問いかけて、それに対して答えることによって、その生徒がいま何について学びを得ているのか、ということがわかるのだ。そのため授業では、生徒たちが自分で「Why」を説明できるように、自分でテーマやその意義を理解できるようにする事が必要になる。
テクノロジー活用にも同じ事が言えるだろう。
例えば、iPadには無料で利用できるプレゼンテーションソフト「Keynote」や、ビデオ編集を簡単に行える「iMovie」といったアプリが揃っている。しかしアプリがあるから、プレゼン発表を毎日させれば良いか、といわれるとそうではない。プレゼンもビデオ制作も、表現方法の1つとして生徒が選んで使えば良いということだ。
そのため、「プレゼンを作りなさい」「ビデオでまとめなさい」という課題を出すのではなく、最も上手く表現できる方法として生徒に選ばせるようにする。なぜその課題に取り組んでいるかが説明できるように、「なぜそのテクノロジーを使っているか」を生徒が説明できるように、指導していくことが重要だと実感した。