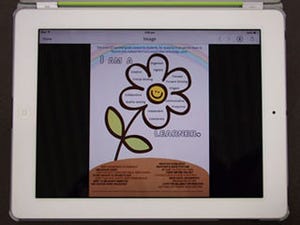テクノロジーの重要な役割と、当たり前という前提と
今回を含めて、3回にわたって、西オーストラリア・ロッキンガム市にある中高一貫校のコルベ・カソリック・カレッジの取材レポートをお届けしてきた。iPadを全員が持ち、授業だけでなく休み時間や家庭でも活用しながら学ぶその様子は、無理がなく、非常に自然な風景として受け入れることができた。
コルベでは、21世紀の学び方、つまり「Connected」が前提の学習を目指して、iPadを選び、生徒の生活、先生の教え方などを変革してきた。
その先頭に立って進めてきたのは萩原氏であるが、本人は「属人性というよりは、学校全体や教科、学年といった学校内にいくつもある『チーム』で成功を勝ち取ってきた、という側面が強みではないか」と指摘する。非常に優秀な1人、ではなくそこにいる人全員が前提を共有し、ITや教育のスキルを高めていかなければ、本当の意味での変革は生まれないし、おそらく筆者が目にした「iPadがある自然な風景」は作られなかっただろう。
生徒がテクノロジーを前提に、常に学び続ける環境を手に入れる。あるいは自分で学ぶべき課題を発見し、それを共有しながら学んでいく。そんな未来の学びが、まさにコルベで作り出され、実践されていた。今後も、学びの変革を止めない萩原氏の挑戦は、日本から遠く離れた南半球の地で、続く。

松村太郎(まつむらたろう)
ジャーナリスト・著者。米国カリフォルニア州バークレー在住。インターネット、雑誌等でモバイルを中心に、テクノロジーとワーク・ライフスタイルの関係性を追求している。慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、ビジネス・ブレークスルー大学講師、コードアカデミー高等学校スーパーバイザー・副校長。ウェブサイトはこちら / Twitter @taromatsumura