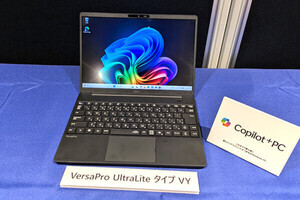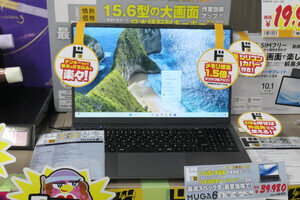インテルは11日、企業向けUltrabookの現状についての記者説明会を開催した。Ultrabookを企業で導入する際にポイントとなる機能メリットの解説にくわえ、実際の導入先担当者をゲストに迎えた最新事例の具体的紹介なども行われた。
説明会ではまず、「Ultrabookの最新の技術が、ユーザーの働き方を変革することができる」と話す、インテル グローバル・セールス&プラットフォーム・マーケティング事業本部 副本部長 兼 マーケティング統括部長 笠倉英知氏が、Ultrabookが企業用途で活用できる要因となる機能メリットの概要を説明した。
最新Ultrabookの特徴は、薄くて軽く、省電力つまり長時間バッテリ駆動と、さらに人前で使っても違和感の無いスタイリッシュデザインも含めた、モビリティ性の高さであるとする。そして本体を開いてすぐに起動する応答性の高さ、セキュリティ機能のサポートの充実もあるとする。これらは全て、企業ユーザーの利用シーンに幅広く最適な特徴であり、Ultrabookはコンシューマだけでなくビジネス用途でも最適なプラットフォームであり得るのだと紹介した。
直近で登場した新OSであるWindows 8についても触れ、ビジネスの現場ではタッチUIに対応したアプリケーションの増加と、その活用が増えてきているという印象を語る。Ultrabookにおいては、これまでのPCのように単にタッチパネルを組み込むだけでなく、製品のフォームファクタから、クラムシェルとタブレットの両方の形態を備えるコンバーチブル・モデルが登場しており、Ultrabookのビジネス向け導入のひろがりのフックになるだろうという期待を語った。
次いで、より具体的に、Ultrabookがビジネス用途で最適なプラットフォームであり得る機能メリットについて、同社のグローバル・セールス&プラットフォーム・マーケティング事業本部 セキュリティー&マネージャビリティー・テクノロジー 坂本尊志氏が紹介した。モビリティや処理性能部分のメリットはコンシューマにも共通のものだが、同氏の肩書きからもわかるように、Ultrabookの企業向け導入の際の最大の(タブレットなど他社主導の競合デバイスとの)優位性は、セキュリティ機能となる。
一時期は、ビジネスでのPCの外部持ち出しには、個人情報保護法以降、特にセキュリティリスクの観点から消極的な見方も強かったが、3.11の大震災以降は、事業の継続性に寄与できるというメリットも注目され、モビリティを活かしつつセキュリティリスクを減らし、クライアント端末単位で会社内外問わず業務遂行が可能な環境の構築が重要性を増している。
仕事の"しかた"を制限しないモビリティなどは重要だが、ただ、物理的に外に持ち出されたPCをどう保護するのかは非常に重要になると、同氏は説明する。そこで企業向けUltrabookで用意されているのが、PC内部のデータを保護するIntel AT(アンチセフト・テクノロジ)と、クラウドなど外部データとの連携を保護するIntel IPT(アイデンティティ・プロテクション・テクノロジ)の2つのセキュリティ機能だ。
ともにUltrabookのプラットフォームのハードウェアレベルでサポートする強固なセキュリティ機能で、Intel ATは、盗難・紛失に備え、内部データへのアクセスを任意にロックできる機能だ。Intel IPTは、専用ハードのチップセット実装によって、ハードウェア・トークンに準ずる強固なセキュリティ・トークンを、ソフトウェア・トークンで実現しているもので、運用コストはソフトウェア・トークン並の低さに抑えることができるという"良いとこ取り"の機能だ。
そして、こういった機能メリットを備える企業向けUltrabookの、最新の具体的な導入事例、導入先での活用例が紹介された。

|

|
|
名古屋市高齢者医療サービス事業団の事例。ASUS「ZENBOOK」とIntel ATをと組み合わせた導入で、医療データ漏洩に備えが必要な訪問介護の現場で活用。当初はタブレットを導入していたが、画面サイズやインタフェースで課題があり、Ultrabookの導入へとしている |
|

|

|
|
日刊現代の事例。デル「XPS 13」とIntel IPTとを組み合わせた導入で、取材活動に活用されている。インテル スマート・コネクトに対応したウェイズジャパンのクラウドサービスと連携することで、取材写真の効率の良いアップロードの仕組みを構築している |
|

|

|
サッカーダイジェストの事例。こちらもIntel IPTと組み合わせ、ウェイズジャパンのクラウドサービスとも連携し、編集部の取材活動に活かされている。行く行くは全社員のクライアント端末としてUltrabookを導入する方向でも進めているという |
キヤノンマーケティングジャパンの事例。企業内の標準クライアントとして、1万2千台の大規模導入を行い、オフィスのフリーアドレス化に活用している |
常陽銀行からは、営業推進部 法人営業グループ 主任調査役 小林弘幸氏が登壇し、直接、事例の紹介を行った。この事例はユニークで、常陽銀行の法人向けインターネットバンキングサービス「JWEBOFFICE」の端末として、同銀行の顧客に対し、Ultrabookの導入を案内している、というものだ。Ultrabookにはマウスコンピューターの製品である、LuvBook Lシリーズのカスタマイズモデル「LB-L401B-JWEB」が導入されている(別途詳細のニュース記事はこちら)。

|

|
常陽銀行 営業推進部 法人営業グループ 主任調査役 小林弘幸氏 |
Ultrabookにはマウスコンピューターの製品である、LuvBook Lシリーズのカスタマイズモデル「LB-L401B-JWEB」を利用 |
この事例の背景には、常陽銀行の顧客が、パスワードだけの利用者認証では不安を感じ始めていること。また、Windows XPの端末を利用していたユーザーがハードウェアの更新時期を迎えていること。そして、新しい電子記録債権「でんさい」という仕組みが間もなく稼動予定で、これが従来の振込みや手形の取り扱いに比べメリットが多く、全国的に顧客がひろく対応する必要が実需として顕在化しつつあり、最適な端末の新規導入のニーズが高まっているといった複数の要因が存在している。
常陽銀行は地方銀行であるという特性もあり、顧客は比較的小規模な事業主までひろがっていることから、初めてのPC導入という場合も多く、より安全で安心できる企業向けUltrabookがフォーカスされたという。あわせて、そういった顧客へのサポートの体制を充実させる必要から、マウスコンピューターの保証体制の手厚さがマッチし、機種の選定につながったとの説明もあった。
続いてオービックビジネスコンサルタント(OBC)から、開発本部 ICTセンターの宮治朱美氏が登壇し、同社における導入事例の紹介を行った。基幹業務ソリューション「奉行シリーズ」で知られる同社では、営業部門の社員のクライアント端末を中心に、パナソニックのコンバーチブルUltrabook「Let'snote CF-AX2」が導入され、すでに業務活用がはじまっている。