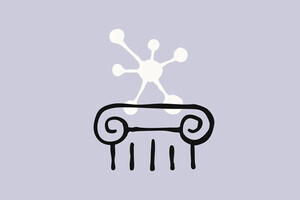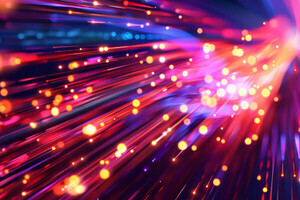違約金条項を含む契約の締結が困難に
新法の施行は中国の労働市場全体にすでに大きな影響を与えている。縁を切られるのは従業員だけではない。優秀な従業員が企業に見切りをつける例が、これまで以上に頻繁に起こる可能性がある。
労働契約法の一部の条項は、従業員に企業を辞める「特権」を与えている。これらの規定は、従業員の流動性がただでさえ高いIT企業にとって、特に効いてくることが予想される。新法の第37条では、「従業員が30日前までに書面で使用者に知らせれば、労働契約を解除することができる」と定めている。第25条では更に、「秘密保持義務違反と当該従業員が受けた特別な研修に関することを除けば、使用者と従業員が、違約金負担にかかわる約定を交わしてはならない」と規定している。
これらの条項を含む労働契約法の施行で、労働市場の流動性が高まるのは間違いない。企業側が本当に恐れているのは、優秀でやる気のある社員が外に飛び出し、向上心のなくなった社員ばかりが社内に残ってしまうという事態だ。違約金条項を含む契約を簡単に結べないとなれば、これはと見込んだ社員と長期契約を結べたとしても、すぐに去られてしまうのではないかと企業側は懸念しているのである。
「業務を全うできない」ことについて、企業側に検証責任
新法は、従業員側の転職の自由度を高めた一方で、企業に対しては社員を解雇する難しさを高めた。同法の定めるところによれば、労働者を解雇するには「一定の法定事由」がなくてはならない。労働契約の解除が可能となる条件として、新法は「労働者が業務を全うできないことが証明され、職業訓練または職務調整を経てもなお業務を全うできない場合(第40条の2)」などと定めているが、その検証責任は使用者側にあるのである。
しかも、解雇にあたっては、法定プロセスを通じて法定の補償を社員に与えなければならない。たとえば上述の「業務を全うできない」社員を解雇したい場合、企業は労働契約法の規定により、次の6つのステップを踏まねばならない。
- 任に堪えないことを証明する
- 当該社員に対し職務訓練をほどこし、職務調整を行う
- 当該社員が依然として任に堪えない証拠を挙げる
- 30日前までに、当該社員に通知を行う
- 労働組合に通知する
- 経済補償金を支払う
前述のとおり、企業は検証責任を負っており、充分な準備なくしては、法廷で敗訴する可能性が極めて高いと考えられている。