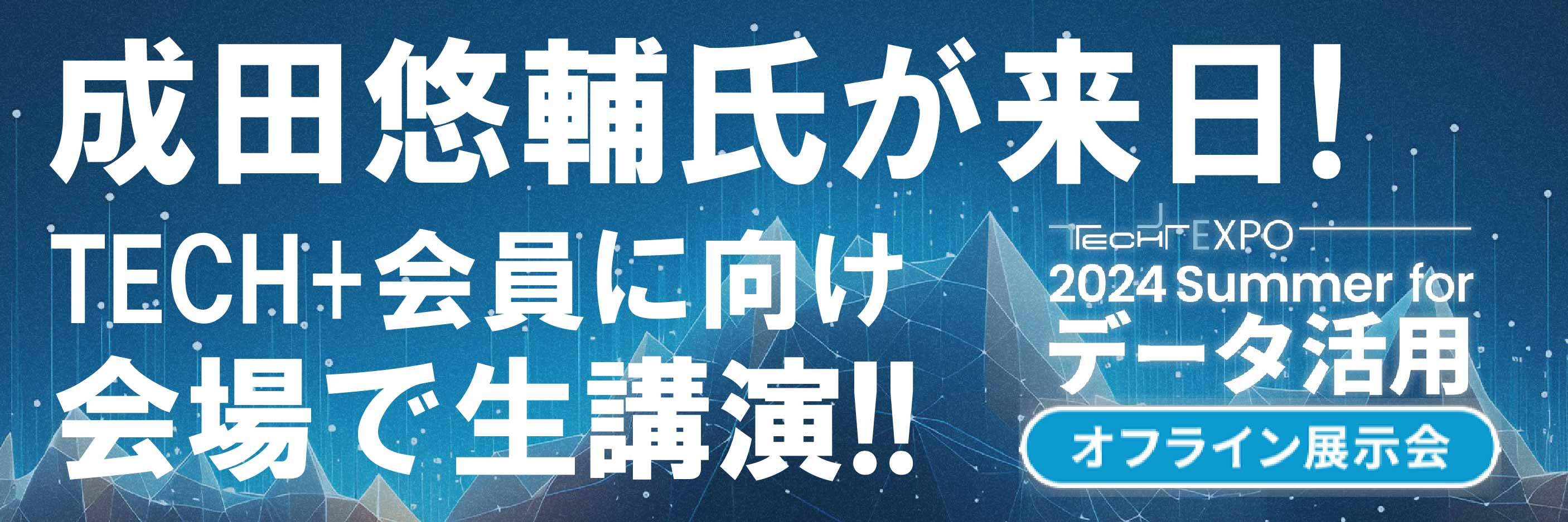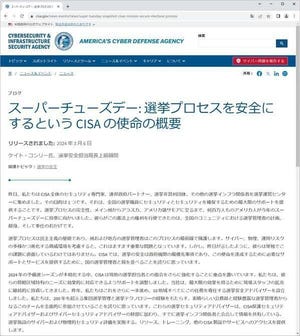近年、投資家の間でESG投資の注目度が高まっている。Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字を取り、持続可能な発展を目指す企業に投資するという動きのことだ。中でも、企業の女性活躍推進を評価する投資家は多い。機関投資家のおよそ3分の2が、女性管理職比率などの女性活躍情報を投資判断に活用しているというデータもあるほどだ(※1)。
その一方で、月経や更年期といった女性特有の健康課題が、企業の業績や社会全体に与える影響は大きい。離職・休職・欠勤・パフォーマンスの低下などによる経済損失を、経産省は3.4兆円と試算している(※2)。少子高齢化が進み、労働人口の減少が日本の大きな課題となる中、女性の健康支援はいまや今後の企業価値を高める重要なカギであるともいえるのだ。
では、企業は女性の健康支援にどのように取り組めばよいのか。一般社団法人日本投資顧問業協会 ESG室長 徳田展子氏と、予防医療テックスタートアップの株式会社リンケージ 代表取締役社長CEO 生駒恭明氏の対談から考えていこう。
-
(左)一般社団法人日本投資顧問業協会 ESG室長 徳田展子氏、(右)株式会社リンケージ 代表取締役社長CEO 生駒恭明氏
対談者 プロフィール
一般社団法人日本投資顧問業協会 ESG室長
徳田展子氏
早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。東京海上アセットマネジメントにてESG投資を含む責任投資全般を担当したのち、2018年8月より現職。内閣府、厚生労働省等の検討会委員を務める。香川県出身。2児の母。
株式会社リンケージ 代表取締役社長CEO
生駒恭明氏
京都大学法学部卒。祖父が産婦人科医、祖母が看護師、父が歯科医という家庭で育つ。MKSパートナーズで企業再生の道を歩み、ヘルスケア領域でM&Aを通じて数々の事業を創ってきた。2018年11月より現職。
ESG投資と女性活躍推進の意義
徳田氏:私は高校生の頃から、世の中がより良くなるためには「あるべきところにお金が流れること」が大事だと思っており、将来はそういった仕事に携わりたいと考えていました。1999年にエコファンド(企業の環境配慮を評価する投資信託)が始まったときは、これだ! と胸が躍ったものです。その後、日本社会において明確に潮目が変わったのは、2015年にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、ESGを投資プロセスに組み入れる、国連のPRI(責任投資原則)に署名してからです。「投資家も社会課題を解決しながら利益を得ていくべきだ」という機運が高まってきました。
一般社団法人日本投資顧問業協会 ESG室長
徳田展子氏
生駒氏:我々リンケージのヘルスケア施策を検討していただく際は、現場よりも経営層に、「健康支援が企業活動の土台となる」という考えを受け入れてもらいやすいです。株主やステークホルダーなど、自社を取り巻く社会的状況を広く把握している方ほど、ESG投資も意識されていて、そこに戦略的な価値を見出されています。
徳田氏:トップのコミットメントは非常に重要ですね。環境・社会への取り組みや、ガバナンスという土台がちゃんとしていないと、財務の価値は上がっていきません。そこに企業価値の源泉があると腹落ちして、経営戦略に組み込んでいける企業はやはり強いです。とくに最近は、「S(社会)」の重要テーマである「人的資本」が注目されています。不健康でやる気のない従業員ばかりでは、価値が最大化されるはずもないですから。「女性活躍推進」もトピックの一つです。
生駒氏:我々リンケージは管理職の5分の2が女性、従業員の男女比は5:5となっていますが、こういった情報も、投資家は見ているのでしょうか?
徳田氏:「女性の取締役比率」は、企業を評価する上で重要ポイントの一つです。経営層に女性が入れば、それだけ女性が働きやすくなり、男性目線では気づかなかったアイデアが会社に生まれていきます。中長期的に見て、企業価値が向上していきやすいと考えられているのです。
そうした女性活躍推進に取り組んでいるのは、私たち資産運用業界も同様です。これまでは財務の数字を中心に分析すれば良かったのですが、今はCO2排出量といった環境に関する情報や、女性管理職比率といった人的資本に関する情報など、非財務情報を含めて企業の価値を見極めねばなりません。企業を評価する上でも、「多様な視点」が求められるようになったのです。そこで、女性をもっと運用部門に増やそうという流れが生まれています。
生駒氏:一方で女性には、月経に伴う不調や妊娠・出産、更年期障害といった、女性特有の健康課題がありますね。これは女性が個人で解決するのは難しい問題です。本人が不調はあって当たり前のものととらえ、病院に行くべきレベルかが分からなかったり、育児・家事・仕事に追われて自分のことは後回しになっていたりと、その理由は多くあります。
しかし、こうした女性特有の健康課題を理由に離職・昇進辞退をされる方は、なんと女性従業員全体の約5割にものぼるそうです。つまり女性活躍を推進し、企業価値を向上していこうと考えるのであれば、女性社員の健康サポートは企業が必ず取り組まねばならない課題であると企業が気づく必要があります。
専門医と女性従業員を繋ぐことで、体調不良を改善する
生駒氏:女性特有の健康課題について、社内のヘルスリテラシーを向上し、定期的に婦人科へ通院いただくことで疾患の予防・治療することを目的としたヘルスケアサービスが、私たちリンケージの提供する「FEMCLE」です。日本子宮内膜症啓発会議(JECIE)と提携して、Web問診と受診勧奨、専門医によるチャット相談、医療機関の紹介などをおこなっています。
開発の背景にあるのは、婦人科医の課題感です。婦人科では、「もっと早く通院していればここまで大事に至らなかったのに」という疾患を持つ患者が来院されることが少なくないそうです。全国の婦人科専門医の「悪化する前に婦人科へ足を運んで欲しい」という想いから、子宮内膜症を啓発する目的でNPO団体「JECIE」が立ち上がったのが2012年のことです。この想いを受け継ぎ、テクノロジーの力でより安価に、よりスピーディーに全国の女性の健康を支えたいという思いで、FEMCLEを開発しました。
株式会社リンケージ 代表取締役社長CEO 生駒恭明氏
徳田氏:もっと早く知りたかったサービスです! 私はいま3歳と6歳の子がいるんですが、仕事と育児で疲れているのに、夜中、よく目が覚めてしまっていました。コーヒーの飲み過ぎでもない。ストレスでもない。原因が分からなくて悩んでいたのですが、ようやく「これって更年期かも?」と気づいて、更年期外来を受けることができました。
生駒氏:実は「女性特有の健康課題に伴う95%の症状は、適正な治療をすれば改善できる」と医学的にも証明されています(※3)。であるにも関わらず、女性のうち74%が月経に伴う不調を抱えていながらも「婦人科を受診した人」は約2割にすぎないという調査結果があります。ソリューションは明確にあるのに受診してくれない、という悩みがあったのです。こうしたギャップ解消を支援するしくみがFEMCLEです。
徳田氏:確かに、正しい情報をもつ専門医に、気軽に相談できていれば、もっと早く対応できる人が増えると思います。
生駒氏:FEMCLEを導入していただくと、まずは就労女性に多い5つの疾患に関するWeb問診を受けていただきます。問診結果は専門医が一人ずつ丁寧に解析して、「要至急受診」「受診推奨」といったかたちで客観的に判定結果をお戻しします。判定に疑問がある場合には、専門医へ直接相談できるチャット機能もあります。
導入いただいた企業のユーザーからは、「ずっと気にはなっていたけど、これまでは仕事や子どもを優先していた。受診してみたら小さな疾患が見つかりました」「病院に行く時間を作るのは物理的にも精神的にもハードルが高いので、受診前に婦人科医にチャット相談することで納得して受診できた」という声をもらっています。
徳田氏:婦人科の受診をためらってしまう理由の一つに、「ちょっと怖い」といったイメージがあると思います。ネットの情報は何が本当でウソか分かりませんから、専門医と直通で相談できるのはとても心強いことだと思います。
管理職のためのヘルスリテラシー講座
生駒氏:実は、女性の不調による損失は、社会や企業にとっても非常に大きなものとなっています。経産省は、離職・休職・欠勤・パフォーマンスの低下・追加採用の費用などを合算して、全体で3.4兆円もの経済損失が生まれていると試算しています。
男性はメタボなど生活習慣に起因する疾患が多く、これは定期健康診断でスクリーニングできるのですが、女性の場合はホルモンバランスの変化に由来する疾患(子宮筋腫、子宮内膜症、更年期障害、月経困難症等)が多いのが特徴です。女性向けの健康診断オプションとして乳がん・子宮頸がんを選択することが多いと思いますが、こうした女性ホルモン由来の疾患は、健康診断項目に含まれておらず、初期的には自覚症状がないことも多いため、女性自身が疾患の存在に気が付きにくいのが特徴です。
徳田氏:症状が改善できれば、当人にとっても、企業にとってもプラスになりますね。でも、「ホルモンバランスで体調が変わる」ということは、男性にはなかなか実感しにくいことでしょう。気遣いたいけど、何か言ったらセクハラになりそうで……と困っている方もいると思います。
生駒氏:FEMCLEは、男性や管理職に向けて、ヘルスリテラシーを向上するための研修も用意しています。女性特有の健康課題に関する基礎知識はもちろん、具体的なケーススタディを用いながら「どう声がけすればセクハラにあたらないのか」といったことも各企業のカルチャーを踏まえ、企業担当者と綿密に打ち合わせをした上でお伝えします。受講された方の中には、更年期で苦しむ奥様にホルモン補充療法を勧めるなど、職場だけでなく家族への意識まで変わった、という方もいらっしゃるんですよ。
徳田氏:家庭円満も、仕事でパフォーマンスを出す上でとても大切ですね。男女ともに健康の知識を身につけて、助け合う社風が生まれれば、もっと働きやすい会社になると思います。女性だけでなく、男性にも正しい知識に「気づく」機会を提供することができれば、女性に対するアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)も徐々に解消していくのではないかと期待しています。
生駒氏:我々は、女性の健康を組織課題として認識していただくために、FEMCLEのデータをもとにした「組織診断レポート」を企業にフィードバックしています。症状別・年代別での有症状者率・仕事への支障率や、それらによってもたらされる年間の労働損失額などをお示しするとともに、各社の状況に応じた改善策の立案・実行までを伴走しています。
徳田氏:投資家が「人的資本についてどのような取り組みをしていますか?」と尋ねたときに、内容だけでなく、その取り組みによって労働損失額がどれだけ減ったのか、具体的な効果が見せられるのは強いですね。そうした情報を、KPIとともに企業の統合レポート等に積極的に書いていただき、投資家との対話につなげていただけると、さらに良い評価が得られると思います。
従業員にも、投資家にも選ばれる職場づくりを
生駒氏:ITの活用によって、「一人ひとり異なる健康課題」に寄り添える時代となりました。一方、日本人女性は仕事に加え、家事・育児・介護と背負っているものが多く、ご自身の健康が後回しになっている方が多い。こういった社会情勢だからこそ、企業が主体となり、女性達が自信の健康状態に目を向ける機会を創出することが肝要です。「我慢」することなく、健康的に女性が活躍できる職場への投資が、企業のサステナビリティに寄与するよう今後も支援していきます。
徳田氏:昨年、ESG投資の「S(社会)」を測る指標として、「日本版ディーセント・ワーク8指標(JD8)」が公表されました(※4)。そこには、男女格差の撤廃や柔軟な働き方、人的資本への投資、ダイバーシティ&インクルージョン、などが項目として挙げられています。健康な男性が働くことを前提とした企業拘束性の高い従来の働き方を見直し、誰もが尊重され、安心していきいきと働ける社会を構築することで、企業価値向上と持続可能な社会の両方を実現するための指標でもあります。
また、内閣府の調査で明らかになりましたが、女性活躍情報を投資判断に活用している機関投資家のうち、およそ4分の3の方々が女性活躍情報を「企業の業績に長期的には影響がある情報」と考えています。このように投資家も大きく注目していますから、ぜひ、取り組みを具体的に進めていただければと思います。
<参考資料>
(※1)ジェンダー投資に関する調査研究(令和4年度)(内閣府男女共同参画局)
(※2)女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について(経済産業省ヘルスケア産業課/令和6年2月)
(※3)Cost-effectiveness of the recommended medical intervention for the treatment of dysmenorrhea and endometriosis in Japan(Ichiro Arakawa, Mikio Momoeda, Yutaka Osuga et al. 2018/16/12.)
(※4)日本版ディーセント・ワーク8指標(公益財団法人連合総合生活開発研究所、株式会社Quick)
[PR]提供:リンケージ