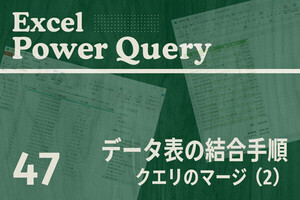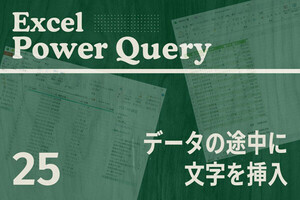働き方改革の一環として、また新型コロナ感染のリスク回避策として、在宅勤務によるテレワークを採用する企業が増えている。しかし、実際には出社しなければできない仕事が多かったり、外部から社内ネットワークへのアクセスが困難だったり、新しい働き方に見合った環境が整っていないケースも多いようだ。そうした課題を抱える企業が、今後、環境整備を進めるにあたっては、どこから着手し、どのように進めていけばいいのだろうか。
解決に向けた考え方の一つとして、NTTコムウェアの長尾 憲幸 氏の講演「ニューノーマル時代の働き方を支える環境づくりとは」を紹介しよう。本講演は、2020年9月3日にオンライン開催されたマイナビニューススペシャルセミナー「全体生産性から導く『働き方改革』主導法 ~バックオフィス部門から"新たな生産性を"~」で行われた。
クラウドサービスを活用し、バックオフィス部門での業務改革を
長尾氏はまず、企業が取り組むべき課題として 「バックオフィス部門の業務改革」「バックオフィス部門の働き方改革」を挙げ、それらを実現することで得たリソースを「新たなビジネスの創出」にシフトしていくことが、会社全体の生産性向上につながると語った。この3つを成功に導くためには、クラウドサービスの活用がポイントになるという。
バックオフィスの業務改革を説明するにあたり、長尾氏は料金請求業務を例にとって、従来の課題を列挙した。「毎月の請求額の計算や請求書作成が大変で、期限に間に合わない」「未納者への個別対応が多く回収コストがかさむ」「請求書を古い住所に送ってしまった」「誤請求が発生してしまい、返金を行うことになった」「複数請求をまとめて入金された際に、どの請求だったのか確認が大変で作業が属人化している」などだ。
「料金請求業務を手作業で対応する場合、想像以上に膨大な手間がかかります。また、お客様への請求を取り扱う業務のため、ミスが発生すれば信頼の失墜にもつながります。実は業務の至る所に『落とし穴』があるのです。これらの課題は、料金請求業務のベストプラクティスが活かされたクラウドサービスを導入することによって解決できます」(長尾氏)
こうしたサービスを利用して、業務に必要となる情報を階層構造で保持する仕組みを整えれば、「どの顧客に対して、どんな条件で、どんなサービスを提供しているか」を効率的に管理できる(下図参照)。入力補助をはじめとするサポート機能で、ミスを防ぐ仕組みが整っているサービスも多い。さらに、料金計算、請求額の確定、請求書の送付など、毎月の定型作業が自動化されることによって、大幅な作業効率の改善が期待できる。
最近のクラウドサービスには、AIによる自動判定サービスも用意されており、例えば入金データと請求の紐づけを確認する作業に利用されている。入金データとして提供される振込人名義は、略称や、法人格を省略した入力が行われるケースが大半であり、従来は業務に習熟した従業員が1件ずつ紐づけを確認して消込を行う必要があった。こうした人手による判断をAIによる機械学習を活用して効率化する動きが進んでいる。NTTコムウェアが提供しているAIサービスの場合、過去1年間の入金消込の組み合わせを学習させることで、80%の消込を自動化できたという。
「ベストプラクティスを活用したクラウドサービスを利用することで、ミスのない管理や情報の一元管理、定型業務の自動化が可能です。さらにAIサービスを活用した業務の効率化も組み合わせることで、バックオフィス部門の業務改革が実現できます」(長尾氏)
テレワーク環境を整え、バックオフィス部門での働き方改革を推進
働き方改革の有力な手段であるテレワークだが、ある調査の結果によれば、バックオフィス部門でのテレワーク実施率は3割程度にとどまっている。その理由としては「重要なデータを扱う業務であるために自宅ではできない」「セキュリティを考えると情報の入ったパソコンを家に持ち帰れない」などが上位だ。こうした課題を解消し、テレワークを推進していくためにも、クラウドサービスが利用できると長尾氏はいう。
「クラウドサービスは、場所を問わずにどこからでも利用可能です。本社ビルからはもちろん、リモートオフィスや自宅からでもアクセスできます。また自社システムや他社サービスとの連携も、APIによって手軽にできるような仕組みになっています」(長尾氏)
そのほかのメリットには、システムを構築することなく、環境設定と操作方法の習熟だけですぐに使えること、災害時や障害発生時の事業継続性、自社でセキュリティ対策やパッチ適用を施す必要がないことなどがあり、「クラウドサービスならではの利点が、バックオフィス部門の働き方改革につながると考えています」と、長尾氏はいう。
煩雑な業務からリソースをシフトして、新たなビジネス展開へ
バックオフィス部門の業務改革、働き方改革で、コストや人員などのリソースに余裕を生み出し、それらを新ビジネスにシフトして、会社全体の生産性向上に取り組むことを長尾氏は勧める。新ビジネスの例として、長尾氏が提案するのは「サブスクリプション」だ。
「サブスクリプションは、お客様の利用動向を踏まえたサービス提供ができるため、不況の影響を受けにくいビジネスモデルです。サービスのプランを見直したり、オプションのサービスを追加したり、利用量が減ってきたお客様には、ダウンセルや一次休止を勧めることで解約を防止することもできます。お客様の利用動向に合わせてアクションを取ることで、継続的な関係を築くことが可能になります。このようなメリットを背景に、サブスクリプションビジネスに取り組む企業は着実に成長しています」(長尾氏)
長尾氏は、サブスクリプションビジネスを展開するのに役立つクラウドサービスとして、NTTコムウェアの「Smart Billing」を紹介した。最短1カ月で導入できる「Smart Billing」は、サブスクリプションビジネスにおける料金請求に必要な一連の機能、例えば料金体系をGUIで簡単に設定できるプライシング機能、3階層のデータ管理で柔軟な対応を可能にする顧客管理機能、顧客ごとに契約を管理できる機能、自動料金計算などを備えており、「どんなサブスクリプションも思いのまま」(長尾氏)に展開できるという。回収方法も、請求書払い、口座振替、クレジット払い、コンビニ払いに対応し、自由に組み合わせて提供することが可能だ。さらに分析に利用できるよう、主要なKPIの可視化機能も搭載されている。
「もう一つ、NTTコムウェアが提供する『PayMa』という消込業務を効率化するサービスもあります。AIで入金消込業務を支援、効率化するSaaSです ――新しいビジネスの創出には、こうしたクラウドサービスの活用がポイントになります。煩雑な業務から脱却して、新たなビジネスを考えるところにリソースシフトしていただければ幸いです」
このように語って、長尾氏は講演を締めくくった。
Smart Billing
https://www.nttcom.co.jp/smartbilling/LP_inflow/