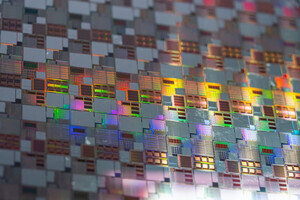世界中にユーザーを持つオープンソース監視ソリューションZabbix。そのユーザーやパートナー企業の情報共有を目的として、2016年11月、「Zabbix Conference Japan 2016」が開催された。レポート第1弾では最新バージョンZabbix 3.2の新機能や、「Interop Tokyo 2016」での利用事例などを採り上げた。第2弾となる本稿では、ユーザー企業、パートナー企業が行った講演の概要をお届けする。
 |
OSSならではの柔軟性を発揮 ~ Zabbix活用事例
まずは活用事例を紹介しよう。KDDIでは、同社が提供する法人・ビジネス向けクラウドサービス「KDDI クラウドプラットフォームサービス」のクオリティ維持にZabbixを活用している。「とめない(高可用性)・まもる(高信頼性)・つながる(高接続性)」をコンセプトにしたこのサービスは、稼動実績99.999%以上という高い安定性が自慢だ。それを支えるZabbixの利用事例を、同社プラットフォーム開発本部の加藤 真人氏がいくつか紹介した。ここではそのうち3つをピックアップしよう。
【1】 仮想サーバーの自動登録:クラウド基盤ソフトウェアのAPIログから「仮想サーバー作成コマンド」「KVMホスト追加コマンド」をZabbixで検知、監視ホスト登録を自動化している。
【2】仮想サーバー再起動の動作を検知: Zabbixの監視対象となっているホストを、多くのユーザーが停止・再起動させると、アラートにより運用負荷が上がってしまう。そこでAPIログからユーザーの処理を検知し、該当サーバーの監視ステータス(有効/無効)の切り替えを自動切化している。
【3】基盤ソフトとの登録状態同期:クラウド基盤ソフトとZabbixはリアルタイムに自動連携させているが、同期に失敗した場合に備え、夜間に自動で差分の吸収処理をしている。「動化に潜むリスクを回避するための自動化も必要だと、加藤氏は言う。
 |
 |
KDDI株式会社 プラットフォーム技術部 |
九州通信ネットワーク株式会社 |
九州通信ネットワークの木村 裕氏は、Zabbixパートナー企業である九電ビジネスソリューションズ、インターネットイニシアティブ(IIJ)の協力の下、Zabbix 2.2に自社の課題解決のための機能を実装した経験を語った。まず導入した、見やすく、かつ細かい検索条件を指定できるUIを開発し、Zabbixのアラーム、システムログ、Trapからのエラーを一元管理できるようにした。このUIを利用して、冗長化目的で運用しているZabbixサーバー2系統の設定を同時に行える仕掛けをつくって作業の負荷軽減に役立て、また強制復旧にも対応できるよう、他システムとの連携も図った。
さらにはディスクやライセンスの増強時期を、Zabbixに自動予測させる機能も開発した。後日、予測機能はZabbix 3.0で、強制復旧機能はZabbix 3.2で実装されることになるのだが、こうした独自開発が行えるのはZabbixが自由度と柔軟性に富んでいることの裏付けと言える。現在、木村氏はZabbixを利用して、パターンマッチングによる異常検知や予兆監視の実現に取り組んでいるという
新たなソリューションへの挑戦 ~ Zabbixが生む可能性
 |
株式会社あくしゅ |
Zabbixを利用した新しい試みは、他の企業でも盛んだ。あくしゅは、IaaS基盤ソフトウェアWakameや、その機能の一部を独立させた仮想ネットワークソフトOpenVNetなどを生み出した開発企業だ。WakameとZabbixを組み合わせたVM管理・監視サービスを大手クラウドサービス企業に提供するなど、多くの実績を持っている。 同社では今、仮想ネットワーク上に本番環境と同じものをつくり、そこでシステムの運用テストを行う仕組みづくりを進めている。これが実現すれば、例えばファームウェアをアップデートしたり、新しいルールを設定したりする場合、本番環境に適用する前に十分なテストを行えるようになる。
「この仮想のテスト環境の中にZabbixを入れたいと思って、今、工夫を重ねているところです」(あくしゅ 代表取締役 山崎 泰宏氏)
パナソニック ソリューションテクノロジーでは、「ユーザー指向監視」という新たな監視手法に取り組んだ。ユーザーはシステムの応答が遅いと感じると、イライラしたりシステムの改悪を疑ったりする。ユーザーが体感するレスポンスの質を、クレームが出る前に把握・改善できれば、システム管理者のストレスは軽減すると、同社カスタマーリレーション部の関戸 智史氏は考えた。
 |
パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 カスタマーリレーション部 関戸 智史氏 |
「そのためにはユーザー目線での監視が必要となります」(関戸氏)
同社が提供している、画面の表示時間やアプリケーションの応答速度を数値化するソリューションで得た数値を、Zabbixに送ることでユーザーの体感を監視するシステムを構築した。Zabbixに閾値を設定することで、レスポンスが低下した際にはアラートが出てシステム管理担当者に知らせる。これにより管理者が状況把握や迅速な対処をするのに役立つだけでなく、対処後にはその効果を確認することも可能となった。このサービスは現在「システム診断サービス」のオプション「体感品質測定サービス」として提供されている。
 |
ぷらっとホーム株式会社 営業部 営業3課 課長 |
ぷらっとホームの後藤 敏也氏は、同社の新型IoTゲートウェイOpenBlocks IoT VX1と組み合わせることで、ZabbixがITの世界以外でも利用できることを示した。OpenBlocks IoT VX1は従来モデルの豊富な機器接続インターフェース、超小型という特長を踏襲しつつ、CPUを高性能化した製品で、あらゆるデバイス、センサーに対応する。搭載されているファームウェアIoT Gateway FW 2.0には、デバイスとゲートウェイの通信をハンドリングするPD Handlerや通信ソフトPD Emitterなどが含まれており、AWS、Watsonなどの主要なIoTクラウドとカスタマイズなしに通信できる。またIoTアプリの構築用にはNode-REDが用意され、グラフィカルな画面で容易にプログラムができるようになっている。セッションではOpenBlocks IoT VX1とZabbix、センサーを組み合わせた温湿度監視や、ビーコンの送信設定を利用した入退出監視などの活用事例が示された。
いっそう効果的に利用するために ~ ZabbixプラスOSS
OSS(オープンソースソフトウェア)であるZabbixを、他のOSSと組み合わせて仕事の効率を高める方法も紹介された。SRA OSS, Inc. 日本支社の佐々木 宏一朗氏は、Zabbixとログ収集ツールFluentd、データの可視化を得意とするダッシュボードGrafanaを組み合わせた監視システムの構築事例を披露した。Zabbixでもログ収集は可能だが、複数行のログを扱ったり、ログを加工したりすることは難しい。そこで佐々木氏はFluentdでログを収集してデータをZabbixに出力、異常があればアラートを出すというシステムを構築した。問題がなかったデータについてはDBに出力・保存する。そして複数の外部DBからデータを取得できるGrafanaで、まとめて可視化するのだ。この手法を利用すればZabbixサーバーを複数運用している場合でも、サーバーごとに監視画面を切り替えずにすむようなる。
 |
 |
SRA OSS, Inc. 日本支社 マーケティング部 |
TIS株式会社 IT基盤推進技術部 OSS推進室 |
TISの山本 文彦氏は、同社がOSSとして提供しているZabbix向けAWS監視テンプレートを紹介。監視設定だけでなく、ZabbixからAWSのサービスを呼び出す仕掛けも含まれており、AWSとオンプレミスを組み合わせたハイブリッド環境でも利用できる。AWS側で用意されている監視ツールCloudWatchからデータを吸い上げ、Zabbixで一元管理する構造なので、将来的に別のパブリッククラウドに乗り換えても、運用に影響が出ないという利点もある。
テンプレートの主な機能としては「Amazon CloudWatchメトリクス監視」(CloudWatchとZabbixの監視データを総合評価して一元的に運用)、「AWS各サービス課金情報監視」(CloudWatchで吸い上げた課金額をZabbixで統合的に評価)、「AWSサービス稼働状況監視」(AWS Service Health Dashboardでの警告情報をZabbixに集約)などがある。
これから本格利用を考えているなら ~ Zabbixの運用・導入サービス
Zabbixの導入・運用をサポートするサービスも紹介された。Zabbixと長い関わりを持つアークシステムでは、これまでの導入・運用支援の実績を活かし、「まるごとおまかせZabbix」というサービスを2017年1月から開始する。監視環境構築、保守サポート、高可用性・CSV出力(オプション)などを提供するという。 またZabbixの運用をアウトソーシングしたいという企業向けには、サイトロックから「統合運用監視サービス」が紹介された。ユーザー企業のZabbixサーバーを、同社のROC(Reliability Operation Center)にいる専任スタッフが、SSHトンネル経由で運用する。Zabbixに慣れていない企業でも安心して利用できそうだ。
 |
 |
株式会社アークシステム 新井 健志氏 |
サイトロック株式会社 |
カンファレンスは午前10時から午後5時半までの7時間半におよんだが、来場者は終始熱心に耳を傾け、また登壇者も自社の事例や成果を誇らしげに語っているのが印象的だった。最後に登壇したZabbix Japan代表の寺島 広大氏は、次のようなコメントでカンファレンスを締めくくった。
「Zabbix 3.4は2017年3月リリース予定で開発しています。来年のカンファレンスの頃には4.0もリリースされているはずなので、もっと成長したZabbixを見ていただけるのではないかと思います」
なお、当日の発表資料はこちらで確認できるので、ご一読頂きたい。
レポート第1弾はこちらから確認できます。
(マイナビニュース広告企画:提供 Zabbix Japan)