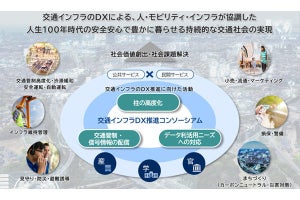インフラシェアリング事業を手がけるJTOWERは、米DigitalBridge(デジタルブリッジ)による株式公開買付(TOB)に賛同したことを発表。成立すれば同社の傘下となって上場廃止となる見込みですが、同社はNTTドコモなどから多くの通信鉄塔の譲渡を受けており、それらがいとも簡単に外資の手に渡ることでインフラの安全保障上のリスクとなる懸念などが指摘されています。インフラシェアリングのリスクを改めて考えてみましょう。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。
先行投資で業績低迷のJTOWERに外資が狙い
複数の携帯電話会社が設備や場所などを共用することで、コストを抑えながらネットワークを整備するインフラシェアリング。これまで、その活用があまり進んでいなかった日本の携帯電話会社も、高い周波数を用いる5Gでより多くの基地局を設置する必要が出てきたこと、そして政府主導の料金引き下げ要請で収益が大幅に悪化したことなどを受け、積極活用する方針へと舵を切っています。
実際、KDDIとソフトバンクは、インフラシェアリングのための「5G Japan」という会社を2020年に合弁で設立。地方の5Gに関するインフラシェアリングを主体に展開していましたが、それを都市部、なおかつ4Gにも拡大するなど、インフラシェアリングの積極化に大きく踏み切っている様子がうかがえます。
-

KDDIの決算説明会資料より。KDDIはソフトバンクと合弁で展開している「5G Japan」を通じたインフラシェアリングをさらに強化し、両社で地方だけでなく都市部でもインフラシェアリングを推し進める方針を打ち出している
しかし、インフラシェアリングで現在、最も注目されているのはJTOWERではないでしょうか。JTOWERは主に屋内でのインフラシェアリングなどを手がける企業で、2022年3月にはNTTドコモから6002基の通信鉄塔の譲渡を受けることを発表するなど、大株主であるNTTのグループ企業から通信鉄塔を譲り受けて屋外のインフラシェアリングにも本格的に乗り出していました。
ただ、そのJTOWERは2024年8月14日、米国のデジタルブリッジによる株式公開買付(TOB)に応じると発表し、大きな驚きをもたらしました。デジタルブリッジはデジタル関連インフラの投資会社で、携帯電話基地局や光ファイバー網、データセンターなどに投資をしている企業です。
それゆえ、JTOWERのようにインフラシェアリング用の通信鉄塔などを保有する企業への投資経験も豊富に持っているようで、JTOWERの買収に至ること自体は自然な流れといえますが、一方のJTOWER側はなせ、外資からのTOBに応じるに至ったのでしょうか。
同社の発表内容によりますと、国内のインフラシェアリングは今後本格化して重要性が高まると考えられる一方、その需要にこたえるには長期的な視点での先行投資が必要とのこと。
ですが株式市場からの資金調達は「株価の状況により資金調達に制約が生じる可能性があり」「短期的な収益性が重視される傾向が強く、将来の成長を見据えた先行投資が実施しづらい」ことなどから、長期的な成長のためTOBに応じるに至ったとしています。
JTOWERの株価を確認しますと、同社が2024年5月9日に、2025年3月期の最終損益が赤字になるとの予想を発表して以降、急速に落ち込んでいるようです。
NTTドコモからの通信鉄塔の譲渡が進み保有する鉄塔自体は増え、売り上げは伸びる見込みですが、人員の強化や鉄塔取得に伴う支払い利息、固定資産税が増えることなどから、赤字予想に至ったようです。
ゆえにJTOWERは現在、事業拡大に向けた先行投資が響いて、経営が厳しい状況にあるといえます。そこで、株価低迷と事業の将来性に目を付けたデジタルブリッジが、豊富な資金力を強みとして買収に動いたと考えられそうです。
外資の手に渡ったNTTグループの鉄塔、NTT法の議論に影響も
同社の発表資料を確認するに、TOB完了後も現在の経営体制は維持されるとのこと。またTOB前の大株主であるNTTグループやKDDIとの業務提携は維持するとされており、株主は大きく変わりますが経営面で大きな変化が起きる訳ではないようです。
しかし、今回の買収をよくよく考えてみると、多くの通信鉄塔というインフラが、容易に外資の手に渡ってしまったと見ることもできる訳で、それだけに経済安全保障などの観点から懸念する声も出てきているようです。
実際、現在総務省などで進められているNTT法の見直しに関する議論では、光ファイバーを敷設するのに必要な管路や電柱などの「特別な資産」が外資に渡ることを問題視する声が、競合各社などから挙がっています。
ちなみに、今回のTOBに関するJTOWERの説明資料を確認しますと「弊社としては、公開買付者が必要な外為法上の審査及び承認手続、審査を経た上での本件実施になると理解しており、問題ないものと認識しております」とされています。
また、豪レンドリースが子会社を通じてインフラシェアリング用の鉄塔建設を進めているなど、国内のインフラシェアリングに外資系企業が参入する事例が他にない訳ではありません。
ですがJTOWERが保有する鉄塔の多くは、元々NTTグループが保有していた資産でもあります。それがコスト効率化を重視したインフラシェアリングのためJTOWERに売却・譲渡した結果、いとも簡単に外資の手に渡ってしまうTOBが実施され、しかもそれを大株主であるNTT自らが認めてしてしまったことは、今後のNTT法の議論にも大きく影響してくる可能性があるでしょう。
インフラシェアリングは投資コストを抑えたい携帯各社と、携帯料金を引き下げながらもインフラの充実を求める国の思惑が一致し、5G時代に入り官民の前向きな姿勢が非常に目立つ印象を受けています。
ただ、今回のような外資による買収以外にも、設備を持つ事業者が力を持つことで生じる基地局整備コスト高騰の可能性、インフラの集約で災害に弱くなること、土地と設備の所有者が異なるケースが生じることで災害の復旧対応に遅れが生じる可能性……など、インフラシェアリングが抱える問題点についてはあまり議論されてこなかったように思います。
筆者としてもインフラシェアリング自体を否定する考えはありません。しかし、国内で安定的かつ強靭な5Gインフラの整備を進めるためには、導入に向けコスト効率化の観点だけでなく、もっと多角的な議論で問題点をあぶり出す必要があったのでは?と感じてしまいます。