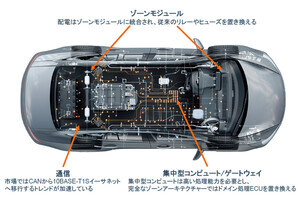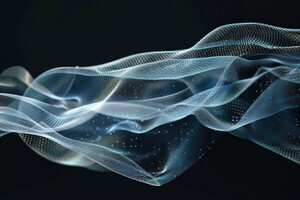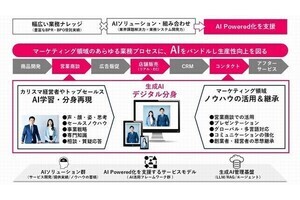4月5日、米国を中心に世界各地で「Hands Off(手を引け)」と銘打ったトランプ政権に対する抗議デモが行われました。全米50州の1,100以上の都市で集会が開かれ、その数は世界中で1,400カ所以上に及び、主催団体は「数百万人が参加した」と報告しています。「テックトピア:米国のテクノロジー業界の舞台裏」の過去回はこちらを参照。
先行きが見えない混乱を招くトランプ氏の関税政策
過去に見てきた抗議デモでは、例えば2011年の「Occupy Wall Street」では20~30代前半の若者(当時はミレニアル世代)が、Black Lives Matterではアフリカ系アメリカ人が主体というように、参加者の顔ぶれにある種の特徴がありました。
今回の「Hands Off」デモは、政治的関心が高い層、リベラル層や進歩派が中心でしたが、退役軍人や労働者層の参加も活発で、今のトランプ政権に対する反発が広範囲に、そして深く浸透していることが伝わってきました。
掲げられるプラカードのメッセージも実に多様でした。「民主主義を守れ」「イーロン・マスクは政治干渉をやめろ」「ウクライナを支援せよ」「トランスジェンダーの命を守れ」といったプラカードが掲げられ、中東問題から手を引くよう訴える人、関税政策に反対する人、社会保障制度の縮小に抗議する人など、参加者の主張は多岐にわたっていました。
これだけ多様な声が集まると、何か特定の解決策に向かうというより、トランプ政権に「NO!」を叩きつける巨大なエネルギーの塊のように見えます。かといって「トランプ退陣」がすぐに現実味を帯びるわけでもなく……。正直なところ、先行きが見えない混乱の中にいる、という印象が残りました。
こうした社会のざわめきとは裏腹に、トランプ政権は立て続けに関税政策を発表し、世界経済を揺さぶり続けています。株価は世界中で急落し、各国間にはピリピリとした緊張感が漂います。「トランプ大統領は一体何を考えているんだ……?」そんな声が聞こえてきます。
たしかに、次から次へと打ち出される政策は、時に「はちゃめちゃ」で予測不可能に見えることも。しかし、「米国が慢性的に貿易赤字を抱える構造からの脱却」という点において一本筋が通っています。
中国への経済的依存が引き起こした世界経済の構造変化
今回の関税政策は「このままではアメリカは破産する」というトランプ氏の主張に基づいたものです。トランプ氏は、これを現政権で突然言い出したのではなく、オバマ政権時代からたびたび指摘しており「債務上限」問題が議論されていた際に「米国はギリシャのようになる」と警告していました。
とはいえ、多様な問題を抱えながらも変わらず豊かな米国。「またいつもの選挙向けの“トランプ節”だろう」と、多くの国民は選挙戦におけるトランプ氏の定番レトリックと受け止めていました。
でも、実際のところ、財政破綻の可能性は誇張ではなく、米国が抱える深刻な問題なのです。その根源を深く掘り下げていくと、ある構造的な脆弱さ、いわば米国経済の「アキレス腱」が見えてきます。それは「中国への経済的依存」です。
そのあたりを、ビジネス/テクノロジーアナリストのベン・トンプソン氏が4月7日に公開した「Trade, Tariffs, and Tech」で丁寧に解説しています。これは米国人による米国人のためのトランプ関税の分析ですが、トランプ政権の動向に世界中が固唾をのむ今、私たちにとっても他人事ではない、重要な視点を与えてくれます。
少し歴史の教科書をめくってみましょう。第二次世界大戦後、世界はブレトン・ウッズ体制のもとで復興への道を歩み始めました。
米国はその巨大な消費市場と「ドル」という基軸通貨をテコにして、世界の成長エンジンとなり、欧州や日本の復興を後押ししました。海外諸国はアメリカに製品を輸出し、その儲け(ドル)でアメリカの国債を買う……。そんな「富の循環」が生まれたのです。
これは米国の負担が大きいシステムでしたが、当時の米国経済は他を圧倒するほど巨大だったので、大きな問題とはなりませんでした。
しかし1971年になると、このシステムは自らの重みに耐えきれなくなり、ニクソン・ショックによる金ドル交換停止措置がとられ、ブレトン・ウッズ体制の通貨管理システムは崩壊します。それでもなお、ドルの基軸通貨としての地位は揺るがず、むしろ米国の貿易赤字と財政赤字が構造的に拡大しやすい状況が生まれてしまいました。
そして、その流れに決定的な変化をもたらしたのが、2000年代以降の中国の世界経済システムへの本格的な参入でした。安価で巨大な生産能力を持つ中国と、まるで無尽蔵かのように借金を重ねられる米国。
この組み合わせは、米国民に安い消費財と低金利という「蜜月」のような恩恵をもたらしました。しかしその裏側で、アメリカ国内の製造業はどんどん空洞化し、競争力を失っていったのです。
問題は、単に「人件費が安い」だけではありません。長年かけてアジア、特に中国に蓄積された製造ノウハウやサプライチェーン・エコシステムは、もはやアメリカが簡単に取り戻せないものになっています。
中国の労働コストが以前より大幅に上がった今でも、製造業における中国の優位性は、むしろ加速しているようにすら見えるのは、世界の経済構造そのものが大きく変わってしまったからです。
トランプ関税は「正しい処方箋」なのか?
現在のグローバル経済システムが中国に過度に依存しており、この状態を持続するのは不可能だという問題意識は、保守派だけでなくバイデン政権も共有していました。トンプソン氏も、中国への依存を減らし、アメリカの製造業を再び活性化させようとする「包括的関税」の考え方自体には「理屈の上では一理ある」と認めています。
しかし、理屈として正しくても、それが現実世界で有効な「処方箋」になるとは限りません。トンプソン氏は、現状でいきなり「包括的関税」という荒療治を施すことには、かなり懐疑的な目を向けています。その理由として、彼は大きく3つのポイントを挙げています。
国民に「覚悟」はあるのか?:世界経済の秩序の再構築には、相当な痛みを伴います。トランプ大統領は国民に「忍耐」を求めていますが、関税合戦が始まった途端に株価は暴落し、あれだけ大規模な抗議デモが起きたわけです。本当に国民は耐えられるのでしょうか?
もっと良い「治療法」があるのでは?:経済成長を直接促す方法は他にもあります。例えば、規制緩和を進めたり、誰もが公平にチャンスを得られる環境を整えたりすること。特にAIのような新しい技術が花開こうとしている今、コストカットや貿易再均衡に政治的エネルギーを注ぐのは、大きな機会損失ではないか、と指摘しています。
複雑で治療困難な「患者」:今の経済システムは、確かに欠陥はあるかもしれませんが、何十年もかけて築き上げられてきた複雑なシステムです。簡単に修正できる代物ではありません。診断で問題を見つけられても、治療できるとは限りません。下手に手を出せば、かえって大混乱を招きかねないのです。過去の歴史において、大きな戦争後に新しい経済システムが生まれてきたのには理由があります。古いものが破壊された後の方が、新しいものを構築しやすいからです。
グローバル経済の構造問題という「病」を認識しながらも、その治療法として提案された「手術(包括的関税による強制的なシステム変更)」は、あまりにもリスクが高すぎるというのがトンプソン氏の見立てです。
「トランプ氏が提案したいかなるものよりも、はるかに痛みを伴うシナリオ(例えば、中国による台湾侵攻のような地政学的リスクの高まり)が存在する」と警告します。関税という「手術」が、予期せぬ合併症を引き起こし、取り返しのつかない事態を招く可能性があるというわけです。
製造業を国内回帰させるためには段階的で複合的な取り組みが必要
では、どうすればいいのか?トンプソン氏の提案は、少し意外に聞こえるかもしれませんが、「問題の先送り」という選択肢です。例えば、AIチップの輸出規制を少し緩めて、経済的な相互依存をむしろ深める。半
導体製造などで重要な役割を担う台湾が、中国にとってもアメリカにとっても「必要不可欠」なパートナーであり続けることが、かえって軍事的な衝突を避ける「抑止力」になるのではないか、という考え方です。
もちろん、これはアメリカにとって根本的な解決策ではありません。ドルが基軸通貨である限り、貿易赤字が積み上がり、製造業が弱体化しやすいという構造的な問題は、依然として残ります。
それでもなお、米国内でこれほど関税政策への反発が強いのは、まだ「先送り」できるだけの体力、言い換えれば「猶予」が残されていると感じているからなのかもしれません。
結局のところ、製造業を国内回帰させるためには、段階的で複合的な取り組みが必要です。税制や補助金制度の抜本的な見直し、イノベーションを阻む規制の大胆な緩和、そして何より、新たな製造業の時代を担う技術者や技能者を育てる実践的な教育プログラムの確立……。
AIやロボティクスといった破壊的技術への積極投資と、それらを活用した高付加価値なものづくりへの転換も欠かせません。そして、この経済構造の変革、社会の分断、そして国際秩序の変化という課題は対岸の火事ではなく、形は違えど日本もまた直面している現実なのです。
最後に、今回の関税政策について、金融関係者の間で「トランプ政権が金利を下げるために、意図的に株式市場を暴落させたのでは?」という声も囁かれています。2025年には約9兆2000億ドルもの米国債が満期を迎えることを考えると、一理あるのかもしれません。
ただ、そうだとしても、やはり包括的関税という手法は失敗のリスクが高すぎます。また、仮に米国債の借り換え成功や「第2のプラザ合意」にこぎつけたとしても、米国が抱える構造的な問題を解決しなければ、持続不可能な状態がただ長引くだけになってしまいます。