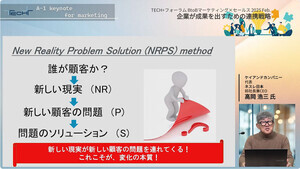自社の商品やサービスを「その企業ならでは」と認識してもらう企業ブランディングへの注目が集まっている。国内外の競争激化や物価の上昇などが背景にある。しかし、大企業と違い、中小企業がブランド戦略を打ち出すのは容易ではないとされる。こうした中で、インターネットを活用してコストを抑制しつつ、効果的なブランディングを実施する中小企業やB to B(企業間取引)企業も出始めている。この連載では、ITなどを活用してブランディングを行っている事例を紹介する。
最終回となる第35回は、中小企業の経営コンサルティングや事業再生を手掛けるJライフサポート(東京都 千代田区)を取り上げる。同社は動画サイトに経営者が出演し、資金調達など事業再生の具体的な方法を詳しく解説。多くの登録者を獲得し、自社のブランディングやクライアント確保につなげている。三條慶八社長は企業ブランディングの意義について、「他社にはない自社の得意技を理解し、それを潜在顧客に知ってもらうことだ」と話す。聞き手はZenkenの本村丹努琉(もとむら・たつる)氏。
1960年兵庫県神戸市生まれ。経営に悩む中小企業経営者に向け、会社経営と再生のノウハウを提供する経営アドバイザー。阪神淡路大震災により140億円の負債を抱えた企業を自らの手で再生させ復活を果たす。その経験をもとに「何があっても大丈夫!」をモットーに、経営者とともに闘う姿勢を貫き、真に会社と家族を守る経営支援を行う。
日本の中小企業経営者は大企業と異なり失敗後の再起が極めて困難な環境にあることから、失敗しても再挑戦できる社会を構築することを人生のミッションとする。現在はJライフサポートの代表として経営者の再生支援に取り組み、企業の持続的発展を支えるアドバイスを提供している。主な著書に「経営の極意」(フォレスト出版)などがある。
ポイント
①企業ブランディングとは自社の得意技を知ってもらうこと②社長がYouTubeなどの動画で事業再生の方法を解説しブランディングに成功
③動画配信の前に書籍やFacebookなどで一定の知名度を獲得
④自分を必要としてくれる人にブランディングしサービスすることが重要
本村:貴社は中小企業の経営コンサルティングなどを手掛けています。事業の概要と強みを教えて下さい。
三條:当社は中小企業の経営コンサルティングや事業再生のサポートを手掛けています。クライアントは全国に50~60社あり、業種はITから物流、製造業、建築などさまざまです。当社が他の経営コンサルティング会社と違うのは、「私がクライアント企業の社長ならこうする」という立場でアドバイスをする点です。月に1度はクライアントの経営者と対面で面談し、ときにはプライベートも含めて心配事の相談に乗るなど精神面でも支えるようにしています。
一般的なコンサルタントは、一流大学を卒業している一方で自分では商売をしたことも借金をしたこともない人がほとんどです。もちろん、自身自分が経営する赤字会社を再生した経験もありません。その点が、経営者の私とは大きく違います。
私はかつて兵庫県神戸市で不動産賃貸業と飲食業を経営し、順調に成長させていました。しかし1995年の阪神・淡路大震災により数十億円の借金を抱え、「早ければあと3年で倒産する」というところまで追い詰められました。そこから事業を再生させた経験があります。こうした経験に基づいた具体的な助言ができるのが私の強みだと思っています。経営面のアドバイスだけでなく、「頑張ればなんとかなる」ということも伝えられるため、多くの経営者が私の話を聞いて「元気をもらえる」と言ってくれます。
本村:中小企業のブランディングには、どんな意義があると考えていますか。
三條:ブランディングとは、自社の「他社にはない得意技は何か」を知ってもらうことです。しかし、中小企業経営者の大半は自社の強みがわかっていません。私はコンサルティングをする際に「お客様はなぜあなたの会社や商品を選んでいると思いますか」と質問するようにしています。その答えこそが強みであり、それを知ることがブランディングの第一歩になります。
本村:まずは自社の強みを知ることが重要ということですね。ただ、特に中小企業の場合は実際にブランディングをするのが難しいという声もあります。
三條:確かに中小企業のブランディングは容易ではありません。ただ、中小企業は大企業のようにみんなに知ってもらう必要はありません。少人数でも根強いファンがいれば、継続的に収益をあげられます。それこそが中小企業の生きる道だと考えています。
一方、老舗の中小企業は長年培ってきたブランドがかえって邪魔しているケースがあります。過去の伝統や成功体験にしがみつきすぎて、もうからなくなっているのです。老舗企業は時代に合わせてリブランディングしていかなければ、しがらみのない新しい企業に負けてしまうことがありえます。
本村:企業ブランディングの成功例は。
三條:YouTubeやTikTokなどの動画配信です。特にYouTubeは3年間で累計約300本の動画を投稿しており、チャンネル登録者数は1400人まで増えました。動画では、潜在顧客がどんな話を聞きたいかニーズを調べた上で、業績改善の方法などを私が解説しています。
例えば「会社の業績が悪化しており事業を再生したい」といった場合、借金返済のリスケジュールの方法、資金の再調達の方法、中小企業活性化協議会の活用などを解説します。このほか、「代位弁済の怖さ」「個人保証の問題点」「資金繰りの方法」などといったテーマで動画を配信しています。
YouTubeは書籍と違って制約が少なくある程度は自由に発言できるので、多くの人が視聴してくれます。配信を始めてから3年間で100件以上の問い合わせがありました。2月後半に投稿した動画では1週間で10件程度の問い合わせがあるなど、反響はさらに大きくなりつつあります。問い合わせの内容は「YouTubeを見た。当社の現状に不安を抱えており相談できないか」といった具合です。
また、TikTokでは私が自社を再生した様子をドラマ仕立てで配信しています。動画はホームページにも掲載しています。顧問先の元テレビ局員の方がサンプルとして無料で作ってくれたもので、当社のブランディングに貢献してくれています。ブランディングの方法は時代とともに変わってきました。今は動画の時代で、文字はなかなか読んでくれません。動画を活用したり、SNSで拡散する方法を考えたりする必要があると思います。
本村:動画を活用してブランディングしようとしている企業は多くありますが、必ずしも貴社のように成功しているわけではありません。動画配信で工夫しているポイントはありますか。
三條:もちろん、動画を配信しても多くの人が視聴してくれるとは限りません。私の場合は、動画配信の前に著書の商業出版やFacebookを開設したことがプラスになったように思います。著書は、ある出版社の社長と面談したところ、出版していただけることになりました。
自費出版ではなく商業出版だったので、読者からも信頼できると思われたのかもしれません。その社長に勧められてFacebookを開設して事業再生関連の解説をアップしていたところ、現在はフォロワーが約2500人にまで増えました。こうした活動が当社の知名度も向上させ、動画を視聴してくれる人たちが増えたのではないかと思います。
本村:三條社長の話をうかがっていると、自分を必要としてる人と自分が貢献したい人の両方を考えて、ブランディングやマーケティングをしているように思います。その考え方は現代に合っているように思います。
三條:中小企業は大企業のように全国の多くの人たちを対象にブランディングする必要はありません。自分を必要としてくれるコアな顧客にどう喜んでもらえるかを一番に考えるべきだと思います。
本村:自社を信頼してくれる顧客の要望に全力でこたえるのが大事ということですね。ブランディングで失敗した例はありますか。
三條:創業当初は手当たり次第にブランディングやマーケティングのためのツールを試していました。例えばFAX広告やメール広告です。たくさん送れば当たるかと思っていましたが、残念ながら成果はほとんどありませんでした。
失敗の原因はいくつかありますが、1つ目はターゲットを明確に打ち出せていなかったことです。そのため、届けるべき潜在顧客に情報を届けられなかったと思います。2つ目はお客様の目線を大切にできなかったことです。大量にメールを送るだけのやり方には、こうした大事な視点が欠けていました。
また、私自身の信頼性や認知度が乏しいことも、ブランディングにマイナスになっていると感じました。例えば、私が事業再生などを成功させた企業経営者がその情報を発信してくれれば、ブランディングに成功していたかもしれません。こうした反省が動画配信での成功につながりました。
(編集協力 P&Rコンサルティング)