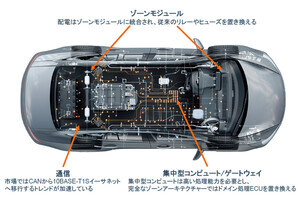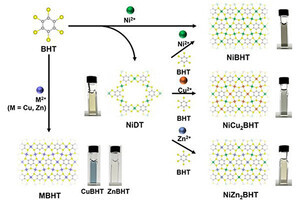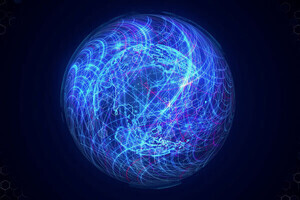2024年11月5日(米国時間)に行われる米大統領選。民主党指名候補のカマラ・ハリス氏と共和党指名候補のドナルド・トランプ氏の熾烈な一騎打ちが予想されている。
現在、米国内の世論調査では両候補の支持率は拮抗しており、どちらの候補が次期大統領に選出されるのかを世界中が注視しているのは言わずもがなだろう。米大統領選挙の結果が日本の経済・産業界に与えうる影響とは、一体どのようなものがあるのだろうか?
今回、10月18日にみずほリサーチ&テクノロジーズが公表した「米大統領選を受けた経済・産業への影響~国民の『内向き化』が招く米国第一主義の帰結とは?」のレポートをもとに、日本のマクロ経済・市場への影響に関する部分を抜粋し、AIと半導体業界に関するものを紹介する。本稿はAI編としてお伝えする。半導体編はこちらを参照。
日本企業にとってはハリス氏当選が望ましい?
レポートによると、日本企業はハリス氏の予見性を評価してはいるが、トランプ氏の政策に伴う通商政策や為替変化を警戒しているという。実際、ロイターが日本企業506社(回答者数243社)を対象に実施した7月21~8月9日の調査において「どちらの候補者が経営戦略や事業計画にとって望ましいか?」という質問に対して、ハリス氏は43%、トランプ氏は8%となった。
貿易・投資に目を移している見ると、財務省の資料では日本の2023年における国別対外直接投資残高(約100兆円)、UN Comtradeの資料による2023年の国別輸出額(約1500億ドル)ともに米国がトップで最大のパートナーとなっており、投資・輸出いずれも自動車産業との結びつきが強い。
仮に、トランプ氏が提唱する大半の外国製品への関税を一律に引き上げる「普遍的基本関税」を導入した場合、輸出の大幅な減少が見込まれるという。また、米国企業全体の海外調達比率は9.3%だが、在米日本企業は50%に達しており、関税引き上げに伴う影響を受けやすい構造になっている。
金融市場は過去の傾向を鑑みると、大統領選実施前は米国からの資本が流出(ドル安/米株安)する傾向にある反面、実施後1~2か月後には元の水準に回復することから、日本では実施前は円高・株安、実施後は円安・株高が起こりやすい状況になっているとのこと。
株式市場は各候補者の政策を意識した値動きとなっており、トランプ氏の銃撃事件勅の相場は化石燃料や金融、不動産など、ハリス氏が出馬表明直後の相場は再生エネルギー、住宅関連の株がそれぞれ上昇した。トランプ氏が再選し、保護主義を強めた政策を展開した際は株価の下押し要因になるという。
ドル・円相場はトランプ氏が再選してインフレ圧力を生む政策を実行し、米国の金利上昇を伴えば再び160円近くまで円安が進行するリスクがあるようだ。円安が進行した場合、輸出比率が高く、海外子会社の配当も円安で拡大する大企業・製造業の利益率が大幅に改善する一方で、価格転嫁を満足にできない中小・製造業では収益を圧迫するおそれがある。特に鉄鋼や化学、機械、自動車など輸出比率の高い業種で大企業と中小企業の差が鮮明だとしている。
日本の産業全体への影響
続いて、産業全体の影響について見ていこう。ジョー・バイデン大統領はトランプ前政権の環境・エネルギー政策を修正し、EV(電気自動車)や蓄電池、クリーンエネルギー関連の投資を促進しており、ハリス氏が当選した際は現政権の政策が多く継続され、現在の事業環境は継続する見通しだ。
一方、トランプ氏は現政権の政策巻き戻しを示唆し、自国主義の先鋭化や政策の予見が不確実である点は大きな不安要素だと指摘。
2022年8月に成立したIRA(インフレ削減法)の修正や排ガス規制の緩和、化石燃料への優遇措置復活などが見込まれ、中長期的には環境対策が進む流れは変わらないものの、投資時期などを見極めることが重要だという。
また、対中政策などの通商政策の方向性に大きな変化はないが、自国主義が先鋭化する状況下において、米国にコミットして米国で稼ぐか、米国を離れてそれ以外の地域で稼ぐかの選択を迫れる可能性があるとのことだ。
AI業界への影響はいかに?
では、AI業界についてはどのような状況なのだろうか?バイデン政権下では、米国がAIで世界をけん引するべく、開発における健全性の担保を中心に連邦政府機関や民間セクターのAI安全基準を扱うガイドライン、フレームワークの導入を推進している。
さらに、ハリス氏当選時は、バイデン政権の方向性を引き継ぎつつ「AI総司令官(AI Czar)」としての経験に加え、カルフォルニア州司法長官時代からのテック業界とのネットワークを活かし、連邦AI規制法案の成立などを通じてAI産業は健全な成長に向かう可能性があるという。
ハリス氏による規制強化が実現すれば、企業が規則に沿ったコンプライアンス遵守を推進しやすくなるほか、安全性表示が消費者の信頼を高めることからAI製品が普及する可能性がある。
また、政府からの資金と契約が増加する可能性が示唆されており、産業育成につながるとともに、AIソリューションやベンダー側にもメリットとなる。ただ、コンプライアンス関連の費用が発生し、参入障壁が高まる可能性も指摘されている。
他方、トランプ氏が再選した際は連邦政府の研究予算、特に国際的な連携に関する配分が削減され、防衛に重点が置かれるとの見立てだ。また、同氏はバイデン大統領のAI大統領令を廃止し、官民パートナーシップの弱体化が懸念されており、国内防衛部門にはメリットが生じるものの、AIの熟練人材ビザの発給削減、AIの安全性の不確実性といった全体的なAI産業の成長が停滞する可能性があるとしている。
こうした流れは現在のAIに関する日米の連携を弱め、日本のAI産業も成長のスピードが鈍化することが想定される。現在、進行中の日米の連携としてはAI防衛システムの共同開発や1億1000万ドルを投じる大学と民間開業の研究開発協力の縮小、米国企業と連携している日本のAIベンダーの成長鈍化といったものがある。
以上のように、両候補の当選した場合の政策の違いは明らかだ。ハリス氏であれば、現行の政策を引き継ぎつつ、バイデン大統領が実現できなかった政策に努めるだろう。一方、トランプ氏の場合、自国主義への回帰が鮮明となっており、日本企業では経営戦略や事業計画の見直しに迫られる可能性が高い。