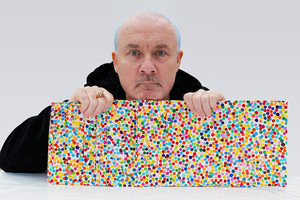連邦政府の政策変更の発表に驚かされることは少ない。事前に演説で匂わされていたり、親しい記者にリークするなどしてメディアや人々の反応を見た上で実行に踏み切るからだ。しかし、8月25日のホワイトハウスの科学技術政策局(OSTP)の発表は晴天の霹靂、大きなサプライズだった。
連邦機関の助成を受けた研究の成果について、査読済み論文の最終原稿が出版されると同時に誰でも無料で自由に利用できるようにする新方針を打ち出した。論文の基礎となるデータについても共有を求めている。関係する政府機関は新方針に従った新ポリシーを2024年末までに固め、2025年末までに実施に移す。
この新方針に至る背景を説明すると、研究者は長年、研究成果を論文という形で学術誌に投稿して世に発表してきた。そして、学術誌の出版社は図書館などと購読契約を結ぶ「購読料」モデルで収益を上げてきた。しかし、それでは掲載された論文を読めるのは購読料を支払っている図書館などを利用できる人達だけ。購読料モデルによって情報と知識の流れが妨げられ、研究の輪の広がりや活発な議論の機会が損なわれているという批判が長く上がっていた。
公的助成を得ている研究の場合、米国の納税者は研究の資金に協力し、研究成果を利用するために再び支払う”二度払い”になる可能性もある。1990年代後半から、公的資金による研究への自由で迅速なオープンアクセスを求める声が高まり、高速インターネットの普及でそれが加速。学術情報の流通における米国の価値を保ちたい政府もオープンアクセス化を支持した。そして出版社との妥協点を探る綱引きの末、出版から1年後に公的データベースに登録されてアクセスできるようになり、今に至る。新方針は1年間のエンバーゴも置かない即座のオープン化を求めている。
出版社の多くは即座公開に理解を示している。だが、政府の介入に批判的だ。25年以上前にオープンアクセスの議論が本格的に始まった頃は、安定して高収益を上げられる購読モデルを脅かすオープン化に激しく抵抗したが、今は変化の必要性を受け入れ、研究者から投稿料を徴収する「投稿料」モデルへの転換を進めている。例えば、16の学術誌を発行している米国微生物学会(ASM)はすでに6誌をオープンアクセス化させており、残りについても2027年までに移行させる計画である。
オープンアクセス化は着実に進んでいる。ただ、歩みが遅いのも事実。バイデン大統領は、オバマ政権で副大統領だった頃から即座公開の実現に取り組んできた。2016年の演説で、「納税者はがん研究に年間50億ドルを出資していますが、出版後にそのほぼ全てが(有料の)壁の後ろに置かれています。これでどのように(科学の)プロセスがより速く進むのか、教えてください」と指摘していた。それから6年である。その間にCOVID-19の感染拡大が起こった。出版社はCOVID-19に関連する全ての論文を一時的にオープンアクセスにすることに合意し、それがオープン化の効果と価値を実証する結果になった。
政府は新方針でオープンアクセスではなく「パブリックアクセス」という言葉を使っている。出版社への影響に配慮し、バランスを図っているのだろう。
新政策が最終的に学術誌、出版社、研究者にどのような影響を与えるか、現時点で予測するのは難しい。規則はまだ固まっていないので、査読を経て受理されたほぼ最終バージョンを公開することで条件を満たせるようになる可能性もある。論文は購読モデルで提供する。また、他の場所で無料で読めるとしても、出版社がより優れたインターフェイスや検索機能、他のサービスを提供すれば、図書館は購読料を支払うことを望むかもしれない。
コストを誰が負担するようになるかも重要なポイントになる。投稿料モデルが広まれば、資金力が乏しい機関や発展途上国で研究する著者の出版をより困難にしてしまう可能性がある。OSTPはブログ投稿で「研究エコシステムにおいて脆弱なメンバーに対する支援とともに、パブリックアクセス政策を確実に実施したい」としている。例えば、いくつかの政府機関がすでに行っているように、研究者がオープンアクセスの出版費用を助成金で賄うことを認めたり、パブリックリポジトリの拡大に資金を提供するといった対策が考えられるが、変化を急げば望ましくない歪みが出やすくなる。変化がはらむ課題について政府は甘く見ていると懸念する声もある。
Scienceに対して、ASMのCEOであるStefano Bertuzzi氏は、学術界において米国は「800ポンドのゴリラ」だと指摘している。「800-pound gorilla in the room」(部屋の中にいる800ポンドのゴリラ)、無視することは不可能な存在、避けられない存在という意だ。米国の新方針であっても、日本を含む他の国も見過ごすことはできない。課題を含めて、変化の波紋は世界に広がる。