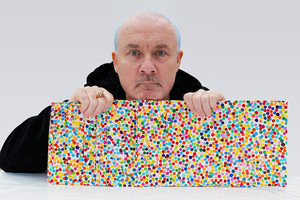「ランチの場所を探すとき、18〜24歳の約40%はGoogleマップやGoogle検索ではなくTikTokやInstagramを開く」。Fortuneの「Brainstorm Tech」カンファレンスにおいて、Googleのプラバカール・ラバガン氏(Knowledge & InformationのSVP)が明らかにしたGoogleの調査結果である。
ベビーブーマー、X世代、ミレニアル世代にとって、Googleはネットで何かを探すときに最初に訪れる場所だった。ところが、Z世代に対してGoogleはそんな場所でなくなろうとしている。そこで同社はひと月前から「Let’s Internet Better,」というZ世代をターゲットにしたキャンペーンを展開している。
ゆるいアニメーション動画で、ネット上の誤った情報、詐欺やなりすましへの注意を喚起する。キャンペーンロゴはNBCのファミリーチャンネルで1980年代に放送された教育広告「The More You Know」を模していて、15秒のビデオには「Should you put slugs on your face」(顔にナメクジをつけるべき?)とか、「Did someone just buy the sun?」(誰かが太陽を買ったの?)など、バイラルマーケティングを皮肉ったタイトルがつけられている。Z世代の感覚やユーモアに共鳴するように作成されている……のだが、見ていて違和感を覚える。そして、その違和感こそGoogleが今レガシーになろうとしている理由である。
Z世代をターゲットとしたキャンペーンの内容がインターネットリテラシーであるというのは、InstgramやTikTokのような限られたインターネット・コミュニティに検索対象を絞り込む危うさを指摘しているのだろう。しかし、Z世代は、InstagramやTikTokだけを情報源にしているわけではない。むしろ他の世代に比べて、ネット上の誇張やフェイク、誤った情報への警戒感が強く、InstagramやTikTokを含む複数の情報源にあたり、相互参照して情報の価値を見極める力に長けていることが様々な調査で明らかになっている。InstaramやTikTokを最初に開く40%がGoogleマップやGoogle検索を使わないわけではない。正しくは、GoogleマップやGoogle検索に頼らず、必要ならそれらも使っているのだ。
「Let’s Internet Better,」のようなインターネットリテラシー・キャンペーンが必要なのは、Z世代ではなく、むしろGoogle検索頼みでGoogle検索しか使わなかったり、ソーシャルメディアの偏った情報の影響を受けてきた世代の方である。だから、Z世代向けの演出で「Let’s Internet Better,」の内容では、Googleが「近頃の若者は〜」と語っているように思えてしまう。
Facebookの急成長期に重要な役割を果たしたサム・レッシン氏が、Instagramの"TikTok化"に関して「デジタルメディアの"アテンション"獲得の食物連鎖」を示し、全てのデジタルメディアはそれに従った進化をたどっているとしている。
- インターネット以前:「People Magazine」時代
- 「あなたの友人」からのコンテンツが「People Magazine」を殺す。
- カーダシアン家(有名人/セレブ/インフルエンサーの「友達」)が「本当の友達」を殺す。
- アルゴリズムによるレコメンドがカーダシアン家を殺す(キム・カーダシアンが「昔のInstagramに戻って」と要求←今現在)
- 将来:「アルゴリズム的な"みんな"」を打ち負かす純粋なAIコンテンツ
それを受けて、テクノロジーアナリストのベン・トンプソン氏が以下のように、メディア、AIの役割、UIからデジタルメディアのトレンドの流れを整理した。
- メディア:テキスト → 画像 → ビデオ → 3D → VR
- AIの役割:時間 → ランク付け → レコメンド → コンテンツ生成
- UI:クリック → スクロール(ニュースフィード)→ タップ(Stories) → スワイプ(Reels、TikTok)→ Autoplay
今でもテキストや画像がWebで欠かせないように、Web成長期からの検索エンジンであるGoogleは今後も重要な役割を果たしていくだろう。だが、それが全てではない。2010年代以降のネットの進化によって、ネットの利便性が向上し、より効率的に情報を得られるようになり、新たな体験も生まれた。
レッシン氏の食物連鎖におけるコンテンツの流れの中で、Googleが検索エンジンとしてデジタルメディアに対して巨大な力を発揮してきたのは(3)まで、いま同社のサービスでZ世代との直接的な結びつきはYouTubeの方がはるかに強い。Facebookも同様に同サービスは(2)にとどまったまま、Metaのサービスの進化の牽引役はInstagramに移っている。
今ネットは大きな転換期を迎えようとしている。テック企業の古い採用面接問題に「馬くらいの大きさのアヒルと、アヒルくらいの大きさの馬100匹のどちらで戦うか」という問題がある。ランキングの世界では誰もがフォローする馬サイズのアヒルが貴重だったが、優れたコンテンツが力を発揮するレコメンドの世界では100頭のアヒルサイズの馬の方が貴重だ。そうした大きな変化の中で、停滞を抜け出せずにいるGoogleやFacebookのレガシー化が加速している。