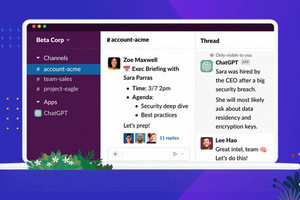チーム・コミュニケーションを円滑にするビジネスのサポートツール「Slack(スラック)」。コロナ禍におけるリモートワーク文化が進んだことも相まり、近年は多くの企業が導入を始めている。では、Slackはどのように企業のコミュニケーションを円滑にし、生産性の向上に役立っているのだろうか。今回はグループ会社全体でSlackの上位ラインセンスである「Enterprise Grid」を導入しているさくらインターネットの事例を紹介する。→過去の「Slackで始める新しいオフィス様式」の回はこちらを参照。
メール文化からSlackへと完全移行した
さくらインターネットがSlackを導入したのは2016年。全従業員へ有料のビジネスプラスプランアカウントを付与するようになったのが始まりである。有料アカウントを導入するきっかけについて、同社 技術推進統括担当 執行役員 兼 最高情報セキュリティ責任者(CISO) 兼 最高情報責任者(CIO)の江草陽太氏は次のように語る。
「全社的にはメール文化だったのですが、社員同士でも『お疲れ様です』という定型的な枕詞を打ってしまうほど“遠回り”なコミュニケーションに、手間を感じていました。その時、もともとエンジニア部門で使っていたSlackのフリープランの使い勝手の良さに、魅力を感じていました。メールを代替する全社的なコミュニケーションツールを複数検討したうえで、データ保存量も大きく、社内のSSO(シングルサインオン)認証システムとも連携できるビジネスプラスプランの導入に至りました」(江草氏)
2018年6月には、グループ8社への導入も開始し、ワークスペースの増設に伴いビジネスプラスからEnterprise Gridへとプランを変更した。現在1,000人強ものアカウントを有するさくらインターネット。なぜグループ全社での導入に踏み切ったのだろうか。
「Slackを使うことでオープンなコミュニケーションが発生し、情報を蓄積できることに価値を感じていました。グループ各社にもその波が広がればと思い、全グループ導入を決断しました。経営幹部にも『メールよりやっぱりSlackだよね』という共通認識があり、導入へ踏み切るのはかなりスムーズだったと思います」(江草氏)
安全にオープンコミュニケーションを遂行するためのルールづくり
現在は、おおむね1社に1つ、計9つのワークスペースを運用しており、さくらインターネット本体では江草氏を含む5人でワークスペースの管理を行い、グループでは各社2~3人ずつが管理者の役割を担っている。ユーザーは基本的に出向者を除き、所属する会社のワークスペースにしかアクセスできない。
チャンネルは基本的に部門・案件ごとに開設し、現在は本社だけで3,000弱ものチャンネルがアクティブに動いている。なんと雑談系の「#times」チャンネルだけでも350ほどあるのだという。かなり活発に機能しているさくらインターネットグループのSlackだが、どういった運用ルールを設けているのだろうか。
「オープンコミュニケーションを前提としているからこそ、プライベートチャンネルを開設する場合は、Slack上で申請してもらいます。ただ申請のハードルは低いですよ。『個人情報を扱うから』というような明確な理由があれば、基本的に申請を通すようにしているんです。『これってオープンでやりとりできるのでは?』と自発的に気づいてもらう目的もありますね(笑)」(江草氏)
また、江草氏は「完全に禁止してもDMが増えるだけなので、申請制にしました。グループ外のゲストをSlack コネクトで招待するときも申請制にしています。SSOでゲストも管理していて、NDA(秘密保持契約)の同意内容や利用期間などを記録しています。現在68もの他社のワークスペースとコネクトしているんですよ」と説明する。
そのほかにもアプリを利用する際は申請を必要とするなど、セキュリティにまつわるいくつかのルールが存在するさくらインターネット。ただ、セキュリティの観点以外では「あまり厳格にルールを設けず、自由さを持たせることでベストプラクティスが生まれることを期待しています」と江草氏。Slackによるオープンコミュニケーションを推進したことで、業務環境にも変化が訪れた。
「社外の企業とやりとりする場合でも、契約の際に『Slackでやりとりしませんか』とお誘いすることが多くて。完全移行とまではいきませんが、社内外ともに、メールでのコミュニケーションはほとんどなくなりました。特にトップダウンで『メール禁止』などのルールは設けなかったものの、メールとSlackが併用されてしまうような事態は避けたかった。各部門の役員と業務フローの変更を計画したり、Slack上で法務や経理の気軽な相談ができるようなチャンネルを開設してもらったり……と、Slackを浸透させるための工夫は凝らしました」(江草氏)
大規模災害への対応とSlack新サービスのローンチ、そして次のステップへ
2018年6月の導入からわずか3カ月ほど経過した2018年9月6日、さくらインターネットで早くもSlackが活躍する瞬間が訪れた。それは、北海道を襲った大地震による大停電が発生した時のことだ。
当時約3万8,000もの顧客に対し、クラウドをはじめとしたインターネットインフラを提供していた北海道の石狩データセンター。同社では9月8日に北海道が復電するまでの2日半、石狩データセンターを停止することなく運用することができたのだ。
その背景には「Slackの導入が功を奏しました。災害が発生したころ、少なくともさくらインターネット本体はSlack中心の業務に移行できていたんです。震災発生の直後からSlackを活用し、現場の状況把握や指揮を迅速に行うことができた。だからこそ、災害対応がスムーズにできたと思います」と、江草氏は振り返る。
2023年現在、グループ全体としても「Slack中心の業務」が浸透しているさくらインターネット。コロナ禍を通し、リモートワークでも総務が円滑に機能するような独自のサービスも誕生した。
「ある時、総務部から『名刺などの荷物を、住所を匿名化して郵送できるようにしたい』という要望が挙がったんです。社員同士が住所を共有することは会社の規定上難しく、従来では近くの営業所宛に郵送し、受け取り側が取りに行く……という少々面倒なルールを設けていました。そこで、ヤマト運輸さんがフリマサービス向けに提供している匿名での配送サービスを応用して、Slack内で送り先のユーザーを指定することで、お互いに住所を知らないまま荷物を送ることができるサービスを社内向けにローンチしました」(江草氏)
さくらインターネットでは、この宅配便の取次ができるSlackアプリを2023年2月8日より外部に向け提供開始。グループ内でも部門を横断し活用機会の多いアプリが、他の企業へどう波及していくかを期待する。その一方で、長年Slackを使い込んできたからこそ見えてきた課題もあるという。
「パブリックチャンネルでやりとりして問題のない内容であっても、心理的に『大勢に見られるのは嫌だから』とDMで連絡してしまう傾向がるのは課題です。もっとオープンにコミュニケーションをしてもらえるような工夫は、これからも考えていきたいです。その半面、個人情報の扱いにも慎重にならなければならず、セキュリティとのバランスはとり続けていければと思っています。Slackは、今や弊社のさまざまな情報を集約する重要なプラットフォームの役割を果たしています。テキストベースのやり取りが履歴として残っていくので、私自身も気になったツールをSlack内で検索してみて、Tipsを得ることが多々あるんです。オープンなコミュニケーションプラットフォームとして機能し続けることで、よりグループ全体の知見が蓄積されていくことに期待したいです」(江草氏)