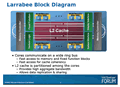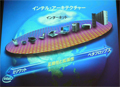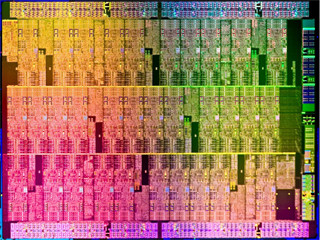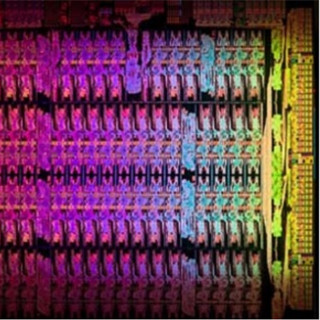先月、米有力紙ニューヨーク・タイムズに掲載されたシリコンバレーのベテラン記者ドン・クラーク氏の記事が目を引いた。「IntelはどうしてAIチップブームに乗り遅れたのか?」と題するこの記事は、シリコンバレーを中心としたテック産業を40年間取材したクラーク記者ならではの長い経験とそこから生まれる鋭い視点で、現在大きな問題を抱えるIntelという偉大な半導体企業の本質を解説している。
約2.5兆円の巨大赤字を計上したIntel
Intelの第3四半期の決算結果は過去最大166億ドル(約2.5兆円、1ドル=150円換算)の赤字を計上して大きな話題となった。
稼ぎ頭のパソコン/サーバー用のCPUのビジネスはAMDにシェアを奪われ相変わらず振るわず、現在データセンター分野の成長を牽引するGPU製品での遅れで、生成AIブームに完全に取り残されている状態だ。そのうえで、ファウンドリ会社の将来に向けたキャパシティーを増強すべく果敢な設備投資を継続している。今回の決算発表の大赤字は、2017年に買収したモービルアイののれん代の償却、今年中に完了するという1万5000人のリストラ費用など、諸々のネガティブ費用をすべてまとめて計上した結果である。CEO、Pat Gelsingerの決断は経理上の負の遺産を全て清算し、今後の成長計画の結果をはっきり示そうという決意の表れで、巨大赤字にもかかわらず株価は上昇した。
シリコンバレーを40年以上見てきたドン・クラーク記者の記事
今回のIntelの決算については幅広いメディアに多数の記事が掲載されたが、先月米国の有力紙ニューヨーク・タイムズに掲載されたドン・クラーク記者の記事は大変に興味深い。シリコンバレーに本拠地を構えたクラーク記者の40年はそのまま、私自身のAMDでの勤務経験を含む半導体関連企業での職歴とほぼ重なる。クラーク記者の名前は以前から目にしていたし、どこかのプレスイベントなどで質問をする姿を見た覚えがある。この記事で興味深いのは何といってもその職業柄、Intelをはじめとする業界の他の企業などの幹部への長年の取材などで得た生の情報を踏まえたうえでの分析だということだ。
IntelがAI半導体ブームに乗り遅れた理由としてクラーク記者が上げる理由は、x86マイクロプロセッサーでの成功体験で築かれたIntelの企業文化と、その成功体験から来る慢心であるという。
IntelはDRAMビジネスからの撤退後、社運をかけて取り組んだx86マイクロプロセッサービジネスの大成功により世界最大の半導体企業として長年業界に君臨したが、その企業文化が外部からの技術導入を排除してしまう負のパターンに陥っているというのがクラーク記者の見立てである。その例として、クラーク記者があげているのが2005年に当時のCEO、ポール・オッテリーニがIntelが取締役会に諮ったNVIDIAの買収計画である。
結局この計画は取締役会で却下され、実現されなかった。当時と現在のNVIDIAの株価を考えれば、「この時買収していたら……」という“タラレバ”話はいくらでもできるが、クラーク記者はその買収が実現していたとしてもIntelがAI半導体で業界をリードすることにならなかったかもしれない、と解説している。
というのも、NVIDIAによるAI半導体ブームが明らかになってきていた2016年に、IntelはAIチップのベンチャー企業Nervana Systemsを4億ドルで買収したが、結局その技術はIntel社内で技術部リソースのサポートを充分に得られず発展することはなかった。それどころか、そのプロジェクトの進行中にIntelによる他のAIチップのスタートアップ企業Habana Labs.の買収が突然決まり(買収額は20億ドル)、Nervanaの技術者たちは結局Intelを去ったという。現在Intelが力を入れているAIチップGaudi3は、このHabana Labs.の技術を基本としていると思われるが、Gaudiチップは発表されて以降、大手顧客の獲得に成功したという話はほとんど出てこない。
私自身、Intelの上層部がNVIDIA買収の計画を画策していたという話は初耳で、同じ時期にAMDがカナダのATi社を買収したことと合わせると非常に興味深い事実である。AMDがATiの技術と組織の取り込みに細心の注意を払って成功させたのとは大きな違いがある。これには企業文化の違いが関係していると思う。
Pat GelsingerとLarrabeeアーキテクチャー
クラーク記者の記事には他にも興味深い事実が書かれている。Intelはx86命令セットで積み上げた技術資産を基礎として、CPUとGPUのハイブリッド型の高速演算処理チップ「Larrabeeアーキテクチャー」を考案した。単純なイメージとしては、枝葉を落とした多数のx86マイクロプロセッサーコアを1チップに集積したアーキテクチャーで、汎用プロセッサーのタスクと高速並列計算を1つのチップ上で実現するというのが基本設計思想であった。
2009年ころ、開発が進められていた初代Larrabee(Larrabee1、開発コード名)は45nmプロセスを採用し、16コアを1チップに統合するもので、第2世代として32nmプロセスで最大24コアを統合する「Larrabee2(開発コード名)」が商品化が計画されていたが、性能などの問題もあり、市場での受けは思わしくなく結局プロジェクトは終息した。そのプロジェクトを率いていたのが当時Senior Vice President and General Manager, Digital Enterprise GroupとしてIntelの技術を知り尽くしたPat Gelsingerその人である。Gelsingerは2009年、Inteを去り、2021年にCEOとして舞い戻ったが、クラーク記者は最近Gelsinger本人へのインタビューを行い、「私は(あのアーキテクチャーで)成功できると信じていた。あの時IntelがLarrabeeを継続していれば、全く違った状況になっていたと思う。しかし、歴史を書き換えることはできない」という言質を取っている。Intelの企業文化とx86アーキテクチャーへのこだわりを象徴する印象深い語りだ。
-

Larrabeeの系譜は、のちにMany Integrated Core(MIC)と呼ばれるアーキテクチャとしてXeonなどと組み合わせて利用するコプロセッサ「Xeon Phi」へと変更され続いた。写真はXeon E5と組み合わせて利用することで1TFlops以上の理論演算性能を提供することを可能とした第1世代Xeon Phi「5110P」 (編集部撮影)
2024年第3四半期の決算発表におけるメディアとのインタビューで、Intel Foundryに閑する質問にGelsingerは「現在鋭意進めている18Aプロセスノードは、2025年下半期に生産を開始する。そこで生産される製品のほとんどがIntelブランドの製品になる。社外の顧客の注文を広く受け付けるのは生産開始から2年後ということになるだろう」と述べた。Intelはあくまで自社のx86製品を大量生産するキャパシティーの構築に集中している模様だ。この姿勢はこの40年変わっていない。